【10-03】魚・膾・刺身
朱新林(早稻田大学大学院文学研究科特別研究員 浙江大学古籍研究所) 2010年 8月31日
拙著『寿司一曲抱玉食 長流和漢幽幽事』で指摘したことがあるが、古代中国において刺身は寿司と同様に、悠久の歴史的淵源と文化的伝統をもち、上は王族や大臣から、下は一般大衆にまで幅広く好まれた。古代中国における刺身の誕生・発展の歴史と文化の伝統を振り返ると、中日の文化交流の過程におけるもう一つの重要な横顔をうかがい知ることができる。その横顔は、私たちの記憶を数千年前の古代中国社会にまでさかのぼらせ、中日間の食文化の伝統には複雑に絡まり合う関係があることを、私たちに教えてくれる。
近現代の中国史では、北方のホジェン族の一部村落に刺身を食べる習俗があり、南方の一部の漢族居住地域にも刺身を食べる習俗が残っていた。しかし国内外の大多数の華人の観念では、刺身は正統的な日本料理であり、その起源が中国にあることを知る人は少ない。実際は、刺身は中国の伝統食の中でも重要な地位を占めており、中国古代の先人たちの食卓にも並ぶ料理だった。
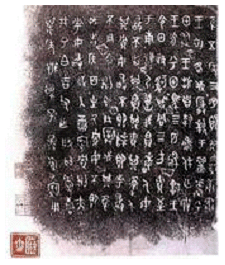
「兮甲盤」銘文
先秦時代には、刺身は「膾」と呼ばれ、『礼記・内則』に「薄い生肉のことを膾という」とあるように、もともとは薄く切った生肉を指した。現有の信頼できる文字記載によると、最も古い文字記録は周宣王5年、つまり紀元前823年までさかのぼる。出土青銅器「兮甲盤」に刻まれた銘文の記載によれば、紀元前823年、周は軍隊を大挙出動して、侵入してきた獫狁族を迎え撃ち、最後は獫狁族を破り凱旋帰国した。この勝利を祝うために、将軍の尹吉甫は張仲らの友人を宴席に招いた。その席には生の鯉の刺身が供された。これが『詩経・小雅・六月』にいう「すっぽんを焼き・鯉を膾にする」である。この時代に「膾」の字は薄く切った生肉を指すとともに、肉を薄く切る動作も意味した。「膾」の材料には、魚、牛肉、羊肉等の肉類があった。しかし秦漢以降、牛肉、羊肉の薄切りは歴史の舞台から徐々に去り、「膾」は専ら魚肉の薄切りを指す名詞となって、さらに「鱠」という文字が派生して特に刺身を指すようになった。指摘の必要があるのは、「膾」と「鱠」がしばしば混用された点である。上述の『詩経・小雅・六月』は中国北方の魚膾(薄切り魚肉)に関する最も古い記録である。
北方と比べると、中国南方における類似の古典文献の出現はかなり遅い。西暦1000年以降に東漢の趙曄才が『呉越春秋・闔閭内伝』に書いたところによれば、呉の軍が楚の都郢を破った後、呉王闔閭は魚膾の宴を設けて伍子胥を慰労した。その席には「魚膾」があったが、これがすでに紀元前505年のできごとであった。これ以降、魚膾は古代中国南北で盛んに食べられる流行食品となり、東漢の応劭による『風俗通義』の記載には、その流行ぶりが表れている。そこには「祝阿では生の魚を食べない」とある。祝阿は現在の中国山東省斉河県祝阿鎮であり、この地の住民が生の魚を食べなかったことが、応劭の目にはすでに変わった習慣だと映っている。このことは逆に、刺身が当時の社会に広く伝播していたことを反証している。
上述の文献では、魚膾は主に王侯将軍を接待しもてなすための珍味として現れた。しかし時代の推移に伴い、刺身は徐々に士大夫や一般大衆の家庭料理になっていった。唐末の夏彦謙による詩『夏日訪友』には、事前に挨拶をせずに旧知の友人を訪ねたときの情景が記録されている。主人が客をもてなす料理の中には鯉の刺身があった。「春の料理にはエビをむき、鯉を下ろして薄切りにする。ハスの色香は美しく、ジュンサイは口当たりが爽やかだ。料理と酒を泥封とし、並べると新しい味わいがある」。宋代の詩人蘇軾と陸游はどちらも刺身が好きで、2人の書いた魚膾に関連する詩はそれぞれ13首と37首にも上る。宋孝宗の淳煕14年(西暦1187年)、陸游は厳州(今の浙江省建徳市)で州の長官に任ぜられた。あるとき郊外で辺り一面の蕎麦の花を目にして陸游はしばらく感嘆し、有名な『秋郊有懐』4首を詠んだ。詩文で彼はかつての農耕生活を思い返しながらこう描写している。「故郷を思い出し、車を下りる。川にはカニが棲み、田には牛が足を沈める。働き終えて夕暮れに帰り、酒を傾ける。細く切った緑色のフナに、赤い花のような鯉」。陸游の若いころ、1日働き疲れた後に刺身を味わい酒の肴とすることは、悠々自適の楽しみであり、そうした以前の暮らしぶりを懐かしんでいる。陸游とならぶ同時代の詩人範成大の詩『田家』でも、「子どもが牛を呼び女は薪を拾う、妻は小川でとれた魚を薄切りにする。背中をむき出した老人が陶淵明と同じ詩人でないと、なぜ言えるだろうか」と刺身を食べる情景が描かれている。
刺身が全国で流行するにつれて、その調味料と調理法にも絶えず改善が加えられた。南北朝時代に至ると、有名な「金齏玉膾」が登場する。これは刺身を食べる時のたれの1種で、中国古代の刺身文化の中でよく称えられる。北魏の賈思勰は、この「金齏玉膾」の作り方を『齊民要術』に記載しており、特にその第8巻の「八和齏」の一節で金齏の作り方を詳しく紹介している。分かりやすく言えば、「八和齏」は一種の調味料で、にんにく、しょうが、みかん、梅干、とうもろこし、炊いたうるち米、塩、みその8種類の材料から作られ、魚膾につけるためのたれである。これは、現在日本の刺身用のたれである醤油とわさびに相当する。このたれはその後隋の煬帝が好み、煬帝は「金齏玉膾とは東南の美味である」と言っている。煬帝は刺身が格別に好きだったことが見て取れる。たれのほか、さまざまな生野菜と和える食べ方もあり、この食べ方ではさらに色彩や造形上の視覚的な美しさが求められた。
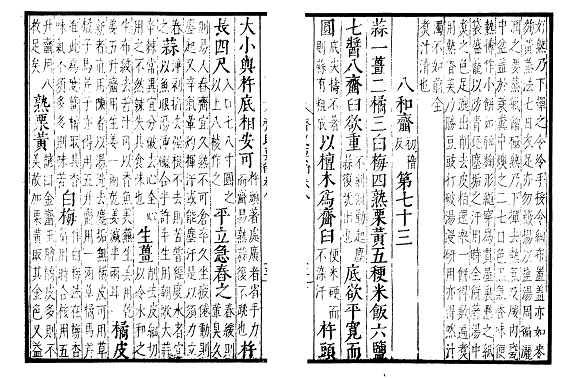
津逮秘書本『齊民要術』第8巻
唐代は刺身の食用が最も盛んになった時期で、当時の社会における魚膾の流行のほどが多くの詩に反映されている。李白の『魯中都有小吏逢七朗以闘酒双魚贈余於逆旅因膾魚飲酒留詩而去(魯の都の小吏が七朗からその宿に酒一斗と魚二尾を贈られ、魚膾と飲酒にちなむ詩を残して去った)』では詩の題の中に刺身が出てくる。王維は詩『洛陽女児行』の中で「侍女の捧げる金の皿には鯉の薄切りが盛られている」と書いている。王昌齢の詩『送程六』には「青魚、雪が舞い、薄切り魚に薬味」とある。白居易の詩『軽肥』には「天池の魚を薄切りにする」とあり、さらに『松江亭携楽観漁宴宿(松江亭で漁見物を楽しむ夜宴)』には「皿には赤い鯉の薄切り」とある。五代後蜀の君主孟昶の妃、花蕊夫人の『宮詞』にも「日中に殿頭が魚の薄切りを求める」とある。これらのことから、唐から五代に至る時代に、刺身は宮廷の宴席の定番料理というだけでなく、一般庶民が日常的に食べる料理になっていったことが分かる。刺身はちょうどこの時代に日本に伝わった。前回の拙作で指摘したが、中日両国間の交流は、現在残っている文献によると漢代までさかのぼることができ、東漢末年と三国鼎立の入れ替わる時期には、中国と日本の間の往来はすでに頻繁になっていた。唐代のころの日本は、中国の先進的な文化を学ぶために7世紀以降次々と中国へ「西海使」(すなわち遣隋使と遣唐使)を送っており、これが当時の基本国策ともなっていた。当時の日本が唐の繁栄にあこがれるさまは、今日欧米大国を追う姿と同じで、彼らは唐で流行する事物なら何でも取り入れて試そうとした。そして、それらが繁栄する唐の文化を代表するものであり、上流社会に溶け込んだことの表れだととらえた。
唐の余韻を引き継いで、宋、遼、金、元時代にも魚膾を食用する習慣は依然として一般的に広く流行し、文献に名前があり存在を証明できる魚膾は「魚鰾二色膾」、「鮮蝦蹄子膾」、「鯽魚膾」、「沙魚膾」、「水母膾」、「三珍膾」など38種類にも上る。このほか、蘇軾と陸游はどちらも刺身が好きで、2人の作った魚膾に関する詩はそれぞれ13首、37首にも上る。金代の女真族にも刺身を食用する習慣があった。南宋の歴史家徐夢莘の『三朝北盟会編』の記載によると、女真族は中原を支配する前にすでに刺身を副食にしており、「魚やキバノロの生食を食べ、焼いた肉も時々食べた」。金代末年の名医張従正は、医書「儒門事親」に女真族が中原を支配した後の食習慣について書いているが、そこには「北方の貴族のようにチーズ、バター、羊の生肉、魚膾、鹿の干肉、豚の燻製、海産物などを好む」とある。これは、女真族が中原を支配した後も依然として刺身を食用していたことの揺るぎない証拠である。
元代の宮廷にも刺身料理があった。蒙古の太医忽思慧による『飲膳正要・聚珍異饌』には、彼が元王朝の歴代皇帝のために作成したレシピがおさめられているが、そのうちの料理の一つが魚膾である。その作り方は、生の鯉の薄切りに、からしを入れて強火で炒めたしょうが、ねぎ、大根それぞれの千切りと香菜を加え、臙脂で着色し、塩、酢などをつけて食べるというものである。
明代の劉伯温は『多能鄙事』第2巻「魚膾」の条で魚膾の作り方を詳しく説明している。それによると、「魚の大きさは問わないが、新鮮なものがよい。頭と尾、はらわたを取り去り、薄く切って白い紙の上に暫く並べてから、糸のように細く切る。細かく刻んだ大根と生姜の千切りを魚と和えて皿にとり、葉野菜、からし、つけ酢と合わせる」。
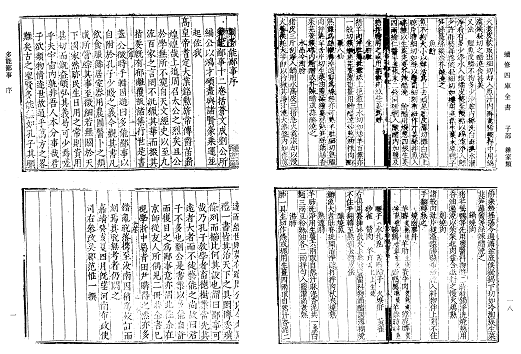
『続修四庫全書』本『多能鄙事』と第二巻
李時珍は『本草綱目』に、簡単にだが魚膾の製法を記している。それは「切って作れば出来上がりで、このため膾という。新鮮な魚を薄切りにして血を洗い、にんにく、しょうが、酢、五味をつけて食べる」というものである。しかしその当時は魚膾の普及度はすでに大きく低下しており、『三国演義』、『水滸伝』など多くの白話小説に刺身の食用の描写があるものの、すべて前王朝の話であり、前王朝の風俗が原書に残存、反映されている可能性が高い。
清代に下るまで、文献には刺身に関する記載は残っているが、そのころにはすでにほんのわずかになっている。高士奇はその詩『西苑侍直』の中で、「恩により魚の薄切りをふるまう」と書いている。この詩が作られたのは康煕18年(1679年)から19年(1680年)のことであり、清代の宮廷ではまだ刺身を宮廷料理として供していたことがうかがえる。清の李調元は『南越筆記』の中で、「粤の習慣では生の魚を好み、...草魚が最上である。中でもさらに白草魚が最上である。水から上げたばかりの新鮮なものの鱗とひれをとって、血を洗い、薄く切って生のままとする。赤い身に白い肌理があり、吹けば立ち上がるほど軽く、蝉の羽のように薄く、形がそろっている。酒に浸し薬味と合わせて、口に入れると氷が溶けるようで、非常にうまい。ニシンとイワナが特においしい」と刺身流行の余波が江南、嶺南地区に引き続き残っていることを示している。
上に述べたような中国古代における刺身の描写から考えると、魚膾は中国の食文化を構成する一部分として、長い歴史的発展と文化的蓄積を経、唐・宋の両時代に最盛期を迎えて、唐代に日本に伝わった。元・明代以降、刺身は中国の食文化において、中国料理の主流体系から次第に消えていき、その存在は徐々に薄くなって周辺へと追いやられ、清末にはすっかり廃れた。その代わりに唐代に日本へと伝わって以降、刺身は盛んな活力を呈した。このことは、日本が属する海洋文化と大きな関係がある。そして中国と日本の間にある細長い海峡、異なる環境や生産方法によって、両国における刺身の発展は異なる境遇を迎えた。
刺身が中国から日本に伝わったとはいえ、両国で刺身のための材料は異なる。古代中国の魚膾は多くが川魚か、淡水海域で捕獲された回遊海魚を用いたものだが、日本の刺身はほとんどの場合海の魚を材料とする。古代中国では鯉は魚膾に最もよく利用される原料であった。漢代の辛延年による詩『羽林郎』には、西漢の丞相霍光の下僕が居酒屋で働く異民族の女をからかい、女がこれをきっぱりと拒んだ話が描かれている。詩の中で女はこう歌う。「私に酒をと言うなら、玉で作った壷を提げましょう。私に料理をと言うなら、金の皿に鯉の薄切りを」。

スズキ
古代中国で最も有名な魚膾の材料はスズキであった。西晋末年、呉郡(その中心は今の江蘇省蘇州市)の張翰は、洛陽の司馬冏斉王府で任職した。晋の惠帝の太安元年(302年)秋、ちょうど司馬冏の権勢が高まり朝廷の政治を握ったころ、張翰は空一面に舞う落ち葉を目にし、ふるさとではスズキが豊漁を迎える季節だと思い出した。スズキの刺身とジュンサイの汁物をご飯にかけたものがどんなにおいしいかと考えると、思わずこう歌った。「秋風に落ち葉が舞い、呉の川にはスズキが肥える。三千里離れた家に帰らず、残念で仕方なく天を仰いで悲しむ。」しかしスズキは、古代中国で魚膾の材料として最上級というわけではなかった。孫権が、どの魚を刺身にするのがいちばんいいか、術士の介象と話し合ったことがあるという伝説がある。介象はボラを挙げた。孫権はため息をつき、東海ではボラがとれるが望んでも手が届かないと嘆いた。介象は正殿の中央に小さな穴を掘らせてそこに清水を満たし、すぐさまその水の中からボラを釣り上げて見せた。ボラは俗に「子魚」といい、その身の肉と卵はやわらかくおいしいことで知られている。かつて南宋の宮廷御膳では珍味とされ、古代には捕獲量は少なく、そのために貴重であった。唐の楊曄は『膳夫経』のなかで刺身に適している魚を3段階に区別している。最上級はフナのみ、その次がギギ、クロダイ、タイ、スズキ、三つ目がエツ、「味魚」、泥土鯉、キグチ、アジなどである。このことは、古代中国で刺身用に求められた材料の多様性をあらわすもので、この多様性はまた、中国の食文化に色濃い地域的色彩も含んでいる。
日本料理における刺身は、多くが生魚を切った小さなかたまりで、ふぐ刺しなど数種類のみが、皿の模様が透けるほど紙のように薄く切られる。中国古代の魚膾は、薄く切れば切るほどよいとされ、時には特別に薄く加工する必要もあり、これは「膾縷」と呼ばれた。三国時代魏の曹植は賦『七啓』の中で、出来上がった刺身はまるで蝉の羽や縠(しわのある絹の一種)のように薄く、雪のようにやわらかくほぐれ、風になびくほど軽いと形容し、こう書いている。「蝉の羽のように薄く切られ、重なる様子は縠のようだ。雪のように消え、風に飛ぶほど軽く、これ以上切ることはできない」。そのほかに刺身を下ろすことについてはもう一つの専門用語として「斫膾」がある。「斫膾」の際にはまな板の上に白い紙を敷き、包丁を入れたときに出る水分を吸収させる。表面に湿り気のない刺身は皿の上にばらして盛り付けることができ、見た目も食感も良くなる。技術の高い調理人なら、刺身をごくごく薄く切ることができるだけでなく、紙にほとんど水気を滲みさせない。杜甫はこれを詩にし、「まな板に置いたのになぜ紙が湿らないのか」と感嘆している。

刺身
刺身は日本に伝わった後に「刺身」という専門の呼称がついただけでなく、徐々に日本料理の中でも最も代表的な、最も特色ある料理となっていった。細菌の繁殖を防ぐために、刺身を食用する際には必ず素材の十分な鮮度を保証しなければならない。20世紀の初頭、冷蔵庫はまだ日本に普及しておらず、日本人のうち刺身を食用するのは主に沿海の地域の人々に限られていた。その後、鮮度保持や輸送の条件が改善を続けるにつれて、刺身を食べる日本人も徐々に増えた。大まかに言うと、江戸時代以前の刺身は、主にタイ、ヒラメ、カレイ、スズキを材料としており、これらの魚肉はほとんどが白身だった。明治以降、赤身のマグロ、カツオなどが刺身の高級材料となり、現在の日本人は、貝類、イセエビなども薄く切って「刺身」と呼ぶ。その中でもふぐは刺身の逸品で、多くの人に好まれている。しかし一つだけ変わらない原則があり、それは選ぶ魚が新鮮でなければならないという点である。日本人の多くは、刺身にして本当においしいのは、しめてから数時間おいた後の魚だと考えている。その理由は、しめた魚が硬くなった後にアミノ酸の量が最高になるためである。刺身を食べる際にわさびと醤油をタレとするのは、中国の「金齏玉膾」と同じで、これは刺身に不可欠のタレである。わさびは鼻をつく独特の辛味がある調味料で、その音に漢字を当てると「瓦沙比」である。殺菌と同時に食欲増進の効果があり、また魚の生臭みを取り除いて、そのおいしさを引き立て、日本人はこれを非常に好む。刺身の盛り付けには千切りの大根、海草、しその花などが添えられ、食文化の中で自然に親しむ日本人の気持ちを表している。
刺身は栄養価が高く、タンパク質を豊富に含み、ビタミンと微量のミネラルを含み、さらに脂肪量が少なく、栄養豊富で吸収されやすい優れた食品である。そのため日本のみならず世界各国の観光客からも好まれている。現在、刺身と寿司はともに日本の文化的特色の重要な符号とシンボルであり、日本が海外に向けて観光事業を推進する際の効果的な名刺ともなっている。およそ日本を訪れる外国人客は、いつも刺身を供する料理店に入り、国際的ブランド力のあるこの民族的食文化を楽しむ。しかし私たちが、刺身は中国と日本の文化交流の一つの重要な縮図だと理解するなら、おいしく栄養ある刺身を味わうと同時に、もう一つ別の異国情緒が感じられるのではないだろうか。

朱新林(ZHU Xinlin):
中國山東省聊城市生まれ。
2003.9--2006.6 山東大学文史哲研究院 修士課程修了
2007.9--現在 浙江大学古籍研究所 博士課程在籍中
(2009.9--2010.9) 早稻田大学大学院文学研究科 特別研究員