第3節 地域分布と現状
第1項 地域分布
54の国家ハイテク産業開発区の地域分布は下表の通りである(2008年12月現在)。
| No | 所在地域 | 数 | No | 所在地域 | 数 |
| 1 | 北京 | 1 | 15 | 江西 | 1 |
| 2 | 天津 | 1 | 16 | 湖北 | 2 |
| 3 | 上海 | 1 | 17 | 湖南 | 2 |
| 4 | 重慶 | 1 | 18 | 広東 | 6 |
| 5 | 吉林 | 2 | 19 | 広西 | 2 |
| 6 | 遼寧 | 3 | 20 | 海南 | 1 |
| 7 | 河北 | 2 | 21 | 四川 | 2 |
| 8 | 山西 | 1 | 22 | 貴州 | 1 |
| 9 | 山東 | 5 | 23 | 雲南 | 1 |
| 10 | 河南 | 2 | 24 | 陝西 | 3 |
| 11 | 江蘇 | 4 | 25 | 甘粛 | 1 |
| 12 | 浙江 | 2 | 26 | 新疆 | 1 |
| 13 | 安徽 | 1 | 27 | 黒龍江 | 2 |
| 14 | 福建 | 2 | 28 | 内モンゴル | 1 |
| 合 計 | 54 | ||||
最も多く設けられているのは広東省で、その後に山東省、江蘇省が続く。また、上表を図で示すと次頁の通りになる。
図3.2 国家ハイテク産業開発区の地域分布
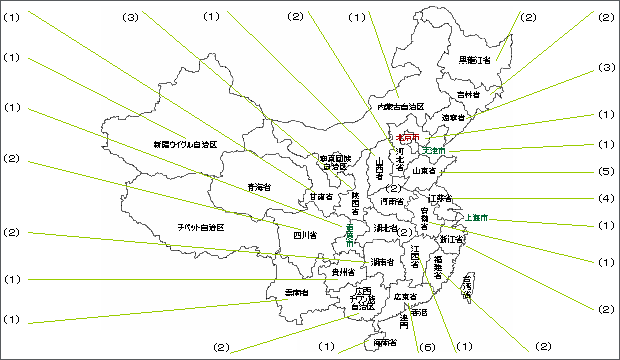
出典:現地情報をもとに技術経営創研が作成(背景図:Copyright © 2003-2004 中国まるごと百科事典 )
| No | 名称 | 企業数 | 総生産高 | 総収入 | 製品販売収入 | 増加値 |
| 1 | 北京 | 2,375 | 217,280,801 | 242,739,718 | 221,331,665 | 3,869,608 |
| 2 | 上海 | 283 | 165,807,065 | 179,155,340 | 170,576,234 | 37,637,797 |
| 3 | 深セン | 159 | 139,566,006 | 138,057,739 | 134,543,061 | 28,047,536 |
| 4 | 南京 | 103 | 127,516,561 | 134,746,926 | 127,319,850 | 13,143,508 |
| 5 | 无錫 | 173 | 91,495,315 | 91,217,628 | 90,664,742 | 19,429,735 |
| 6 | 蘇州 | 204 | 90,187,108 | 106,741,814 | 87,621,176 | 22,266,350 |
| 7 | 厦門 | 86 | 70,410,810 | 69,639,802 | 68,838,941 | 16,782,239 |
| 8 | 杭州 | 190 | 68,638,065 | 72,277,743 | 68,525,855 | 8,090,328 |
| 9 | 青島 | 52 | 55,557,575 | 58,264,423 | 55,387,474 | 15,626,086 |
| 10 | 惠州 | 63 | 53,411,706 | 53,661,667 | 52,704,183 | 9,451,292 |
| 11 | 珠海 | 119 | 52,727,771 | 51,759,436 | 51,360,146 | 8,904,909 |
| 12 | 広州 | 173 | 42,868,721 | 43,728,152 | 42,349,475 | 8,153,576 |
| 13 | 吉林 | 132 | 42,733,446 | 47,150,366 | 46,455,737 | 13,609,772 |
| 14 | 天津 | 532 | 40,311,384 | 40,748,231 | 39,521,652 | 6,148,211 |
第2項 事例
ここでは、中国初の「データセンター基地の建設」を宣言する西安国家ハイテク産業開発区及び新エネルギーの開発や活用に取り組むウルムチ国家ハイテク産業開発区を例として述べる。
西安国家ハイテク産業開発区は1991年に中国国務院の承認により設立され、特に電子情報産業、精密機器製造産業、バイオ医薬産業、新材料産業といった分野に力を入れている。現在、同開発区は54の国家ハイテク産業開発区の中で指定された6カ所の重点開発区の一つとなり、総合評価は北京、上海、深センに続く4位となっている。また、陝西省の富裕層の8割が同開発ゾーンに住んでいると言われている。
西安国家ハイテク産業開発区の一部を構成する西安ソフトウェアパークは1999年に中国科学技術部より「国家重点計画ソフトウェア産業基地」に認定され、2001年に国家計画委員会、情報産業部より「国家ソフトウェア産業基地」の認定を受け、2003年に国家発展と改革委員会、情報産業部、商務部より4つの「国家ソフトウェア輸出基地」の内の一つに認定された。また、西安国家ハイテク産業開発ゾーンは2005年に国家知的財産局より「国家知財実証パーク」の一つに認定されている。さらに、西安市は2006年に国家商務部より「国家サービス・アウトソーシング基地都市」の認定を受けた。
2007年6月5日、北京にて開催された「2007中国データセンター戦略フォーラム」において、関連の研究報告が発表され、西安市はデータセンター構築における地域特性、環境、技術力、安定性、交通、人材などの観点から総合的に評価され、北京、上海、広州、成都を抜いて1位に輝いた。これにより、西安国家ハイテク産業開発区は中国初の「データセンター基地」を建設することを宣言し、国内外のデータセンター関連事業者の誘致を始めている。
2007年現在、西安国家ハイテク産業開発区にはアメリカ、日本、ドイツ、シンガポール、香港、台湾など29の国と地域の729社が進出しており、世界トップ500社や有名なグローバル企業に名を連ねる40数社も含まれている。アメリカのインテルやIBMはもちろん、東芝、富士通、ブラザー工業、NEC、ダイキン工業なども参加している。
ウルムチ国家ハイテク産業開発区は、1992年に中国国務院の承認により設立されたが、その後、ダイヤモンド中央商務エリア、タイマツイノベーションエリア、工業パークエリア、ハイテク工業パークエリアなどを順次形成し、新エネルギー、新材料、石油化学工業、希少資源の付加価値創造など6つの産業を形成させるように展開してきた。同開発区は現在も、光、熱、風から得るエネルギーが他のどの地域よりも豊富である地域性を生かした取り組みが続けられている。
もともとウルムチには多様なエネルギー資源が存在している。ウルムチは「煤田上的城市(石炭上の都市)」や、「油海上的煤船(石油の海の上にある石炭の船)」などと言われている。ウルムチハイテク産業開発ゾーンは、このような環境下に50平方kmもの新たな工業パークを建設し、石炭から電気、ガス、石油へと変化させるプロジェクトを発足した。また、地域大手企業とともに風力エネルギー工業パークを建設し、アメリカのBPグループとともに太陽光発電事業を推進し、天然ガスの開発や付加価値創造も含む新エネルギーの開発に注力し続けている。その結果、風力発電は2006年現在でアジア最大の規模となった。
ウルムチハイテク産業開発区は前述のような位置づけと同時に、アジア大陸の中心にあり、中国西部の対外開放の重要な窓口となっている。2005年、ウルムチハイテク産業開発ゾーンがある会議で「中央アジア市場を発展させる戦略連盟」の発足を呼びかけたところ、参加者から大きな支持を得た。ウルムチハイテク産業開発区は、国内だけでなく、中央アジアを中心とした国外向けの輸出や国際的な連携も積極的に進めている。これはまさに「産業開発」の視点を持った行動であると言える。
第3項 地域的な特徴
全国各地に設けられている54の国家ハイテク産業開発区の中には、実質的に「中国で唯一」や「中国で最も」といった冠を付けてもよい特徴を持った国家ハイテク産業開発区が多数存在する。
例えば、唯一現代農業に重点を置く「楊凌国家農業ハイテク産業モデル区」、唯一パーク名に「稀土(金属)」を含む「包頭稀土国家ハイテク産業開発区」、唯一の国家光産業基地として認定された「武漢東湖新技術産業開発区」、唯一県レベルに設置され環境保護に重点を置く「宜興国家ハイテク産業開発区」、唯一の「虚擬(バーチャル)大学サイエンスパーク」が設けられている「深セン国家ハイテク産業開発区」などが挙げられる。
また、中国におけるソフトウェアパークのモデルと評される「大連ソフトウェアパーク」が置かれている「大連国家ハイテク産業開発区」、中国初の「科技城」(科学技術新都市)が建てられている「蘇州国家ハイテク産業開発区」、最も積極的に太陽光発電や新エネルギーに取り組む「保定国家ハイテク産業開発区」、中国最大の航空宇宙救助設備の研究、設計、実験、製造基地を持つ「襄樊国家ハイテク産業開発区」、最も多くの多国籍バイオ医薬開発機関を誘致した「上海張江国家ハイテク産業開発区」といった特徴を持つ国家ハイテク産業開発区も見られる。
一方、複数の分野に取り組む国家ハイテク産業開発区が、ある分野において特定の強みを持ちつつも、その他の分野を生かすことなく同化されてしまったケースもある。各パークとしての「競争的な優位性」をいかに保つべきかは、今後の各地域のパークの発展を見据えた際の大きな課題でもある。
2005年6月、温家宝首相が「北京中関村、上海張江、深セン、西安、武漢、成都の国家ハイテク産業開発区を世界一流のサイエンスパークとすることを目指す」と明言した。これを受け、2006年6月14日、中国科学技術部がこれら6地域の国家ハイテク産業開発区の要人を西安に招集し、「世界一流のサイエンスパークを建設するイノベーション宣言」に調印した。2006年10月23日、中国科学技術部が再度それら6地域の産業開発区の要人を深センに招集し、「世界一流のサイエンスパークを建設するアクション方案」に調印した。北京中関村をはじめとするこれら6地域の国家ハイテク産業開発区は総合的な実力が強いと言う特徴が現れている。
2006年12月、中国初かつ最大の中関村サイエンスパークが、中国標準化管理委員会などの中央官庁により、初の「国家高新技術産業標準化示範区(国家ハイテク産業標準化モデルパーク)」(以下、「中関村モデルパーク」と略す)に指定された。中関村モデルパークの目指すところは、企業の技術規格作成を促し、戦略的な競争優位を強化させることである。その具体的な目標は、下記の通りである[1]。
- ①中関村モデルパークに立地する企業は、国際機関、国家、業界及び企業連盟により制定されるすべての規格策定プロセスの20%以上に参加する。
- ②独自の著作権を持つ国際規格、国家規格、業界規格、地方規格など諸規格の数と質を高め、中国における最高レベルを目指す。
- ③業界で指導的地位にある企業が国際規格の制定に参加する割合を5%以上とし、併せてR&Dを展開していく。
- ④中関村モデルパークの企業が独自開発した技術規格をベースとする産業連盟と技術連盟を結成し、連盟メンバー企業の85%以上が当該規格を採用する。
- ⑤中関村モデルパークにおいて、国内で一流の規格サービス・プラットフォームを構築し、同パークの規格関連サービスの能力と質を高める。
- ⑥北京市規格専門家のデータベースを作り、ハイテク産業分野の標準化におけるハイレベルの人材を育成する。
- ⑦中関村モデルパークの重点企業が全国専門標準化技術委員会(TC)や技術委員会部会(SC)のワークショップに参加する割合は、5%を確保する。リーディング企業が国際専門規格化委員会や部会のワークショップに参加する割合は、1%を確保する。
- ⑧中関村モデルパークの建設は、北京中関村サイエンスパークが提唱している「知的所有権、標準及びブランド」と言う戦略に沿って展開されるものである。
[1] 戴玉才「中関村科技園、初のハイテクモデルパークに」毎日コミュニケーション(2006年12月18日)。