第3節 国家ソフトウェアパーク
第1項 概要
中国の産業政策の基本は1953~2000年にかけて9回実施された5カ年計画であり、これらと並行して、国内外の状況変化に対応したさまざまな個別政策が策定され、実施された。中国国家ソフトウェアパーク制度は、中国「タイマツ計画」の下に1990年代よりソフトウェア産業育成のために策定されたものである。
1980年代に入って中国におけるコンピュータ生産は飛躍的に増大したが、コンピュータ利用と言う点では問題を抱えていた[1]。利用技術の普及の遅れから、多数のコンピュータが放置され、平均利用率は5~20%と言われていた。こうした状況を反映し、コンピュータ産業は、下記したように「4重4軽」と呼ばれることもあった。
①本体重視・周辺機器軽視
②ハード重視・ソフト軽視
③製造重視・サービス軽視
④生産重視・応用軽視
このような状況にあって、以下に掲げる施策が実行された。
まず、1980年、中国科学院の研究員がシリコンバレーを視察し、「技術拡散モデル」を中国へ導入し、発展させることを構想した。そのために、北京中関村に内外のコンピュータ、通信、ソフトウェア企業を集めた中国版シリコンバレーの建設が始まり、1984年には国策会社として「中国軟件開発公司」が設立された。
その後、下表に示すように、1988年に中国「タイマツ計画」がスタートした。この政策の下に、1990年代以降、政府は、ソフトウェア産業育成のために主要都市に国家ハイテク産業開発区を建設し、外国企業の誘致、内外のソフトウェア企業の集中による効率的なソフトウェア生産の実現に努めた。1997年には戦略的基礎研究計画として「中国国家重点基礎研究発展計画」、略称「973計画」がスタートした。その中でソフトウェアを含む「情報技術」が研究対象となった。
| 時期 | 政策 |
| 1988年8月 | 中国「タイマツ計画」の策定・公表 |
| 1990年代初め | 中国情報産業部がソフトウェアパーク設立方針 |
| 1992年 | 中国3大ソフトウェア産業拠点(北京、上海浦東、珠海)設置決定 |
| 2000年6月 | 「ソフトウェア産業及びIC産業発展の奨励に関する若干の規定」 |
| 2002年11月 | 「ソフトウェア産業振興アクションプラン(2002~2005年)」 |
2001年には、北京、上海浦東、珠海、大連、成都、西安などの11カ所が国家級のソフトウェアパークとして認定され、付属資料に取りまとめたように、2007年末時点の国家ソフトウェアパークの合計数は29カ所にまで増えた。大都市を中心に地方政府が積極的に建設し、企業誘致を行っているが、各地のソフトウェアパークは必ずしも独立して設けられているとは限らず、実際は国家ハイテク産業開発区内の一角に併設されていることが多い。
図8.2 国家ソフトウェアパークの地域分布
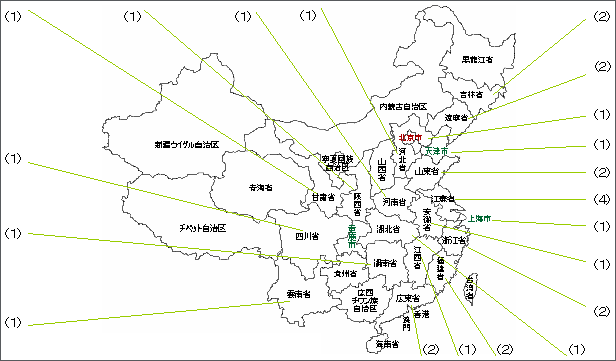
出典:現地情報をもとに技術経営創研が作成(背景図:Copyright 2003-2004 中国まるごと百科事典)
[1] 中国の国産コンピュータ開発の歴史は1956年の中国科学院計算機研究所設立にさかのぼる。当初は旧ソ連の技術導入によって国産コンピュータ開発が進められたが、その後の中ソ対立期間におけるアメリカ製のコピー時代を経て現在に至っている。JIPODEC「わが国IT開発拠点の中国移転に関する調査」(平成14年)。
第2項 事例
瀋陽の東大ソフトウェアパーク、山東の斉魯ソフトウェアパーク、湖南の創智ソフトウェアパーク、四川の拓普ソフトウェアパークは4大ソフトウェアパークとして有名であるが、むしろ、中国を代表する国家ソフトウェアパークとしては、大連国家ソフトウェアパークが挙げられる。2008年12月3日には、東京・新宿に同パークの海外初となる大連(日本)ソフトウェアパークが開園した。
同ソフトウェアパークが設立される前の1998年は、まだ農地が広がっていた地域が、2004年には国家ソフトウェアパークへと変身した。GEキャピタル、シーメンス、デル、IBM、マイクロソフト、エリクソン、ノキアなどの世界的企業や、ソニー、パナソニック、東芝、CSK、オムロンなどの日系企業のソフトウェア開発部門が進出している。入居企業は約130社で、その内、日系企業は40社程であった。
また、2007年9月5日には、シンガポール貿易工業部傘下のシンガポール騰飛集団と大連ソフトウェアパークが共同で建設した「騰飛ソフトウェアパーク」が竣工し、インドのシリコンバレーであるバンガロールを目指している。
大連国家ソフトウェアパーク股フェン有限公司[2]CEOの高によると、騰飛ソフトウェアパークは面積が35ha、投資総額は2億ドルを予定している。今後、5~8年以内に8棟のビルから成る大規模ITパークを形成し、60万㎡におよぶ高規格のビジネス空間を提供しようとしている。同集団は、大連、上海、北京など10都市で積極的なビジネス展開を見せている。
また、大連国家ソフトウェアパークには、日本語とコンピュータに精通した人材を養成する「大連外国語学院東軟信息(情報)技術学院」が創設された。この種の専門大学としては中国初である。同学院は東軟集団と大連軟件(ソフトウェア)団地、大連外国語学院が共同で創設したものである。大連外国語学院は中国国内で最大規模の日本語人材養成大学であり、一方、大連ソフトウェア団地は日本の情報技術(IT)産業界で知名度が高く、上記したように、ソニーやパナソニック、IBM、デルコンピュータなど世界の有力メーカーが数多く進出している。このような「強強間の協力」は「中日ソフトウェア産業協力戦略ゲート」プロジェクトを進める大連市にとって、持続可能な発展に向けた人的資源からの支援となる。
こうして、既に創設されていた東軟信息技術学院、大連鉄道学院軟件学院、大連理工大学軟件学院に、今回新設された「大連外国語学院東軟信息(情報)技術学院」が加わり、これらを中心に据えたソフトウェアの教育システムが完備されることになった。ソフトウェア関係の人材養成は2005年までに年間1万人を超えると見込まれていたが、実際はそれ以上の結果となった。
[2] 大連軟件園股フェン有限公司は、中国で最も早くソフトウェア産業パークを開発、管理及び運営した企業の一つで、累計投資額は55億元を超える。2007年7月現在、同パークへの入居企業は381社で、内30社は「世界の500社」に選ばれた企業である。「国家ソフトウェア産業基地」の一つである。
第3項 経済・社会効果
中国科学技術部は、2005年9月、「国家ソフトウェアパークは、既に中国ソフトウェア産業の自主技術開発の中心、ソフトウェア産業の国際化の最先端、また、ソフトウェア企業成長のゆりかごとなっているとした。基地の指定を開始してからの10年間で、認定を受けたソフトウェア産業基地は29カ所となり、基地内のソフトウェア企業は1万2000社、従業員は37万人を超えた。総売上高は1638億元に達し、ソフトウェア産業の売上全体の60%以上を占める」と評価した[3]。
一方、日本のソフトウェア企業の中国進出は、1980年代半ば頃に始まった。「合弁」、「100%出資」、「資本参加」など、進出形態はさまざまながら、北京、上海などの海岸沿いの大都市を中心に進出している。しかし、近年では、中部の武漢、西部の西安などへの進出も徐々に増えてきている。また、進出の始まった当初は合弁が多数を占めたが、近年は100%出資子会社が増加している。
2006年6月22日、中国科学技術部副部長・馬頌徳は「中国ソフトウェア交易会」などが開催した「中国ソフトウェアの自主的なイノベーションフォーラム」において、「過去4年に中国のソフトウェア及び情報サービス産業は急速に発展した。年平均成長率は30%を超え、成長が最も速いハイテク産業となった」と述べた。中国政府の統計によると、中国ソフトウェア産業の年間生産高は、2000年の593億元から、2005年は3900億元へ増加し、世界市場におけるシェアも4%へ拡大した。
[3] 人民日報日本語版「ソフトウェア産業基地、オリジナル開発の主力に」(2005年9月23日)。