2.1 ナノテクノロジー・材料分野の概要
(1) 関連政策
1)各政策の分野別取り組みについて
ナノテクノロジー・材料は、広範な科学技術分野の飛躍的な発展の基盤を支える重要分野であると世界的に位置付けられている。中国は「第10次5ヵ年」期(2001~2005年)において、ナノテクノロジー研究に延べ15億元(約225億円)を投入し、基礎研究と応用研究で飛躍的な進展を達成した。一方で、創造的な成果が少ないことに加えて、持続的発展の基礎能力が十分でなく技術移転の能力が不足している等の課題が浮き彫りになっている。
① 中長期科学技術発展規画(2006~2020年)
中国政府はこうした状況を踏まえ、2020年までを視野に入れた科学技術政策に関する長期的方針を示した「国家中長期科学技術発展規画綱要(2006~2020年)」(「国家中長期科学和技術発展規劃綱要(2006-2020年)」)を公布した。
同規画綱要では、次世代のハイテクおよび新興産業発展の重要な基盤を構成し、ハイテクイノベーション能力を総合的に体現する先端技術8分野の1つとして「新材料技術」分野を含めている。
具体的には、ナノテクノロジーの研究を基礎として、ナノ材料とナノ素子を研究するとともに、超伝導材料やインテリジェント材料、エネルギー材料等のほか、きわめて優れた特殊機能材料や新世代の光通信材料を開発するという目標を掲げた。
また、①インテリジェント材料・構造の技術②高温超伝導技術③高効率エネルギー材料技術――を重点基礎研究テーマとして設定した。このうち①については、インテリジェント材料の調整・加工技術、インテリジェント構造の設計・調整技術、中核設備の監視測定技術等を重点的に研究するとしている。
高温超伝導技術については、材料・調整技術や超伝導ケーブル、超伝導素子を重点的に研究するとしている。高効率のエネルギー材料技術に関しては、とくに太陽電池材料と中核技術、燃料電池の中核材料技術、大容量の水素貯蔵材料などが重点研究テーマにあげらた。
中長期科学技術発展規画では、基礎研究分野の重大科学研究のテーマとしてもナノテクノロジー研究が盛り込まれている。具体的な重点研究課題は以下の通りである。
- ナノ材料の制御可能な調整・自動組立・機能化
- ナノ材料のメカニズム、特性および制御メカニズム
- ナノ加工と集積原理
- コンセプトおよび原理段階のナノデバイス、ナノエレクトロニクス、ナノバイオ・医学
- 分子集合体と生物分子の光学的、電子的、電磁的特性と情報の伝達
- 単一分子の挙動と制御
- 分子マシン、ナノスケール計測
② 「第11次5ヵ年」規画
科学技術部が2006年10月27日に公布した「国家『第11次5ヵ年』科学技術発展規画」(「国家"十一五"科学技術発展規劃」)では、重大な国家戦略上のニーズを持つ基礎研究の1つとして「材料領域」を指定している。
具体的には、基礎材料の改質と最適化、新材料の物理・化学的特性に加えて、ミクロ化や人工メカニズム化、集積化、インテリジェント化などに基づき、新材料を探究、設計、製造、加工する新しい原理と方法、材料の使用挙動と環境との相互作用を重点的に研究するとの方針を示した。
また、重大科学研究計画の1つとしてナノ科学技術研究を指定し、中国独自のナノ材料やナノデバイス、ナノバイオ・医学の研究システムを構築し、世界をリードする複数のグループを創設するとの目標を掲げた。
さらに、ナノ材料、ナノデバイスの設計・製造技術を開発し、ナノレベルの相補性金属酸化膜半導体(CMOS)デバイス、ナノ薬物担体、ナノエネルギー変換材料、環境浄化材料および情報記録材料を研究するとした。
このほか国家発展改革委員会が2007年4月28日に公布した「ハイテク産業『第11次5ヵ年』規画」(「高技術産業発展"十一五"規劃」)では、新材料産業を産業発展の重点の1つとして位置付け、特殊機能材料や高性能材料、ナノ材料、複合材料、環境保護・省エネ材料等の産業を重点的に発展させ、新材料の革新システムを構築・改善する考えが明らかにされた。
そうした一環として、電子情報材料の水準向上や航空宇宙材料の研究加速、再生可能エネルギーや原子力といったエネルギー向け材料の生産を拡大するとの方向性が打ち出された。
2)重点分野推進政策
科学技術部、国家計画委員会(当時)、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委員会は2001年、共同で「国家ナノテクノロジー発展要網(2001~2010年)」を公布した。同要綱の主な内容は下記の通りである。
a. 目標:
- ナノテクノロジー発展の基盤を構築し、ナノテクノロジーの開発および応用面で重大な突破を成し遂げ、総合的・持続的なイノベーション能力を持つ研究グループを育成する。
b. 主な任務:
- ナノテクノロジーに関する基礎的研究を強化する。とくにナノスケールの新しい現象、新しい効果、新しいメカニズムおよび新しい方法に関する研究と発見を重視する。また、ナノテクノロジーに関する基準の制定も重視し、ナノテクノロジー産業化の基盤を構築する。
- ナノ材料の製造と加工、ナノデバイスの構築と集積、ナノ加工、ナノスケールでの構造分析および性能測定、国家安全にかかわるナノテクノロジーなど中核技術を開発する。
- ナノ材料およびデバイスの応用を開拓し、ナノテクノロジー研究成果の移転を推進する。「第10次5ヵ年」期間中(2001~2005年)、新材料、パソコンと情報システム、エネルギーと環境、医療と衛生、生物と農業などの分野でのナノテクの応用を重点的に推進する。また、産・学・研の提携促進、ハイテク企業育成、ナノ産業化基地の建設を通じて、ナノテクノロジー成果の移転と産業化を加速させる。
- 国家ナノテクノロジー研究開発基地を建設する。まず既存国家重点実験室もしくは関連研究基地からいくつかの実験室を選定し、重点的にサポートすることにより、ナノテクノロジーの重点実験室に発展させる。また、国家ナノ科学技術センターおよびナノテクノロジー応用国家工程研究センターを設立する。さらに、中央政府は各地方政府部門および企業と共同でナノテクノロジー実験室もしくは研究開発基地の建設を奨励する。
- ハイレベルのナノテクノロジー人材を育成する。
c. 対策:
- 「国家ナノテクノロジー指導調整委員会」を設立するとともに、国家ナノテク発展計画を策定し、ナノテクノロジーの発展を指導、調整する。
- 「第10次5ヵ年」期間中、「国家ナノテクノロジー特別行動」を実施し、研究経費を優先的に保障し、管理面も重点的に強化する。
- 国家ナノ科学技術センターおよびナノテクノロジー・応用国家工程研究センターを設立する。企業によるナノテクノロジー開発を奨励する。また、ナノテクノロジー成果の移転と産業化に優遇政策を与える。さらに、ナノテクノロジー技術の産業化に対するリスク投資体制を構築する。
- ナノテクノロジー・イノベーションを促進するため、特許取得および知的財産権の保護を強化する。
- 大学にナノテクノロジー関連学科を設置し、人材を育成する。
- 海外とのナノテクノロジー技術交流を強化し、中国としての特色を保ちながら、ナノテクノロジー全般の技術レベルを先進国と同程度に引き上げるよう努力する。
2000年11月に設立された「国家ナノテクノロジー指導調整委員会」の2007年6月以降のメンバー構成を表2.1に示す。
|
氏名 |
委員会役職 |
所属および役職 |
|
万鋼 |
主任 |
科学技術部部長 |
|
程津培 |
常務副主任 |
科学技術部副部長 |
|
曹健林 |
副主任 |
科学技術部副部長 |
|
白春礼 |
首席科学者、専門家グループ長 |
中国科学院常務副院長 |
|
朱道本 |
副グループ長 |
国家自然科学基金委員会副主任 |
|
綦成元 |
副グループ長 |
国家発展改革委員会巡視員 |
|
その他 |
メンバー |
国家発展改革委員会、財政部、教育部、国防科工委員会、総装備部、国家品質監督検査検疫総局、科学技術部、中国科学院、中国工程院など |
また国家科学技術部は2001年9月、中国のナノテクノロジーを確実に発展させるため、「国家ナノテクノロジー発展要網」を踏まえ、「国家ナノテクノロジー発展指南枠組み」(「国家納米科技発展指南框架」)を公布した。同枠組みの主な内容を表2.2に示す。
|
項目 |
主な内容 |
|
ナノ材料の基礎的研究と応用研究 |
・ナノ材料の特殊性能、構造安定性に関する基礎的研究 |
|
ナノデバイスの開発と集積技術 |
・ナノデバイスに関する基礎的研究 |
|
ナノ加工と製造に関する技術 |
・ナノスケール加工技術 |
|
ナノスケール構造分析と性能に関する研究 |
・ナノスケール構造分析と性能に関する基礎的研究 |
|
ナノ技術の医学分野への応用 |
・ナノ技術の重大疾患の早期診断と治療への応用 |
|
ナノ技術の生物学、農業分野への応用 |
・ナノスケールでの生命物質の構造と機能 |
|
製造、測定および研究用装置の自主開発 |
・製造、測定および研究用装置の自主開発 |
関連省庁はナノテクノロジーに関連した計画と指南に基づき、「国家重点基礎研究発展計画」(「973計画」)や「国家ハイテク研究開発発展計画」(「863計画」)、「国家科学技術支援計画」(2005年までは「難関攻略計画」)などの国家重大科学技術発展計画の重点プロジェクトのほか、自然科学基金の重大、重点プロジェクト、中国科学院重大プロジェクト、教育部の「振興計画」の重要プロジェクト、国家発展改革委員会の「産業化モデル事業」として、多くの資金と人員をナノテクノロジー研究開発に投入してきた。
(2) 研究予算
1)材料科学分野
機関別に見た材料科学分野の研究開発に関する内部支出と研究開発テーマ件数の推移を表2.3に示す。
|
年 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
研究開発機関(全分野) |
1,971,759 |
2,093,247 |
2,767,834 |
2,834,996 |
3,534,911 |
3,653,731 |
|
(33,784) |
(35,749) |
(36,889) |
(37,292) |
(39,072) |
(42,262) |
|
|
うち |
28,063 |
49,400 |
47,258 |
54,214 |
58,609 |
75,949 |
|
(913) |
(944) |
(896) |
(955) |
(1,029) |
(1,225) |
|
|
高等教育機関(全分野) |
758,722 |
957,739 |
1,262,116 |
1,477,327 |
1,934,537 |
2,870,180 |
|
(141,992) |
(169,643) |
(200,120) |
(237,463) |
(280,327) |
(365,294) |
|
|
うち |
46,148 |
76,293 |
102,850 |
105,194 |
133,815 |
179,606 |
|
(5,166) |
(6,114) |
(7,341) |
(8,292) |
(9,562) |
(10,741) |
① 研究機関
「2007中国科技統計年鑑」によると、研究開発機関の2006年の内部支出は、研究開発テーマ4万2,262件に対して365億3,731万元(約5480億円)となった。このうち材料科学関係は、合計1,225件の研究開発テーマに対して内部支出額が7億5,949万元(約114億円)となり、全体の約2.1%を占めた。
材料科学分野の内部支出額は増加傾向にあり、2006年は2001年に比べ内部支出額は2.7倍になり、対前年比でも約30%という高い伸びを示した。また、1件あたりの平均内部支出額は着実に増加しており、2006年は62万元(約930万円)/件で2001年の2倍に達した。
同年鑑に含まれている全58分野の内部支出額を見ると、航空・宇宙関係の119億3,664万元(約1790億円)、電子・通信・自動制御の85億9,767万元(約1290億円)、エンジニアリング・基礎技術科学の30億4,720万元(約457億円)、原子力科学の19億2,476万元(約289億円)、農学の10億8,010万元(約162億円)、地球工学の10億4,383万元(約157億円)、生物学の9億5,405万元(約143億円)、物理学の9億2,736万元(約139億円)に次いで材料科学関係が9位に入っている。
② 高等教育機関
「2007中国科技統計年鑑」によると、高等教育機関の2006年の内部支出額は、研究開発テーマ36万5,294件に対して287億元(約4305億円)となった。このうち材料科学関係は、テーマ1万741件に対して17億9,606万元(約269億円)で、全体の約6.3%を占めた。
材料科学分野の内部支出額は増加傾向にあり、2006年は2001年に比べて3.9倍となり、対前年比でも約34%という高い伸びを示した。また、1件あたりの平均内部支出額も着実に増加しており、2006年は16.7万元(約250万円)/件となり2001年に比べて約2倍に達したが、研究機関と比べると4分の1程度の水準に過ぎない。
同年鑑に含まれている全58分野の内部支出額を見ると、電子・通信・自動制御の28億5,182万元(約428億円)、土木・建築の23億219万元(約348億円)、コンピュータ工学の20億9,278万元(約314億円)、機械工学の20億7,410万元(約311億円)に次いで、高等教育機関では材料科学関係が5位に入っている。
2)ナノテクノロジー分野
ナノテクノロジー分野の研究予算に関する詳細統計データはないが、2007年6月5日に行われた「国家ナノテクノロジー指導調整委員会」の会合で発表されたデータによると、「第10次5ヵ年」期間中にナノテクノロジー分野に投入された研究経費は15億元(約225億円)に達した。
「第10次5ヵ年」期間中に、「863計画」および「難関攻略計画」のナノテクノロジー分野に投入された研究費を表2.4に示す。
|
計画名 |
項目 |
金額 |
|
863計画 |
国家財政(万元) |
20,000.00 |
|
地方財政(万元) |
1,368.90 |
|
|
民間(万元) |
22,118.05 |
|
|
合計(万元) |
43,486.95 |
|
|
難関攻略計画 |
国家財政 (万元) |
13,000.00 |
|
地方財政(万元) |
49,017.00 |
|
|
民間(万元) |
||
|
合計(万元) |
62,017.00 |
(3) 研究人材
1)材料科学分野
機関別に見た材料科学分野の投入人的資源(研究者・技術者)と研究テーマ件数の推移を表2.5に示す。
|
年 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
研究開発機関 |
127,690 |
118,458 |
129,001 |
124,831 |
133,485 |
157,169 |
|
(33,784) |
(35,749) |
(36,889) |
(37,292) |
(39,072) |
(42,262) |
|
|
うち |
3,485 |
3,809 |
3,274 |
3,321 |
2,942 |
4,010 |
|
(913) |
(944) |
(896) |
(955) |
(1,029) |
(1,225) |
|
|
高等教育機関 |
136,380 |
153,190 |
162,384 |
202,633 |
219,487 |
261,159 |
|
(141,992) |
(169,643) |
(200,120) |
(237,463) |
(280,327) |
(365,294) |
|
|
うち |
5,473 |
6,624 |
6,997 |
8,282 |
8,893 |
9,600 |
|
(5,166) |
(6,114) |
(7,341) |
(8,292) |
(9,562) |
(10,741) |
① 研究機関
「2007中国科技統計年鑑」によると、研究機関における研究者と技術者の人的資源投入量は、材料科学分野では2006年に1,225件の研究テーマに対して4,010人・年であった。2001年に比べ、総数は増加したものの、研究テーマ数も増えたため、1件あたりの人員投入量はやや減少傾向にある。
なお、同年鑑に含まれている全58分野の人的資源投入を見ると、航空・宇宙関係の3万6,734人・年がトップで、電子・通信・自動制御の2万4,460人・年、農学の1万1,678人・年、エンジニアリング・基礎技術科学の1万707人・年、生物学の7,476人・年、地球工学の6,670人・年、原子力科学の6,476人・年に次いで材料科学関係が8位に入っている。
② 高等教育機関
高等教育機関では、過去の6年の実績を見ると、材料科学分野への人的資源の投入が着実に増加している。しかし、研究テーマ数も増加しているため、1件あたりの人員投入は研究機関と同じくやや減少傾向にある。
なお、同年鑑に含まれる全58分野の人的資源投入を見ると、臨床医学の3万593人・年、電子・通信・自動制御の1万4,111人・年、管理学の1万3,936人・年、機械工学の1万1,683人・年、経済学の1万954人・年、コンピュータ工学の1万628人・年、地球工学の9,626人・年に次いで材料科学関係が8位に入っている。
2)ナノテクノロジー分野
国家ナノ科学技術センターの白春礼主任によると、不完全な統計ではあるが、2007年現在、中国では合計50以上の大学と中国科学院に所属する20以上の研究所でナノテクノロジーに関する研究が行われている。研究者数は少なくとも3,000名を超えている。
「第10次5ヵ年」期間中(2001~2005年)の「863計画」および「難関攻略計画」におけるナノテクノロジー分野での研究者の構成を表2.6に示す。
|
計画名 |
分類 |
人数 |
|
863計画 |
高級研究者 |
754 |
|
中級研究者 |
459 |
|
|
その他 |
700 |
|
|
合計 |
1,913 |
|
|
難関攻略計画 |
高級研究者 |
224 |
|
中級研究者 |
251 |
|
|
その他 |
373 |
|
|
合計 |
848 |
(4) 研究成果
1)材料科学分野
材料科学分野において、中国の科学技術論文が、国外の主要書誌情報データベースに収録された件数を見ると、中国において重要な評価指標になっているSCI(Science Citation Index)の件数が圧倒的に多くなっている。
また、EI(Engineering Index)の収録件数の伸びが顕著で、2005年実績(3433件)は2000年(589件)と比べるとほぼ6倍、直前の2004年実績(1697件)と比べても2倍以上の高い伸びを示している。ISTP(Index to Scientific & Technical Proceedings)も年によってバラツキはあるものの、2005年(1975件)は2000年以降で見ても最高となっている。
|
年度 |
書誌収録 |
順位 |
|||
|
SCI |
EI |
ISTP |
合計 |
||
|
2000 |
2,363 |
589 |
690 |
3,642 |
4 |
|
2001 |
2,713 |
649 |
495 |
3,857 |
4 |
|
2002 |
3,760 |
844 |
883 |
5,487 |
3 |
|
2003 |
5,261 |
1,021 |
1,328 |
7,610 |
3 |
|
2004 |
4,718 |
1,697 |
442 |
6,857 |
4 |
|
2005 |
6,657 |
3,433 |
1,975 |
12,065 |
5 |
2005年の材料科学分野の論文収録数は、SCI:6657件、EI:3433件、ISTP:1975件、合計では1万2065件となっており、収録総数で比較すると化学分野(2万7977件)、物理学分野(1万6616件)、コンピュータ工学分野(1万3433件)、電子・通信・自動制御分野(1万2668件)に次いで5位に入っている。
2)ナノテクノロジー分野
ナノテクノロジー分野に限定した研究成果の詳細な統計データはないが、「第10次5ヵ年」期間中の「863計画」および「難関攻略計画」におけるナノテクノロジー分野の研究成果を表2.8に示す。
|
項目 |
863計画 |
難関攻略計画 |
|
国内の発表論文数 |
930 |
287 |
|
海外での発表論文数 |
960 |
136 |
|
特許取得件数 |
150 |
172 |
|
うち発明特許取得件数 |
131 |
160 |
|
国家自然科学賞受賞数 |
3 |
3 |
|
民間および海外受賞数 |
8 |
8 |
|
成果移転プロジェクト数 |
23 |
31 |
|
成果移転収入(万元) |
1,354 |
5,060 |
|
生産高増加分(万元) |
240,334 |
77,964 |
|
納税(万元) |
15,367 |
- |
また、中国のナノテクノロジー研究開発の大まかな進展状況を把握するため、中国国家知的財産権局特許データベースを利用し、ナノテクノロジー関連の特許出願公開件数について調べた。それによると、1985~2002年12月までの中国におけるナノテクノロジー関連の発明特許と実用新案の出願公開件数はそれぞれ2,250件、134件であったが、1985~2007年4月までの発明特許と実用新案の出願公開件数はそれぞれ7,959件、671件に達した。
ナノテクノロジー関係の発明特許と実用新案がわずか4年の間に急増したのは、「第10次5カ年」期間中に中国政府が政策、資金の面からナノテクノロジー分野の発展に力を注いだことが大きく影響している。中国における機関別に見たナノテクノロジー関連特許の出願公開件数の推移および各機関の割合をそれぞれ表2.9、図2.1~2.2に示す。
|
分類 |
特許出願公開件数 |
|||
|
1985~2002年 |
1985~2007年4月 |
|||
|
発明 |
実用新案 |
発明 |
実用新案 |
|
|
研究機関 |
294 |
15 |
1,130 |
60 |
|
高等教育機関 |
487 |
24 |
4,388 |
148 |
|
企業 |
258 |
25 |
1,490 |
145 |
|
個人 |
1,211 |
70 |
1,323 |
328 |
|
合計 |
2,250 |
134 |
8,331 |
681 |
図2.1 ナノテクノロジー関連発明特許の出願公開件数(機関別、1985~2002年12月)
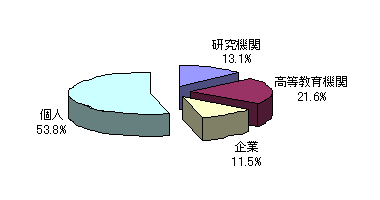
図2.2 ナノテクノロジー関連発明特許の出願公開件数(機関別、1985~2007年4月)
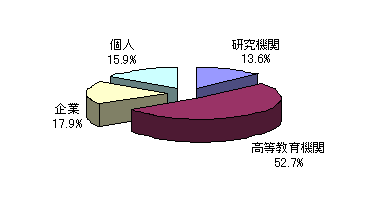
これまでの実績を見ると、2002年までは個人出願公開件数の割合が最も高く、全体の53.8%を占めた。これは、2001年にある1人の個人が940件の漢方薬関連特許を出願したためである。実際、これを除くと2007年までの発明特許の個人出願件数はあまり増えていない。高等教育機関の出願公開件数は、2003年から2007年4月にかけて大幅に増加し、全体の52.7%を占めた。
中国における分野別に見たナノテク関連特許の出願公開件数の推移を表2.10に示す。この表からも明らかなように、2003年以降、ナノ粒子材料やナノチューブ、ナノエレクトロニクス、ナノ医薬といった分野で発明特許の出願件数が大幅に増加している。
|
分類 |
特許出願公開件数 |
|||
|
1985~2002年 |
1985~2007年4月 |
|||
|
発明 |
実用新案 |
発明 |
実用新案 |
|
|
ナノ粒子材料 |
201 |
6 |
1,723 |
117 |
|
ナノチューブ |
98 |
7 |
1,219 |
60 |
|
カーボンナノチューブ |
83 |
7 |
1,029 |
55 |
|
ナノ重合高分子 |
89 |
0 |
215 |
2 |
|
ナノエレクトロニクス |
59 |
2 |
902 |
86 |
|
ナノ半導体 |
32 |
2 |
497 |
44 |
|
ナノ医薬 |
963 |
1 |
1,439 |
35 |
|
その他 |
725 |
109 |
935 |
272 |
① ナノ構造材料・新機能材料
中国はナノ粒子材料、ナノカーボン材料、ナノ重合高分子材料などの分野での基礎研究を積極的に行っているため、こうした分野での特許出願件数が多く、全体の約半分を占めている。このうちナノカーボン材料については、製造方法に関する出願公開件数が全体の約半分を占めており、一部の成果は世界先進レベルに達しているが、日欧米に比べ、プラズマ、レーザなどハイテク方法を用いた製造方法に関する研究が比較的遅れている。
また、エレクトロニクス分野や医薬分野への応用研究が少ない。ナノ粒子材料については、特許の多くが製造方法に関するもので、日欧米に比べ応用研究が弱いと見られている。ナノ重合高分子材料についても、材料の開発と製造に関する特許が多いものの、応用面では、主としてナノ塗料、ナノゴムなどに限られている。しかし、こうした分野に関して、中国は基礎研究だけではなく、応用や産業化に向けての努力を強化している。
② ナノ加工技術分野
中国では、この分野に関する基礎研究は中国科学院や一部の大学などを中心に行われており、特許出願件数も少ない。一方で、マイクロ加工技術のプラットフォーム建設に努力が傾注されており、数多くの研究開発が行われている。
③ ナノエレクトロニクス分野
中国では、この分野での応用はまだ比較的少ないものの、特許出願公開件数は大幅に増加している。近年、欧米の留学組が帰国して研究の中核となり多くの研究が行われていることから、近い将来、急速に実力が向上すると考えられている。
④ バイオ・医薬分野
中国はバイオ分野の応用研究が少なく、特許出願公開件数も少ない。一方、医薬分野での特許出願公開件数は1985年以降2002年までで963件、また2007年4月までで1439件に達しており件数的には多い。しかし、その多くは漢方薬に関するものであり、日欧米に比べ、体内輸送システム、医療用粒子材料、医療用チップ、再生医療用材料などの分野での応用研究成果が少なく、研究レベルも劣っている。
一方で、こうした分野においても近年、欧米の留学組が帰国し、中心的存在として多くの研究開発を行っている。また、日欧米に比べ臨床試験などに関する許認可の法的制約が比較的少ないため、今後の進展が注目されている。
(5) 国際研究活動の展開
中国は、1980年代から科学研究および技術開発の国際協力に力を入れてきた。ナノテクノロジー・材料分野においても、各種レベルで二国間および多国間での国際協力を行っている。二国間での協力活動の内容を表2.11に示す。
なお、科学技術部が2006年11月29日に公布した「『第11次5ヵ年』国際科学技術協力実施綱要」(「"十一五"国際科技合作実施綱要」)では、ナノテクノロジー分野は第11次「5ヵ年計画」期間中の戦略的重点分野と位置付けられており、主に①ナノ加工とナノデバイス②ナノ材料とナノ構造③ナノ医学とナノバイオ④ナノ構造の表象方法と計測⑤ナノデバイスの集積に関する中核技術⑥ナノ理論とモデル――などの課題について重点的に国際協力を行うとの方針を明らかにしている。
|
|
概要 |
|
中国-日本 |
日中両国は1980年5月、「日中科学技術協力協定」を締結した。同協定の下で、日中科学技術協力委員会を設立し、農業、原子力、環境保護などの分野にわたって140以上の科学技術協力プロジェクトが実施された。2003年2月の第10回委員会では、新材料(ナノ材料を含む)をはじめ、バイオ技術・生命科学、情報通信技術、環境・エネルギーおよび社会基盤技術などを今後の重点協力分野とすることが確認された。その後、新材料(ナノ材料を含む)に関する共同研究・開発が行われた。2005年11月には、中国国家ナノ科学技術センターと三菱商事イノベーションセンターが協力し、ナノハイブリッド材料の共同開発を行った(「国家納米科学中心工作簡報」2006年第2号)。2007年12月、日中間のナノ技術の課発と応用に関する産官学協力を促進するため、中国科学技術部の許可を得て上海の国家ナノ技術・応用研究センターに日中ナノ技術産業化協力基地が設立された。 |
|
中国-米国 |
中国と米国は1979年1月、「中米科学技術協力協定」を締結した。同協定の下で、両国政府は材料科学を含む多くの科学分野で約50の協力協議書を締結し、北京電子・陽電子衝突型加速器などの大型プロジェクトを完成させた。2005年6月、浙江省政府および浙江大学は米国のカリフォルニア・ナノシステム研究所と共同で杭州に浙江国際ナノテク研究所を設立し、システムバイオ学、ナノ材料製造および有機EL技術などを中心に共同研究を行うことを発表した。2006年10月の第12回中米科学技術協力委員会では、両国のナノテクノロジー分野における協力強化が合意された。浙江国際ナノテク研究院は2008年11月24日、浙江国際ナノテク共同研究開発センターに改組され、国家レベルのナノ技術開発センターとして、ナノバイオ・医薬、ナノ材料およびナノエレクトロニクスなどの重点分野で、米国をはじめ、英国、ドイツ、フランス、ロシアなどの研究機関、大学との共同研究・開発を展開することになっている。 |
|
中国-英国 |
中国と英国は1978年11月、「中英科学技術協力協定」を締結した。その後、1998年9月には「中英科学技術協力協議書修正案」に署名し、科学技術分野での協力強化を図った。両国政府は2004年5月、「中英共同声明」を公表し、科学技術協力を重点協力分野とすることを決定した。共同声明を受け、中国政府は2005年を「中英科学技術年」とし、シンクロトロン加速器など13の分野を重点分野とし、130以上のプロジェクトを実施した。また、その一環として両国は2005年1月、「中英科学技術協力計画」を策定し、ナノ材料を含む6つの優先協力分野で積極的に共同研究活動を行うとした。具体的には、マイクロ構造分析技術の専門家である英国オックスフォード大学のGeorge Smith教授が主席を務める中英材料協会を設立し、ナノ材料、エネルギー材料、バイオ材料を中心とする共同研究が行われた。また、2005~2006年にかけて、重慶市とロンドンでそれぞれ第1回および第2回中英先進材料シンポジウムが開催された。2008年4月には協力範囲をEU全域に拡大し、重慶市で第3回中国-EU先進材料シンポジウムを開催した。その後、中英エネルギー材料協力推進委員会、中英バイオ材料協力促進委員会、中国-EU軽合金材料協力推進委員会が設置され、それぞれの活動プランが策定された。 |
|
中国-ドイツ |
中国とドイツは1978年11月、「中独科学技術協力協定」を締結した。同協定の枠組みの下で、両国政府は新材料を含む多くの科学分野で共同研究を行った。中国国家自然科学基金委員会とドイツ研究連合会は2000年10月、北京市に共同で「中独研究促進センター」を設立し、両国が毎年それぞれ1,000万元を投入し、ナノ科学や情報技術、材料学、食品栄養学、旱魃防止など6分野において両国の共同研究を支援してきた。また、中国科学技術部とドイツ科学技術省は2005年4月、湖南省長沙市に中独ナノバイオ技術協会を共同で設立し、「中独ナノバイオ技術国際シンポジウム2005」を開催した。ドイツのBASF社は2006年、中国の35の大学および研究機関と契約を結び、高分子材料、工業用触媒、ナノバイオ技術に関する51の共同研究プロジェクトを選定、実施した。 |
|
中国-フランス |
中国とフランスは1978年1月、「中仏科学技術協力協定」を締結した。同協定の枠組みの下で、両国は1991年、「中仏先進研究計画(PRA)協力協議書」を締結し、材料、バイオ技術などを含む6分野での協力に合意した。これまでに専門家委員会を10回以上開催し、382件のプロジェクトを実施した。2006年には、科学技術部の支持の下で、アモイ大学とフランス国家科学研究センター、パリ高等師範学院がアモイに「ナノバイオ・化学国際共同実験室」を設立し、基礎化学や分析化学、物理化学、電気化学などの分野で7つの共同研究プロジェクトを実施した。同実験室は2008年、国家レベル国際科学技術研究開発センターに指定された。 |
|
中国-ロシア |
中国とロシアは1992年12月、「中露科学技術協力協定」を締結し、新材料、バイオ技術などを含む9つの優先分野における協力強化に合意した。その後、1996年までに245件の科学技術協力プロジェクトが実施された。1998年12月には、中国科学技術部の許可を受け、新材料、バイオ技術などの分野での研究成果の産業化を図るため、山東省煙台市で「中露ハイテク産業化協力モデル基地」の建設がスタートした。また、2005年11月、湖南省にある中南大学とロシア非鉄金属加工研究院およびロシア連邦宇宙開発局複合材料研究院は共同で「中露国際新材料工程技術産業化センター」を設立した。ロシアのプーチン大統領(当時)が2007年4月、「ロシアにおけるナノ産業発展戦略」を打ち出したことを受け、2008年7月にロシアのナノテク会社関係者が訪中して中国科学技術部と協議を行い、二国間におけるナノテクノロジー分野に関する協力協定を両国首相会談の場で締結することで合意した。 |
|
中国-韓国 |
中国と韓国は1992年9月、「中韓科学技術協力協定」を締結した。同協定の枠組みの下で、新材料を含む14の分野で18の協力協定や覚書を締結した。2003年7月の両国首脳会談では、一層の協力の推進に関する声明が発表され、新材料やバイオなどの分野で共同研究と産業化を行うことが合意された。両国は2005年7月、「中韓ナノ技術研究センターの共同建設に関する覚書」に署名し、2007年7月までに中国国家ナノ科学技術センターと韓国科学技術院にそれぞれナノ技術研究センターが設立された。その他、新材料共同研究センター、光電子技術共同研究センターなども設立された。 |