3.2 電子情報通信分野の現状および動向
(1) 全体概要
中国の電子情報通信産業は、1978年から1980年代中期にかけて、軍事産業から軍事・民生産業への転換を果たした。また、80年代中期から90年代初期には消費電子製品の生産が開始され、90年代末期にかけてはハードの製造やソフトウェアの制作・応用と情報サービス業の共同発展を実現した。
この分野において、中国は多方面で日米欧をキャッチアップしつつあり、研究者数、発表論文ともに急速に増加してきている。とくにレベルアップが顕著なのは、VLSI、ディスプレイ、データベース、並列コンピューティング、光通信などである。
珠江デルタや長江デルタ、環渤海地域では、電子情報産業ベルトが形成され、携帯電話、マイクロコンピュータ、デジタル電話交換機、カラーテレビ、デジタルカメラなどの電子製品の生産高が世界1位になった。
こうしたなかで、工業・情報化部の李毅中・部長は2008年12月、技術の飛躍的進歩をめざす重点分野の1つとして電子情報分野をあげ、ソフトウェア、IC、新型フラットパネル・ディスプレイ、半導体照明、次世代ネットワークなどの中心となる技術の研究開発、産業化を重点的に支持し、ソフトウェアとIC産業の新しい政策を打ち出す意向を明らかにした。
また、温家宝首相が2009年2月18日に召集した国務院常務会議では、「電子情報産業調整振興規画」が審議され原則可決された。会議では、米国の金融危機を発端とした世界的な景気後退を受け、国際市場での需要が急減し、世界の電子情報産業が大きな調整局面を迎えているとの認識で一致した。
このため、電子情報産業の振興にあたっては、自主的イノベーションの強化や産業の発展環境の改善に加え、情報化・工業化の融合の加速、重要プロジェクトによる技術面での飛躍的な進歩、新規応用による産業発展の推進に努力を払うことが重要との方針が確認された。また、常務会議では、電子情報産業における今後3年間の重要任務が以下のように決められた。
- 産業体系を健全化し、基幹産業の安定的な成長を確保する。コンピュータ産業の競争力を引き上げ、電子部品と関連製品の改良を加速し、AV(音響・映像)産業のデジタル化を重点的に進める。
- 自主的イノベーションをベースとして、中核技術を飛躍的に進歩させ、自主独立したIC産業体系を構築するとともに、新型ディスプレイ産業の障害をクリアーし、ソフトウェア産業の自主的発展能力を強化する。
- 応用を進めることによって発展を促し、サービスおよびサービスモデルの革新を推進する。各種分野での情報技術の応用を拡大する。
また、以下の具体的措置が打ち出された。
- 内需拡大に加え、電子情報製品の応用、産業の発展領域の開拓に力を入れる。
- 資金投入を拡大し、IC回路の改良、新型ディスプレイやカラーテレビのモデルチェンジ、第3世代移動通信産業における飛躍的な発展、デジタルテレビの普及、コンピュータの性能向上や次世代インターネットの応用、ソフトウェアと情報サービス関連のプロジェクトを実施し、社会資金の投入が電子情報産業に向かうよう奨励する。
- 自主的イノベーション能力の構築を強化する。関連する国家科学技術重大専門プロジェクトの実施を早め、企業によるM&A(合併・買収)を支援し、公共技術サービス環境の健全化をはかる。
- サービスのアウトソーシングを促進し、企業が海外で研究開発を行い、生産基地やマーケティング・ネットワークを構築するよう支援する。
- 政策面での支援を強化し、ソフトウェアとIC産業発展に向け関連奨励政策の一層の充実をはかり、デジタルテレビ産業の政策を実施する。また、ハイテク企業の認定目録と基準の調整を行い、これまで通り電子情報製品の輸出税還付に力を入れる。さらに、輸出貸付と信用保険による支援を一層拡大し、中小企業における債券発行の試行対象範囲を拡大する。
なお、工業・情報化部が2009年2月16日に公表した電子情報産業統計によると、同分野における一定規模以上の国内企業の2008年主要業務収入は、前年に比べて14.8%多い5兆8826億元に達した。このうち、製造業は前年より12.8%多い5兆1253億元、ソフトウェア産業は29.8%増の7573億元を記録した。また、工業増加値は対前年比14.7%増の1兆1408億元となった。
工業増加値は、企業の生産活動の業績を示す指標の1つで、各種財務あるいは統計データで用いられており、中国では工業増加値が重視されている。具体的には、〔工業増加値=当期総生産高-中間投入コスト+当期増値税額〕で求められる。このうち中間投入コストには、当期の労賃のほか、生産のために使用された原材料や部品、電気・ガス・石炭などのエネルギー、外部への支払いが発生した部品やサービスの費用などが含まれる。
表3.12に電子情報通信分野における製造業の業種別実績、表3.13に主要製品の生産量を示す。
|
業種 |
企業数 |
主要業務収入 |
工業増加値 |
||
|
2008年合計 |
増減(%) |
2008年合計 |
増減 |
||
|
合計 |
16515 |
512530538.0 |
12.8 |
114078575.1 |
14.7 |
|
通信設備製造業 |
1396 |
84601418.3 |
6.6 |
19178904.7 |
12.3 |
|
レーダー製造業 |
47 |
1697059.8 |
30.3 |
475176.7 |
30.3 |
|
放送設備製造業 |
402 |
3284068.7 |
10.0 |
942052.1 |
9.9 |
|
コンピュータ製造業 |
1460 |
171343075.6 |
7.3 |
26907131.0 |
7.9 |
|
家庭用AV製品製造業 |
1001 |
38077595.6 |
9.3 |
7143986.7 |
10.8 |
|
電子デバイス製造業 |
2464 |
65746474.9 |
22.0 |
18697535.7 |
21.8 |
|
電子部品製造業 |
6079 |
93981874.1 |
16.9 |
25609025.8 |
17.1 |
|
電子測量計器製造業 |
683 |
5730938.2 |
20.4 |
1924103.8 |
20.5 |
|
電子専用設備製造業 |
1359 |
13105274.5 |
35.1 |
4017437.4 |
35.1 |
|
電子情報電機設備製造業 |
1062 |
13347033.2 |
15.7 |
3680616.9 |
16.2 |
|
その他電子情報工業 |
562 |
21615725.1 |
17.4 |
5502604.3 |
20.6 |
|
(外国・香港・マカオ・台湾投資企業) |
7546 |
396183038.5 |
9.6 |
84131811.1 |
11.6 |
|
(国有持株会社) |
964 |
34345134.5 |
15.2 |
7722289.1 |
13.3 |
|
製品 |
単位 |
2008年合計 |
2007年合計 |
増減 |
|
携帯電話(GSM CDMA) |
万 |
55964.0 |
54857.9 |
2.0 |
|
デジタル交換機 |
万(回線) |
4583.9 |
5387.0 |
-14.9 |
|
FAX |
万 |
769.9 |
888.5 |
-13.3 |
|
カラーテレビ |
万 |
9033.1 |
8478.0 |
6.5 |
|
パソコン |
万 |
13666.6 |
12073.4 |
13.2 |
|
(内ノートパソコン) |
万 |
(10858.7) |
(8671.4) |
(25.2) |
|
ディスプレイ |
万 |
13364.6 |
14438.1 |
-7.4 |
|
プリンタ |
万 |
4334.0 |
4234.7 |
2.3 |
|
ディスクリート半導体 |
万 |
24611353.3 |
25045769.0 |
-1.7 |
|
IC |
万 |
4171490.6 |
4116232.0 |
1.3 |
|
デジカメ |
万 |
8188.3 |
7493.5 |
9.3 |
(2) エレクトロニクス
1)マルチコアプロセッサ
中国は、高周波・アナログの集積回路、集積回路のインテグレーション、ディスプレイ技術の産業技術力で世界最先端にあるが、全体では日米欧韓とはまだ差がある。
そうしたなかで、次世代スーパーコンピュータにも採用が予定されている中国が独自に開発中の中央演算処理装置(CPU)「龍芯3号」の大量生産が視野に入ってきた。
中国科学院は2008年8月、米カリフォルニア州で開催された「Hot Chips展」で「龍芯3号」を公開したことを明らかにした。これを受け、中国科学院・計算技術研究所の徐志偉・副所長は同11月30日、2008年内に4コア、2009年には8コアバージョンを完成させ、大量生産を開始する考えを表明した。
中国科学院・計算技術研究所の李国傑所長は2006年9月13日、中国が独自に開発した中央演算処理装置(CPU)「龍芯2号」の検証状況報告会で、「龍芯2号高性能汎用CPUの回路設計」(龍芯2E)が「863計画」の検証作業をクリアしたことを明らかにするとともに、「第11次5ヵ年」期間(2006~2010年)内に、8~16コアのマルチコアプロセッサ「龍芯3号」を開発する計画を明らかにしていた。
計算技術研究所は2001年3月、1000万元を投入して「龍芯プロジェクトチーム」を立ち上げた。その後、2002年8月に「龍芯1号」、2003年10月に「龍芯2号」の試験に成功し、2005年に64ビットの「龍芯2号」、2006年3月に「龍芯2号」のアップグレード版「龍芯2F」を開発した。
「龍芯2F」は、従来の「龍芯2E」に比べて、消費電力が少なくコストが低い。計算技術研究所の李国傑所長は2007年10月13日、欧州の半導体メーカーであるSTマイクロエレクトロニクス社が「龍芯2F」の大量生産を開始したことを明らかにしている。
2)液晶モジュール
中国では、薄型(フラット)テレビの市場拡大が続くなかで、今後、熾烈な価格競争が予想されることから、液晶モジュールの生産拡大に拍車がかかっている。家電大手のTCL集団は2009年3月3日、同社初の液晶モジュール生産ラインの試作が終了し、全面的な量産段階に入ったことを明らかにした。同社によると、2月の生産量は32インチ液晶モジュールが2万700枚、また3月の生産量は5万枚まで拡大される見通しという。
同社の液晶モジュール生産ラインは国内最大規模で、投資額が33億元に達したと見られている。TCLは、独自開発の液晶モジュール生産技術を利用し、生産コストを5%以上削減し、薄型テレビの販売価格を6%引き下げることを計画している。
一方、康佳集団も2009年3月、江蘇省昆山市に8億8600万元を投じて液晶モジュール生産基地を建設する計画を発表した。同社によると、2009年下半期に生産を開始し、国内最大規格となる47インチ液晶モニターを年間720万枚生産する予定で、年生産額は128億元に達すると見込まれている。同社以外にも、海信や創維などの各社もモジュール生産に乗り出している。
こうした背景には、中国政府が打ち出したカラーテレビ産業の戦略的転換がある。国家発展改革委員会は2009年2月25日、薄型ディスプレイ産業の発展を促進する方針を打ち出した。それによると、2009年から3年間にわたって、カレーテレビ産業の転換に向けた政策を実施し、一部プロジェクトに対しては資金面などから支援を行う。
国家発展改革委員会によると、今回の政策はカラーテレビ産業の構造調整と薄型テレビの産業チェーン整備を目標としている。同委員会は、自主発展能力の向上を中心に据え、ディスプレイ重大建設プロジェクトを牽引力として現在の主流ディスプレイ技術と今後の発展を配慮したうえで、カラーテレビ産業の拡大と強化を実現するとともに、薄型ディスプレイ産業チェーンを整備するという方針を明らかにした。
中国電子商会電子製品消費調査弁公室によると、中国の都市家庭が保有する薄型テレビは2008年末時点で2800万台に達し、このうち液晶ディスプレイが85%、プラズマディスプレイが15%を占めたと推定している。なお、カラーテレビ市場全体に占める薄型テレビの割合は30%を上回っている。
(3) フォトニクス
中国はフォトニクス分野において、研究水準や技術開発水準では日米欧に比べると劣るものの、光通信や光メモリ、固体照明・発光デバイスの産業技術力では世界トップレベルにある。
そうしたなかで、世界トップレベルのハイビジョン規格を備え、ブルーレイ製品よりはるかに低コストの中国製レッドレイ・ハイビジョンディスク(NVD)プレーヤーと対応ソフトが2009年1月21日、湖北省武漢市の中国光谷(オプティカルバレー)で世界に先駆けて発売された。
今回、発売されたNVDプレーヤーは「九州レッドハイビジョン」という名称で、12G以上のNVDやDVDの光ディスクを見ることができ、NVD光ディスク1枚で135分のハイビジョン番組を録画することができる。4つのタイプがあり価格は999元から約2000元で、全部で1万台が発売された。同時に発売された対応ソフトは50種類で、記録用のNVDディスク50万枚も発売された。
武漢高科集団は2004年末、武漢光電国家実験室、中国科学院上海光機所と共同で、ブルーレイとはまったく異なるレッドレイ技術を採用し、初の自主知的財産権を持ったレッドレイ・ハイビジョンディスクプレーヤー(NVD)を2006年に開発した。
湖北省と武漢市はこれまでに先行投資として6億元を拠出し、中国光谷にNVDモデルプロジェクト拠点を建設した。さらにレッドレイ製品のシリーズ化とモデルの多様化を進めるとともに、海爾集団や長虹集団、新科集団、TCL集団などの大手企業や台湾・香港の企業、海外企業と協力し、国際市場の開拓にも着手する意向を表明している。2009年の販売予定台数は50万台となっているが、2年後には生産規模を年産300万台に拡張する予定になっている。
産業化の第二段階として、新たに30億元を投資し、武漢市の光ディスク産業基地としての利点を活かして、レッドレイ・ハイビジョンの科学研究基地や産業化基地を建設する計画も浮上してきている。2009年内には、初代製品の性能を大幅に上回る2世代目のNVDプレーヤーが販売されることになっている。
また、NVDはDVDの生産ラインで生産することができるため、中国の光ディスク産業は今後、外国の高額の特許から解放され、世界の光メモリ産業の新しいスキームが構築されると期待されている。
なお中国光谷は、中国の光通信産業の発祥地である武漢に誕生した光電子情報産業を主力とするハイテク産業の一大中心地であると同時に、国務院が認可した最初の国家級ハイテク産業開発区の1つで、中国最大規模の光ファイバー・ケーブル生産基地のほか、光電子部品の生産基地、研究開発基地がある。
一方で、上海市の松江工業開発区に建設された中国初の片面2層ブルーレイディスクの複製・製造ラインが2009年1月20日、生産を開始した。現時点では、単一の生産ラインとしては世界最大の生産能力を持つという。
ソニー・ミュージックと上海新匯グループ、上海精文投資会社の合弁企業である上海新索音楽有限公司によって生産が開始された。生産ラインは、世界最先端の技術を導入し、月にBD25(片面)を50万枚、BD50(両面)を40万枚生産することができ、世界全体の生産量の70%以上を占めることになると見られている。松江工業開発区で生産されたブルーレイディスクは主として中国国内で販売される。
(4) コンピューティング
1)ハードウェア
中国科学院・計算技術研究所の李国傑・所長と清華大学高等教育センターの姚期智・教授は2008年11月11日、北京で開催された「情報とイノベーション学術フォーラム」で講演し、中国の計算機研究が世界に比べて2~3年、技術的には1.5世代程度遅れているとの認識を示した。
両氏によると、チップ規模とソフトウェア分野で差が顕著であることに加えて、世界水準のオペレーティングシステム(OS)がなく、銀行や空港等の重要施設で使うアプリケーションソフトも海外製品に依存しているという。
こうしたなかで、各国のIT技術水準を測る重要な指標と言われているスーパーコンピュータ分野で中国は大きな一歩を記した。2008年11月に公表されたスーパーコンピュータのトップ500ランキングで、上海スーパーコンピュータセンター(上海超級計算中心)に設置されている「曙光5000A」がトップ10入りを果たした。
「曙光5000A」は、中国科学院計算技術研究所と中国の大手サーバーベンダーである曙光情報産業有限公司が共同で開発したもので、スーパーコンピュータの性能を測る代表的な数値であるLINPACKベンチマークで毎秒180兆6000億回の演算能力(180.6テラ・フロップス=TFLOPS)を持つ。
同機は、「国家ハイテク研究開発発展計画」(「863計画」)における高性能コンピュータとコアソフトウェア重要特定プロジェクトの1つで、インターネット向けの高性能コンピュータであると同時に、情報サービス向けのスーパーサーバーなど、各種の目的に応じたサービスを提供することができる。
「曙光」シリーズは1号からスタートし、その後、1000、2000、3000、4000を経て現在の5000Aに到達した。「曙光1000」が開発された時点では、中国の高性能コンピュータは世界の最先端水準から8年遅れていると見られていた。2004年6月には10TFLOPSを達成した「曙光4000A」を開発し、世界との差を4年程度に縮めた。
曙光情報産業有限公司は2005年7月12日、スーパーコンピュータの浮動小数点演算(FPU)速度を100~200TFLOPSにまで引き上げ、2010年には1000TFLOPSを達成する第6世代スーパーコンピュータを完成させる計画を明らかにしていた。
また、中国のスーパーコンピュータは、IBMやインテル、AMD等、国外メーカーのCPUチップを使用していたが、2007年末、中国国産のチップ「龍芯2F」を搭載した初めての1TFLOPS級のスーパーコンピュータが中国科学技術大学と中国科学院計算技術研究所によって共同開発されている。
国産チップを搭載したスーパーコンピュータの開発は、中国科学院の陳国良・院士を総括責任者として、世界トップレベルの大学をめざすことを目的として一部の大学を重点化する「985計画」に採択されて2007年5月にスタートした。
なお、2008年10月7日付の新華社電は、曙光情報産業有限公司の歴軍・総裁が、中国が独自に開発した「龍芯4号」を用いて2010年に1000TFLOPSのスーパーコンピュータ「曙光6000」を完成させる方針を明らかにしたと報じている。
歴軍・総裁は、今後の国産の「龍芯」がコンピュータの主役となり、技術上の障害はなくなるとの考えを示したうえで、「曙光6000」は高性能だけではなく、超高密度、超低価格、超省エネ、超汎用といった特徴を持つと述べた。
中国高性能計算機標準工作委員会は2008年5月9日、IBMなどの海外の大手メーカーに対抗するため、中国高性能計算機産業連盟の発足を公表している。スーパーコンピュータの基準制定や産業化を推進するのが目的で、発足時点ではインテルやAMD、曙光、レノボといったメーカーのほか、中国科学院計算技術研究所、北京気象局などが参加している。
2)ソフトウェア
工業・情報化部は2009年2月6日、国内ソフトウェア産業の2008年の業務収入が前年比29.8%の7572億9000万元に達したことを明らかにした。伸び率も、前年比で8.3ポイント上昇した。
ソフトウェア産業の業務収入の内訳を見ると、ソフトウェア製品が対前年比で32%の増加を示し、業務収入全体の41.8%に相当する3165億8000万元となった。ソフトウェア技術サービスも前年に比べて39.9%の高い伸びを示し1455億元となり、業務収入全体の19.2%を占めた。このうち、アウトソーシングサービス収入は203億元に達した。
また、システムインテグレーション(SI)収入は1616億4000万元となり、対前年比で25.2%増加した。このほか、組み込みシステムソフトウェア収入は1118億2000万元(対前年比17.8%)、IC設計収入217億4000万元(同16%増)などとなった。
ソフトウェア産業の業務収入を地域別に見ると、北京市が最も多く約1573億元、以下、広東省1415億元、江蘇省1202億元などと続いている。
中国ソフトウェア産業協会(中国軟件行業協会)によると、ソフトウェア産業の従業員は180万人に達しており、工業経済に占める割合も2007年の12%から13.6%に上昇している。同協会によると、巨大な国内市場の存在が、ソフトウェア産業の高成長を支える原動力になっている。
中国政府は、ハード部分については量的にも質的にも国際競争力が上がってきたと判断しており、ソフトウェア産業の発展に力点を置くようになってきている。地方政府も競ってソフトウェア産業の発展に努力を払っている。
こうしたなかで、黒龍江省におけるソフトウェア産業の発展を促進することを目的として、2008年6月16日、中国科学院ソフトウェア研究所ハルビン支部および国家基礎ソフトウェア・エンジニアリング研究センター・ハルビン分所が設立された。同省内での技術開発支援や成果の産業化、人材の育成等への貢献が期待されている。
中国科学院ソフトウェア研究所はこれまでに国家重点実験室と国家エンジニアリング研究センターをそれぞれ3ヵ所ずつ設立しており、基礎的フロンティア研究、戦略的ハイテク研究、国防に関するハイテク研究の3大科学研究体系のさきがけとしている.
国家基礎ソフトウェア・エンジニアリング研究センターは、中国における基本ソフト分野の革新的技術開発に取り組んでおり、独自の知的財産権による基本ソフト技術・製品を所有している。
一方で、中国のソフトウェア産業の発展に対する海賊版の影響が懸念されている。2007年12月13日付「科学時報」によると、国家版権局はソフトウェアの海賊版が10ポイント増加すればソフトウェア産業における経済損失が70億元に達するとの試算結果を発表し、海賊版問題がソフトウェア産業成長の障害になっているとの考えを明らかにしている。
なお、国家知識産権局が2008年4月に公表した「2007年度中国ソフトウェア海賊版比率調査」によると、ソフトウェアの海賊版比率は2006年の24%から20%に低下した。
|
地域名 |
企業数 |
ソフトウェア業務収入 |
ソフトウェア製品収入 |
システムインテグレーション収入 |
|||
|
万元 |
増減(%) |
万元 |
増減(%) |
万元 |
増減(%) |
||
|
合計 |
16194 |
75728773 |
29.8 |
31657855 |
32 |
16164477 |
25.2 |
|
北京市 |
4517 |
15729930 |
21.4 |
6518782 |
21.7 |
3990978 |
21.5 |
|
天津市 |
245 |
1348692 |
18.8 |
111111 |
75.9 |
52658 |
21.6 |
|
河北省 |
214 |
343769 |
30.3 |
194665 |
56.1 |
115624 |
16.4 |
|
山西省 |
76 |
49858 |
36.9 |
28946 |
27.3 |
8192 |
65.8 |
|
内蒙古 |
59 |
173404 |
30.3 |
106796 |
123.6 |
20073 |
54.4 |
|
遼寧省 |
550 |
3723198 |
59.1 |
1605241 |
20.2 |
844875 |
32.6 |
|
吉林省 |
188 |
1080000 |
16.1 |
320000 |
10.3 |
410000 |
17.1 |
|
黒龍江省 |
334 |
605248 |
17.5 |
199120 |
10.6 |
215632 |
2.7 |
|
上海市 |
1166 |
5700000 |
15.4 |
2410000 |
17.6 |
1210000 |
5.2 |
|
江蘇省 |
1457 |
12015384 |
30.8 |
2414536 |
31.9 |
1767431 |
29.4 |
|
浙江省 |
894 |
4222409 |
23.1 |
1020804 |
22.8 |
1219174 |
22.6 |
|
安徽省 |
149 |
364524 |
33.7 |
170413 |
38.2 |
141483 |
9.7 |
|
福建省 |
510 |
2602900 |
26.3 |
739500 |
31 |
843600 |
27.8 |
|
江西省 |
64 |
317516 |
70.7 |
92032 |
90.6 |
154240 |
63.9 |
|
山東省 |
561 |
3786611 |
23.7 |
1108995 |
37.2 |
1033148 |
31.6 |
|
河南省 |
191 |
772886 |
35 |
313265 |
34 |
343019 |
35.6 |
|
湖北省 |
208 |
919894 |
33.7 |
576838 |
63.3 |
178367 |
-12.3 |
|
湖南省 |
400 |
956198 |
33.6 |
511200 |
36.2 |
204902 |
31.1 |
|
広東省 |
2854 |
14148721 |
26.1 |
10126432 |
29.4 |
1237566 |
22.5 |
|
広西自治区 |
60 |
254896 |
22.8 |
128021 |
25.1 |
75646 |
17.7 |
|
海南省 |
22 |
15628.48 |
28.3 |
4004.88 |
4.9 |
2724.17 |
-22 |
|
四川省 |
420 |
3739885 |
56.1 |
2107550 |
66.3 |
956267 |
45.7 |
|
貴州省 |
70 |
170793 |
51.4 |
68098 |
40.4 |
92168 |
72.9 |
|
雲南省 |
62 |
174363 |
-11.6 |
36599 |
-1.1 |
122056 |
-12.5 |
|
重慶市 |
129 |
710201 |
13.5 |
289062 |
10 |
190283 |
4 |
|
陝西省 |
620 |
1562000 |
8.3 |
410400 |
122.1 |
580500 |
-13.6 |
|
甘粛省 |
48 |
99566 |
5 |
25217 |
4.8 |
59039 |
3.8 |
|
寧夏自治区 |
19 |
14477 |
16.7 |
3439 |
17.3 |
3590 |
29.8 |
|
新疆自治区 |
107 |
125822 |
32.2 |
16788 |
-0.2 |
91242 |
35.3 |
(5) 情報セキュリティ
工業・情報化部が2008年1月に公布した「ソフトウェア産業『第11次5ヵ年』専門規画」(「軟件産業"十一五"専項規劃」)では、情報セキュリティ分野の先端製品とソフトウェア製品を研究、制作し、自主的に制御可能な情報セキュリティ保障体系を構築するという方針が打ち出されている。
また、国家質量(品質)監督検験検疫総局と国家認証認可監督管理委員会が2008年1月に公布した「一部の情報セキュリティ製品に対する強制的認証の実施に関する公告」に従い、通信安全や身元鑑定、データ安全、評価審査・監視・制御などの分野に加え、ファイアウォールやルータ安全、スパムメール対策製品などの情報セキュリティ製品に対して2009年5月1日から強制的認証を実施することになった。
さらに国家発展改革委員会は2008年11月14日、教育部、工業・情報化部、中国科学院、国家暗号管理局、各省の発展改革委員会に対して、「2009年情報セキュリティ特定事業の実施取組みの関連事項に関する国家発展改革委員会弁公庁の通知」を出した。
この通知では、2009年の情報セキュリティ分野の特定事業と重点分野が以下のようにあげられている。
① 情報セキュリティ製品の産業化
- 国産の信頼できるチップをベースとした安全応用製品、自主的暗号技術に基づいた高機能応用製品の産業化
- 可搬型保存媒体秘密保守管理、悪意のあるコードの防止、電子ファイルの安全管理などのコンピュータセキュリティ保護製品および無線ネットワークの安全管理・応用製品の産業化
- 安全操作システム、安全データベース、安全サーバー、安全接続設備、安全保存、安全オフィスソフトウェアなどの製品の産業化
- 高機能専用安全チップと専用安全設備のハード・ソフトウェア集約化製品の産業化
② 情報セキュリティ専門サービスの提供
- 国家重要インフラ施設、金融、電力、交通などの重要な情報システムに対する緊急時対応
- 国家情報セキュリティ監督管理政策の安全評価と計算のサポート
- 情報セキュリティ事件に関する情報の開示、コンサルティング
- 情報システム安全監視・管理の委託管理サービス
③ セキュリティ標準体系の研究(情報セキュリティ等級保護、リスク評価、秘密情報システムなど)
- 国家電子政務の構築に関する安全基準体系
- 重要情報セキュリティ製品の中核基準
④ 自主開発の情報化設備を採用した情報システムモデル事業
- 電子政務、銀行、証券、発電所、電力網などの重要な分野において、自主的に開発した情報化設備の採用を重点的にサポートし、安全等級保護要求に従って構築された情報システムモデル事業
なお、米マイクロソフト社が資本参加する大手ITアウトソーシングサービス企業である浪潮集団の孫丕恕・総裁は2009年3月、中国では情報セキュリティリスクが至る所に存在するとしたうえで、コンピュータシステムがウイルスに感染し破壊される状況も深刻になっており、経済や政治的意図を持った事件が増加しているとの懸念を表明した。
また同氏は、中国の情報セキュリティシステムは米国やロシア、イスラエルなどの情報セキュリティ強国はもちろん、インドや韓国よりも遅れているとの認識を示した。
一方、情報セキュリティ国家重点実験室は2008年6月、以下の分野で国際的な水準にある研究成果が得られたと発表している。
- 暗号関数、置換暗号、マトリックス認証
- ハッシュ関数、パブリックキー
- PKIシステム
- 大型脆弱性データベースの構築
こうしたなかで浪潮集団は2008年5月、中国初の自主的財産権を持つ安全サーバーの販売を開始している。このサーバーは、サーバー安全増強システム(SSR)を採用し、強制的アクセス制御などの機能を搭載し、新しいウイルスの侵入を防止することもできる。現在、このサーバーは国内の公安や銀行、税務、油田、電力などの多くの分野で利用されている。
また、北京東方微点信息技術公司が開発した主導的防御ソフトウェアは北京オリンピックで採用された。このソフトウェアは、「863計画」の下で開発されたもので、自主的にウイルスを分析・判断する機能を備え、ワクチンソフトで発見、駆除できないTrojan Horseやウイルスを防御することができる。
(6) ネットワーク
1)インターネット
中国インターネット情報センター(中国互聯網信息中心=CNNIC)が2009年1月に発表した「中国インターネット発展状況統計報告」(「中国互聯網絡発展状況統報告」)によると、中国のインターネット利用者数は対前年比で41.9%の高い伸びを示し、2008年12月31日時点で2億9800万人に達した。
また、普及率も22.6%に達し、初めて世界平均の21.9%を上回ったことが明らかになった。インターネットの主な使用目的には、求人の検索やブログの更新、インターネットショッピングなどがあがっている。
主な国のインターネット普及率を見ると、日本73.8%、米国72.5%、韓国70.7%、ブラジル26.1%、ロシア23.2%、インド5.2%などとなっている。2000年から2008年にかけてのインターネット利用者数の推移を図3.1に示す。
図3.1 中国のインターネット利用者数の推移
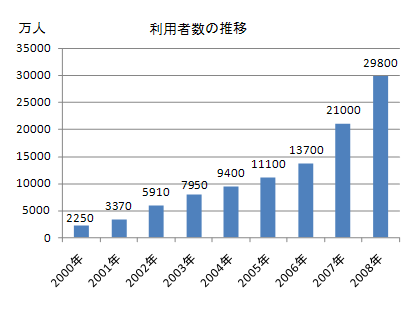
出典:「中国互聯網網絡発展状況統報告」(中国互聯網信息中心、2009年1月)
インターネット接続形態を見ると、ブロードバンドの普及率がめざましく、ブロードバンドユーザー数が2.7億人に達し、全体の90.6%を占めた。このほか、モバイルネット利用者が1億1760万人となり、2007年から133%の増加を示した。農村インターネット利用者も8460万人を記録し、前年から60.8%増加した。
インターネット利用者を地域別に見ると、西部地域の増加率が高く、増加率が60%以上を記録した天津市、河北省、重慶市、貴州省、雲南省、青海省、寧夏自治区、新疆自治区のうち6地域が西部にある。
2008年末時点での普及率は、大都市部が高く、北京市が60%でトップ、これに上海市の59.7%、広東省48.2%、天津市43.5%、浙江省41.7%などが続いている。
|
|
2007年末 |
2008年末 |
増加率 |
||
|
地域名 |
インターネット |
普及率(%) |
インターネット |
普及率(%) |
|
|
全国 |
21000 |
15.9 |
29800 |
22.6 |
41.9 |
|
北京 |
737 |
46.6 |
980 |
60.0 |
32.9 |
|
天津 |
287 |
26.7 |
485 |
43.5 |
69.1 |
|
河北 |
762 |
11.1 |
1334 |
19.2 |
75.0 |
|
山西 |
536 |
15.9 |
819 |
24.1 |
52.8 |
|
内モンゴル |
322 |
13.4 |
385 |
16.0 |
19.7 |
|
遼寧 |
783 |
18.3 |
1138 |
26.5 |
45.3 |
|
吉林 |
434 |
15.9 |
520 |
19.0 |
19.8 |
|
黒龍江 |
476 |
12.5 |
620 |
16.2 |
30.2 |
|
上海 |
830 |
45.8 |
1110 |
59.7 |
33.7 |
|
江蘇 |
1757 |
23.3 |
2084 |
27.3 |
18.6 |
|
浙江 |
1509 |
30.3 |
2108 |
41.7 |
39.7 |
|
安徽 |
587 |
9.6 |
723 |
11.8 |
23.1 |
|
福建 |
866 |
24.3 |
1379 |
38.5 |
59.3 |
|
江西 |
511 |
11.8 |
610 |
14.0 |
19.5 |
|
山東 |
1256 |
13.5 |
1983 |
21.2 |
57.9 |
|
河南 |
956 |
10.2 |
1283 |
13.7 |
34.2 |
|
湖北 |
706 |
12.4 |
1050 |
18.4 |
48.7 |
|
湖南 |
690 |
10.9 |
999 |
15.7 |
44.7 |
|
広東 |
3344 |
35.9 |
4554 |
48.2 |
36.2 |
|
広西 |
560 |
11.9 |
734 |
15.4 |
31.1 |
|
海南 |
144 |
17.2 |
216 |
25.6 |
49.9 |
|
重慶 |
356 |
12.7 |
598 |
21.2 |
67.9 |
|
四川 |
809 |
9.9 |
1103 |
13.6 |
36.4 |
|
貴州 |
224 |
6.0 |
433 |
11.5 |
93.4 |
|
雲南 |
303 |
6.8 |
548 |
12.1 |
81.0 |
|
チベット |
36 |
12.7 |
47 |
16.4 |
29.5 |
|
広西 |
517 |
13.9 |
790 |
21.1 |
52.8 |
|
甘粛 |
219 |
8.4 |
327 |
12.5 |
49.5 |
|
青海 |
60 |
11.0 |
130 |
23.6 |
117.4 |
|
寧夏 |
61 |
10.1 |
102 |
16.6 |
66.4 |
|
新疆 |
363 |
17.7 |
625 |
27.1 |
72.1 |
インターネットの利用状況を各接続機器別に見ると、デスクトップパソコンでの利用率が高くなっており89.4%、以下、携帯電話39.5%、ノートパソコン27.8%などとなっている。
CNNICは、第3世代移動通信(3G)がスタートして以来、3G技術のネットワークが成熟しつつあることから、2009年以降、携帯電話によるインターネットの利用がさらに増加すると予測している。
図3.2 各接続機器別に見たインターネットの利用状況
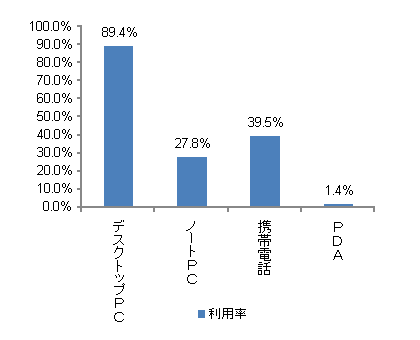
出典:「中国互聯網絡発展状況統報告」(中国互聯網信息中心、2009年1月
インターネットの普及が都市部と農村部の格差縮小につながるとの期待もある。近年の農村部でのインターネット利用率拡大の背景には、環境整備が急速に進んだこともあるが、農業がインターネット経済を支える新たな成長分野になるとの見方も出てきている。
検索サイト「百度」の李彦宏CEOは2009年3月10日、農林・牧畜・漁業から百度が得た収入が昨年第4四半期に前年同期に比べて3倍以上になったことを明らかにした。「人民網日本語版」が伝えた。
同氏によると、金融危機による経済減速は、インターネット企業の収入に影響を及ぼしているものの、農林・牧畜・漁業分野からの収入は力強い成長を見せているという。同氏は、ネーブルオレンジの過剰が深刻な湖北省シ帰県を具体的な事例としてあげている。
それによると、同県のネーブルオレンジと関連したキーワードが検索エンジンにヒットするようにしたところ、百度による2ヵ月に及ぶ宣伝によって、同県のネーブルオレンジの販売量は前年同期より30%以上増えたという。
インターネットバンキングの利用率も、顕著な増加を示している。中国銀行業協会が2009年3月14日に公表した「2008年度銀行業サービス改善状況報告」(「2008年度銀行業改進服務情況報告」)によると、2008年末時点のインターネットバンキングの利用者は、前年より52.8%増加し1億4815万に達した。取引金額は301兆8000億元を記録した。
こうしたなかで中国政府は、次世代インターネットの発展をさらに推進する意向を占めている。国家発展改革委員会の張暁強・副主任は2008年12月3日、次世代インターネットを重視する必要があるとしたうえで、「第12次5ヵ年」期(2011~2015年)の発展規画を検討し、国際的な次世代インターネットの競争において戦略的に有利な位置を占めると同時に関連分野の発展を実現する必要があると語った。
同氏によると、中国はこの5年間に30億元以上を投入し、6つの主要ネットと2ヵ所のアクセスポイントを含む次世代インターネットのモデルネットを構築した。全国の30都市以上をカバーし、ユーザーは100万人を超えている。このうち、清華大学を含めた25の大学は世界規模の次世代通信プロトコル「IPv6」インターネットを構築しており、「中国は次世代インターネットをリードしている」(張副主任)という。
2)モバイル通信
工業・情報化部の集計によると、中国の移動電話ユーザー数は2007年から9392万増加し2008年末時点で6億4123万に達した。これに対して、固定電話のユーザーは、前年から2483万減少し3億4080万になった。
こうしたなかで、工業・情報化部は2009年1月7日、中国移動通信集団公司(チャイナ・モバイル)、中国電信集団公司(チャイナ・テレコム)、中国聯合網絡通信集団公司(チャイナ・ユニコム)の3社に対して、第3世代(3G)携帯電話事業の免許を交付した。
チャイナ・モバイルは、中国が独自に開発した「TD-SCDMA」方式、チャイナ・テレコムは米国が開発した「CDMA2000」方式、チャイナ・ユニコムは欧州が開発した「WCDMA」方式の免許をそれぞれ取得した。中国の独自技術である「TD-SCDMA」が実用化水準に達したことを受け、同時に免許を交付したと見られている。
第3世代は、従来の携帯電話技術と比べてデータ輸送のスピードが大幅に向上しており、画像や音楽、動画などのマルチメディアのファイルを手軽に扱えるだけでなく、インターネットや電子商取引などのサービスを自由に利用できる。
3G携帯電話の許可を取得したチャイナ・テレコムは2009年2月8日、農村部における携帯電話の普及をねらった「手機下郷」活動を本格的に開始したことを明らかにした。全国の農民ユーザーが同社のCDMA方式の携帯電話端末を購入し、ネットワークに加入した場合には優遇措置の適用対象となり、端末機購入代金の13%が政府から補助されるほか、一定の通話料補助も受けられる。このほか、固定電話、ブロードバンド、モバイル業務をセットにした優遇サービスも受けることができるという。
さらに同社は2009年3月15日、上海で3G移動通信規格の商用化テストを開始した。4月には全国規模で業務をスタートし、Wi-Fi携帯電話の販売も開始する予定と見られている。
中国のモバイルテレビ標準規格である「CMMB」(China Multimedia Mobile Broadcasting)方式でのモバイルテレビ放送が2009年3月16日、上海で正式にスタートした。中広衛星移動広播有限公司と上海文広手機電視有限公司が携帯端末向けテレビ放送契約を結んだことを受けたもの。
中国が独自に開発したCMMB方式では、携帯電話やMP4、GPSなどの7インチ以下の小型ディスプレイ向けテレビ放送が可能で、上海市では、CMMBサービス対応の端末機を使えば、時間や場所の制約を受けずにテレビの視聴ができる。
なお、工業・情報化部の李毅中・部長は2008年12月19日、2009年と2010年の2年間における3Gネットワークへの投資額が2800億元に達する見通しであることを明らかにしている。
(7) ロボティクス
中国のロボティクス技術開発は、まだ発展途上にあるが、欧米や日本から帰国した研究者が質の高い研究を行っており、将来、急速にキャッチアップしてくると見られている。
中国自動化学会ロボット競技委員会主任を務める清華大学の孫増圻教授は、中国のロボット研究はすでに先進国と遜色ないレベルまで上がってきているとする一方で、応用面ではまだだいぶ遅れているとの見方を示している。
中国のロボット研究は、2000年11月29日に国防科学技術大学が発表した人間型ロボット「先行者」によって大きな関心を集めた。1990年に開発した二足歩行ロボットと比べて、段差のある場所を自由自在に歩行できるほか、歩行速度もそれまで6秒間に1歩だったものが1秒間に2歩までスピードアップした。
北京理工大学では2002年12月28日、人間型ロボットが「国家ハイテク研究開発発展計画」(「863計画」)の検査に合格した。このロボットは、高さ158cm、重量76kgで、33cmの歩幅で1時間に1kmの走行が可能であった。
その後、改良が進められ、中国科学院が2008年10月に明らかにしたところによると、中国企業が独自に開発した人間型ロボットが瀋陽市行政審査サービスセンターの窓口案内係りに登用された。
このロボットは身長160cm、体重50kgで、手足は自由に動き、自由自在に歩くことも可能という。また、自力で障害物を避けることができる。無線による遠隔操作が可能で、中国語での音声案内のほか、胸元のスクリーンのタッチパネルで訪問者に情報の提供ができる。
2008年1月7日付「科学時報」は、瀋陽新松ロボット(机器人)股份有限公司の研究所が自主的知識財産権を持つ「研磨ロボットシステム」の研究開発に成功したと伝えている。このシステムは、鋳型や翼板など、多数の部品の加工・修復作業に利用可能という。
中国は、極限環境下で用いられるロボット開発にとくに力を入れている。「863計画」の海洋技術重要課題の1つとして、中国科学院瀋陽自動化研究所等が共同開発した水中ロボット「北極ARV」が2008年9月中旬、北緯84度の海氷下で調査を行った。
中国科学院によると、中国が高緯度海域で水中ロボットを用いて実施した初めての調査で、各種計器を装着して海底の状態や氷の厚さ、水深別の海水温度や塩分濃度の測定が行われた。
また国家海洋局の孫志耀・局長は2009年3月9日、中国が自主研究・開発した水深7000mの水圧に耐えられる世界初の水中ロボットが2009年内に海中実験を開始する計画であることを明らかにした。同局長によると、この水中ロボットは定員3人で、組立作業はすでに完了している。
中国は、宇宙開発におけるロボット利用も積極的に進めようとしている。中国工程院の蔡鶴皐・院士は2008年10月、中国が2011年の打ち上げを予定している衛星に搭載するロボットアームを公表した。
母衛星に取り付けられたロボットアームは、小型衛星を掴んで宇宙空間に放出したあと追跡し、再び回収するという。ロボットアームの開発は現在、ハルビン工業大学で進められている。
主要参考文献:
- 「中国科技統計年鑑」(2002~2007各年版、国家統計局・科学技術部編、中国統計出版社)
- 「国家中長期科学和技術発展規劃綱要(2006-2020年)」(国務院、2006年2月)
- 「国家"十一五"科学技術発展規劃」(科学技術部、2006年10月)
- 「高技術産業発展"十一五"規劃」(国家発展改革委員会、2007年4月)
- 「集成電路産業"十一五"専項規劃」(工業・情報化部、2008年1月)
- 「軟件産業"十一五"専項規劃」(同上)
- 「電子基礎材料和関鍵元器件"十一五"専項規劃」(同上)
- 「電子専用設備和儀器"十一五"専項規劃」(同上)
- 「信息技術改造提升伝統産業"十一五"専項規劃」(同上)
- 「中国互聯網絡発展状況統計報告」(中国互聯網絡信息中心、2009年1月)
主要関連ウェブサイト: