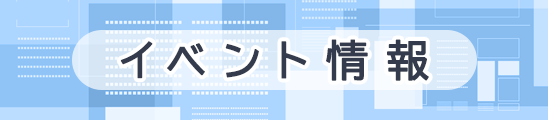フィールドワークからライフサイエンスまで
2011年 2月24日

伊谷 原一(いだに げんいち):
京都大学野生動物研究センター教授、センター長
1957年10月生まれ。1984年 酪農学園大学酪農学研究科修士過程修了・農学修士
1991年 京都大学理学博士(論理博)。
社会活動:日本霊長類学会評議員、ヒトと動物の関係学会常任理事(編集委員長)、岡山県自然環境保全審議会委員、大型類人猿保全日本委員会理事、アフリカ/アジアの大型類人猿を支援する集い世話役代表、京都水族館専門家委員
主な編著:
- アフリカを知る辞典(共著)・平凡社
- サルの文化誌(共著)・平凡社
- アフリカを歩く(共著)・以文社
- 文化から探るチンパンジー社会(訳書)、日系サイエンス・日本経済新聞社
- 原野と森の思考(共編)・岩波書店
- 伊谷純一郎著作集第1~6巻(共編)・平凡社
1.はじめに
京都大学にはパイオニア精神を尊重する伝統がある。今から半世紀以上も前の1958年、今西錦司、桑原武雄、西堀栄三郎のそれぞれが隊長となり、アフリカ探検、ヒマラヤ登頂、南極越冬という、いずれもが初となる大きな冒険的調査が行われた。以来、京都大学は「フィールドワークに根ざした知の学統」を受け継いできたのである。とくに、今西錦司によるアフリカでのゴリラ調査は、やがてチンパンジー、ボノボ、オランウータンという大型類人猿の新たなパイオニアワークを生み出しただけでなく、アジア、アフリカ、中南米に生息する多種多様な霊長類を対象にした研究へと発展してきた。1948年にニホンザルのフィールド研究に始まった日本の霊長類学は、国内外での多彩な研究を加え、常に世界の第一線をリードしてきたのである。
その一方で、霊長類以外の野生動物の研究に関しては、京都大学に限らず日本全体でみても進展しているとは言い難い。また、野生動物の相次ぐ絶滅が危惧される昨今、野生動物研究に着手することは火急の課題であった。そうした中、2008年4月1日、京都大学に野生動物研究センター(WRC)が新しい部局として設立された。同研究センターは、日本が霊長類研究で培ってきたフィールドワークの経験と実績を他の野生動物の研究に活かすとともに、最新のライフサイエンス等の多様な研究を統合して、新たな学問領域の創成を目指している。本報では、WRCの研究内容や今後の展望について紹介したい。
2.多彩なフィールドワーク
WRCは、世界自然遺産に登録された鹿児島県・屋久島と、国の天然記念物に指定されている宮崎県・幸島にフィールドステーションを所有している。これらの施設では、半世紀以上に及ぶ野生ニホンザルの研究を継続しつつ、シカやコウモリなどの哺乳類、鳥類、昆虫といった日本の固有種を対象にした調査が行われている(写真1)。多様な生物に焦点を当てることで、それぞれの特性を浮き彫りにするとともに、生息環境の全体像を把握し、適切な保全方針を構築することが可能となるだろう。屋久島と幸島のフィールドステーションは、より多様な研究ニーズに対応していくために施設整備も進めている。また、国内では伊豆諸島御蔵島、小笠原諸島、天草下島初等などの海域におけるミナミハンドウイルカの音声や行動生態学的研究も行っている。

写真1.宮崎県幸島の「イモ洗い行動」をするサル ©G.Idani
一方、海外でのフィールドワークにも力を入れている。まずはタンザニア西部、タンガニイカ湖畔にあるマハレ山塊国立公園でのチンパンジー研究があげられる(写真2)。マハレ山塊は1985年に日本の協力によって同国11番目の国立公園に指定されたが、京都大学を中心とする研究グループが同地でチンパンジー研究を開始したのは1965年である。以来、45年に及ぶ長期継続研究によって、チンパンジーの生態や行動、高度なコミュニケーション、社会構造などが解明されてきた。現在、マハレ山塊での研究の主たる運営はWRCが担っており、国内外から多くの研究者を受け入れている。

写真2.タンザニア・マハレ山塊国立公園のチンパンジーの挨拶行動 ©M.Nakamura
同じタンザニア西部のウガラ地域に広がるミオンボ疎開林帯は、アフリカのチンパンジー分布域の東限に当たる。ここでは近年、サバンナゾウ、キリン、ハイラックス、猛禽類などを対象にした研究がはじまっている(写真3)。同地域は年間降雨量が1,000mm以下の乾燥帯という過酷な環境であるが、初期人類誕生の環境に類似している点が指摘されている。同地における多様な野生動物や植生に関する研究は、初期人類の生活環境を復元していく上で重要なものとなるだろう。ウガラ地域のングエ谷には、2010年9月に小さいながらもフィールドステーションが設立され、今後の研究の発展が期待されている。

写真3.タンザニア・ウガラの乾燥疎開林帯に生息するブッシュハイラックス ©E.Iida
コンゴ民主共和国(旧ザイール)・赤道州ワンバ森林でのボノボの研究も特筆すべきものだろう(写真4)。野生のボノボは世界中でもコンゴの熱帯雨林にしか生息していない希少かつ絶滅危惧種である。同地での研究が日本の研究グループによって開始されたのは1973年であったが、以降、ボノボの特異的な性行動、父系母権の社会構造、平和的な集団間関係など、それまで完全にベールに包まれていたそのユニークな社会が次々に明らかにされてきた。ワンバ森林は、1990年に日本の研究者の努力によって「ルオー学術保護区」となったが、1991年に同国全域で同時多発した暴動、および1996年から2002年の内戦によって調査は完全に中断した。この戦争によってボノボはその生息数を激減させたが、ルオー学術保護区での調査は2003年から再開され現在も継続されている。同保護区ではボノボ以外の森林性動物もその数を減少させつつあり、それらを対象にした研究の着手はWRCにとっての急務となる。

写真4.コンゴ民主共和国・ルオー保護区ワンバ森林のボノボ ©G.Idani
2010年2月、ボルネオ島北部(マレーシア領)サバ州のダナンバレイ森林保護区に、現地サバ財団とサバ大学熱帯生物保全研究所の協力により、WRCのフィールドステーションが設立された(写真5)。同地は低地混合フタバガキ林からなる熱帯雨林で、テングザル、ボルネオゾウ、スマトラサイをはじめ哺乳類125種、鳥類275種、爬虫類72種、両生類56種などが生息し、野生動物研究において高いポテンシャルを有している。ここでは2004年以来、日本人研究者によって主にオランウータンの生態学的調査が行われてきたが、今後はより多様な野生動物の研究へと発展していくだろう。なお、同じボルネオのカビリ-セピロク森林保護区やタビン野生生物保護区では、すでにヤマアラシやジャコウネコの調査に着手している。

写真5.ボルネオ島サバ州(マレーシア)・ダナムバレー保護区にある野生動物研究センターのフィールドステーション ©G.Idani
熱帯地域だけでなく、寒冷地帯も野生動物研究のフィールドなる。チベット、ヒマラヤ、アラスカ、パタゴニアなどの氷河には、氷の世界に生息する昆虫やミミズなどさまざまな生物が生存し、特異な氷河生態系が成立していることが明らかにされた(写真6)。つまり、無生物的環境と考えられてきた氷河に、定常的な生態系の存在が証明されたのである。現在、氷河生態系の変化やそれが地球的規模の環境変動に及ぼす影響、さらにはアイスコア(柱状氷試料)解析による古環境の復元などの研究が進められている。
その他、海外ではタイやインドでのアジアゾウ、インドのドール、ガンジスカワイルカ、ブラジルのアマゾンカワイルカ、チリのイロワケイルカなど、熱帯林から氷河までのさまざまな環境で、陸・海・空の多様な野生動物のフィールド研究を推進している。

写真6.パタゴニアの氷河に生息する無翅カワゲラ ©S.Kohshima
3.動物園との連携と飼育下野生動物の研究
野生動物を研究するためには、その生息地に出かけていく必要がある。しかし、野生動物は非常に警戒心が強い上に俊敏で、実際に野生環境で彼らを研究することは困難を極める。さらに、活発な人間活動によって多くの野生動物が絶滅の危機に瀕している昨今では、フィールドで彼らを発見することすら不可能な場合が多い。ところが、絶滅危急種かつ希少種であるはずの彼らとは私たちのすぐ身近にある動物園で容易に出会うことができる。しかし、これまで動物園での本格的な研究は少なく、そのほとんどは大学の研究者や動物園の一部のスタッフが個人的なレベルで細々と続けてきたものである。
WRCは、設立とほぼ同時に民間企業である(株)三和化学研究所が熊本県宇城市に所有するチンパンジー・サンクチュアリ・宇土(CSU)に寄附研究部門を開設し、筆者がその初代研究所長(兼任)に就任した。当時CSUは、日本全体で飼育されていたチンパンジー約340頭のうち、その5分の1強に当たる日本最大の76頭を所有していた。ここでは、チンパンジーを通じて人間理解を深めるための認知科学、動物福祉、健康長寿などの研究が行われている。
CSUの寄附研究部門設置と並行する形で、京都大学はWRC、京都市動物園、及び名古屋市東山動植物園を核とする連携協定を、京都市、名古屋市のそれぞれと締結した。続いて、2009年にはWRCがよこはま動物園ズーラシア、名古屋港水族館と、そして2010年に京都大学と熊本市がやはりWRCと熊本市動植物園とを核とする連携締結にこぎつけた。
WRCが最初に取り組んだのは、CSUを通じてのチンパンジーの飼育、環境改善、健康管理などの技術提供である。CSUは30年以上に及ぶチンパンジー飼育経験によって、高度な飼育技術と健康管理技術を有している。それらの内容をプログラム化することで、日本各地の動物園スタッフを集めて研修を行っている。続いて、各園が展示動物として必要とするチンパンジーそのものの提供にも着手した。これまでに、連携する動物園は勿論のこと、中四国を中心に複数の動物園にチンパンジーを譲渡、あるいはBL(breeding loan)提供し、2011年1月現在、CSUが保有するチンパンジー数は59頭になっている。今後もチンパンジーの提供は、譲渡先施設でのチンパンジーの健全な生活が保証されるのであれば、可能なかぎり継続していく予定である。さらには、動物園間の個体移動に関しても、血統関係や将来展望などを吟味しながら支援していきたいと考えている。
WRCと動物園・水族館との良好な関係形成に伴い、野生でのフィールド研究だけでなく、飼育下においても新たな野生動物研究に展望が開けた。飼育下の有利な点は、野生ではとうてい不可能な至近距離から対象動物を観察でき、コンピューターや実験装置などの設備を導入することで、よりユニークな実験研究が行えることである。WRC発足以来、京都市動物園にはWRCの教員が常駐し、霊長類を対象とした認知実験研究を行っている(写真7)。また、WRCの依頼を受けた京都大学霊長類研究所の教員と学生が名古屋の東山動物園に出向し、定期的に実験研究を進めている。さらに、2009年に完成したよこはま動物園ズーラシアや2011年3月に竣工予定の熊本市動物園のチンパンジー展示施設には、チンパンジーの提供だけでなく、展示施設の建設や飼育技術に関するさまざまな指導を行っている。

写真7.京都市動物園におけるチンパンジーの認知科学実験 ©WRC
各地の動物園ではチンパンジーだけでなく、ゴリラ、テナガザル、マンドリル、フサオマキザル、ゾウ、キリン、オオカミ、ハイラックス、ヤマアラシ、ヤブイヌ、ドール、バク、ツシマヤマネコなどの生態や行動に関する基礎研究が行われており、水族館でもイルカやシャチの音声コミュニケーション研究が進められている。これらの種の多くは、野生において絶滅危惧種あるいは絶滅危急種に相当する上に、飼育下での繁殖や個体数の維持が困難なものも多いことから、現段階でできる限り多くの基礎資料を収集しておく必要がある。
4.ゲノム研究
近年の遺伝子研究の発達に伴い、野生動物の生態や行動の研究にゲノム情報を活用する方法が確立されつつある。WRCでは、フィールド調査や動物園での観察などで得られる試料、つまり動物の糞や毛、口内細胞などからDNAを抽出し、その動物の種類、性別、血縁関係、分布や密度などを追跡している(写真8)。また、個体の性格や行動に影響する機能遺伝子などの解析も行っている。

写真8.愛媛県立とべ動物園におけるアジアゾウの口内細胞採取 ©S.Yasui
現在取り組んでいる大きなテーマの1つに、DNA Zoo構想がある。これは、できるだけ多様な種類、かつ数多くの個体のDNA試料からなるデータベースの構築である。家畜や実験動物では全ゲノム配列が解明されつつあるが、野生動物のゲノム情報はほとんど解明されていない。そこには野生動物の保全や飼育動物の福祉だけでなく、私たち人類に有用な情報や特性が記されている可能性がある。地球上で確認されている生物は約175万種であるが、そのうち哺乳類は約5,500種、鳥類は約10,000種を占めるにすぎない。そして、そのうちの約20%が絶滅の危機に瀕しており、やがてはそれらの動物自体が消滅してしまう危険性が高いのである。そうした動物たちが生存している間に、その貴重な遺伝資源をDNA試料として蓄積していくことが急務となる。現在、WRCには約200種、17,000個体以上が登録されているが、今後さらに種・個体数ともに増やしていく必要がある。
ゲノム上に存在するマイクロサテライトは2~7塩基からなる配列が2~数十回反復するもので、この回数には個体差がある。また、ミトコンドリアDNAは核DNAよりも塩基置換の起こる速度が5~10倍早いとされる。これらの遺伝マーカーを分析することで、野生動物の遺伝的多様性、個体識別、血縁関係、系統関係などを解明することができる。たとえば、複雄複雌の集団で生活する霊長類の多くは、乱婚の上に子育てをするのはメスだけであるため、観察だけではどのオスが父親であるかは分からない。しかし、遺伝マーカー用いることによって父親を判定することが可能となる。これまでに、ニホンザルの父子判定が行われ、どんなオスが繁殖に関わっているのか、また交尾回数や群れ内の順位と子どもの数に相関関係がないことなどが明らかにされてきた。最近では、イヌワシの遺伝的多様性を調べることで、その生態の解明や保全のための調査も行っている。
動物の行動や性格の形成には、環境要因だけでなく遺伝要因も大きく影響している。言い換えれば、行動や性格に関連する遺伝子が存在するのである。たとえば、中枢神経系の神経伝達物質であるドーパミンD4受容体にはアミノ酸16個を単位とする反復配列があり、反復数が多く長いタイプの遺伝子をもつと、好奇心が強い傾向にあるとされている。この遺伝子をさまざまな霊長類で比較したところ、人に近縁の種ほど長いタイプが多く、好奇心が強いことが明らかになった。また、やはり神経伝達物質であるセロトニンの伝達に関係するセレトニントランスポーター遺伝子は不安遺伝子とも呼ばれ、これが短い(SS型)と不安を感じやすいとされる。この遺伝子は、ヒトでは他の霊長類よりも短くなっていた。また、人種間の比較では日本人はSS型が圧倒的に多いのに対し、アメリカ人のSS型は20%以下という結果が出ている。すなわち、日本人は不安を感じやすく用心深い性格のサルなのかもしれない。こうした機能遺伝子の分析は、ゾウの性格判定やオオカミの行動特性の研究で活用されているほか、麻薬探知犬や伴侶犬といった人のために働くイヌの性格判定にも応用されている。
ゲノム研究では、ドイツのライプニッツ野生動物研究所やイタリアの国立環境保全研究所との研究協力を推進しており、さらにはガーナ大学農業消費科学部との共同研究や若手研究者の育成といった研究交流にも繋がっている。
これまで述べてきたように、京都大学野生動物研究センターは京都大学が培ってきたフィールドワークの伝統を活かしつつ、最新のライフサイエンスの手法も取り入れて、野生動物の生息地における実践研究と、生息域外での保全研究を推進している。これらを通じて、京都大学の理念である「地球社会の調和ある共存に貢献する」ことを目的とし、将来的には野生動物保全学、動物園科学、自然学といった新たな学問領域の創成を目指していきたい。
主要参考文献:
- 生きものたちのつづれ織り第三巻、京都大がグローバルCOEプログラム:生物の多様性と真価研究のための拠点形成-ゲノムから生態系まで-(2010年2月)






 インドのスタートアップ・エコシステムとディープテック・スタートアップ振興策(2025年3月)
インドのスタートアップ・エコシステムとディープテック・スタートアップ振興策(2025年3月)