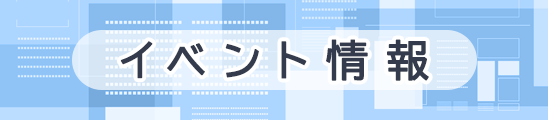【23-53】岐路に立つ中国のイノベーション、日中両国の科学技術協力の可能性
2023年08月17日

柯 隆:東京財団政策研究所 主席研究員
略歴
1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年同大卒業。94年名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。
長銀総合研究所国際調査部研究員、富士通総研経済研究所主任研究員、同主席研究員を経て、2018年より現職。静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授。
主な著書に『中国「強国復権」の条件』(慶応大学出版会、第13回樫山純三賞受賞)、
『ネオ・チャイナリスク研究』(慶応大学出版会)。
中国の習近平政権は正式には2013年3月に発足した。習政権は強国復権の中国の夢を人々に呼び掛けているが、それを実現しようとする最初の戦略は「中国製造2025」の計画だった。すなわち、2025年までに中国を半導体などハイテク製造業の強国にする考えだった。この計画を支えるもう一つの計画は「千人計画」と呼ばれる最先端科学者と技術者を海外からリクルートするものである。
習政権のアグレッシブな強国復権戦略を受けて、海外では、中国はそう遠くないうちに、アメリカを追い抜いて世界一の強国になるのではないかと多くの評論家が予想していた。もっとも楽観的なものでは、2028年までに中国の名目GDPはアメリカを追い抜いて世界一になる可能性があるというものである。さらに、中国国内の一部の研究者は、中国は科学技術の分野ですでにアメリカを凌駕していると豪語していた。もともと習政権が誕生する前から、海外の評論家の一部からは、21世紀は中国の世紀であるといわれていた。
想定外の米国の制裁と長引く影響
今から振り返れば、中国の経済基盤と産業技術基盤をもとに考えれば、中国がアメリカを凌駕できるかどうかは別として、地道に努力すれば、中付加価値の産業技術力を強化し、ハイテク技術の一部について世界をリードすることは不可能ではなかった。しかし、急がば回れといわれるように、「中国製造2025」の計画は間違いなくアメリカ政府を刺激してしまった。これは習政権の誤算といえよう。
2018年、トランプ政権(当時)は米中貿易不均衡を理由に中国からの輸入に対する制裁関税を課した。それだけでなく、中国のハイテク企業ZTEやファーウェイ技術に対する制裁が実施され、米中対立は一気に深刻化してしまった。ビジネスの観点からみれば、中国にとってアメリカは最大の輸出相手国である。すなわち、もっとも重要な得意先である。得意先に失礼なことをいわれても、ぐっと我慢して、笑顔をみせるのは商売のコツである。
しかし、習政権はトランプ政権の制裁措置に対して、やられたら必ずやり返す、歯には歯を、と応酬した。このやり方はのちに「戦狼外交」と名付けられた。わかりやすくいえば、習政権は商売が下手といわざるを得ない。
習政権の前の江沢民政権(1992-2002年)と胡錦濤政権(2003-12年)のとき、対米関係について問題がなかったわけではないが、その都度、対話して問題の深刻化を回避してきた。しかし、習政権とアメリカ政府との対立は一向に下火にならない。それよりも、アメリカの対中制裁は日増しに拡大し、厳しくなっている。気が付けば、習政権はアメリカと対立しているだけでなく、G7のほとんどの国と関係が悪化している。
長い間、中国の対アメリカ戦略はウォール街のビジネスリーダーを囲んで、彼らを通じて、アメリカ政府と議会に圧力をかけるものだった。ウォール街のビジネスリーダーはそれぞれの会社の利益を最大化しようとして、中国政府の要請に答え、米国議会とホワイトハウスにロビー活動を展開していた。しかし、「戦狼外交」によってアメリカの対中国民感情は予想以上に悪化してしまった。この風向きの変化を北京は十分に感知していないようだ。もう一つの可能性は、中国では民主主義の選挙が実施されていないため、北京はアメリカの民意を軽く見すぎたかもしれない。しかし、ホワイトハウスも米国議会も民意を軽くみることができない。しかも、アメリカ人の対中国民感情が悪化してしまって、改善するのに、予想以上に時間がかかっている。
中国の科学技術の実力と「中国製造2025」に代わる新たな計画
では、中国は科学技術の強国になれるのだろうか。米中対立がなければ、中国は地道に努力していずれ科学技術の強国になれる可能性があった。しかし、米中が対立し、中国に対する科学技術の包囲網ができてしまった。この包囲網こそ中国が科学技術強国になる妨げになっている。
2018年当時の米中対立は貿易摩擦だった。今、半導体戦争に発展してしまった。しかも、経済安全保障枠組み(IPEF)ができつつあり、これは中国のイノベーションを抑止するための強力な枠組みである。それを受けて、習政権は国内に向けて、自力更生によるイノベーションの強化を呼び掛けている。中国政府は巨額の研究費を投じて、中国発の半導体チップの開発・生産を試みている。しかし、昔と違って、今のイノベーションはすべてオープンイノベーションであり、クローズドな環境のなかで、半導体のような技術と製品を開発することができない。とくに、半導体製造装置は、アメリカ、日本とオランダの企業が寡占しているため、それを手に入れることができなければ、中国企業だけでは、何もできない。
トランプ政権の猛烈な制裁を受けて、習政権は「中国製造2025」計画を撤廃した。否、厳密にいえば、その計画を国内でいわなくなっただけで、それを断念したわけではない。代わりに、打ち出されたのは、「第14次5カ年計画」だった。その計画には宇宙開発や新素材、デジタル技術、スマート農業などが含まれている。しかし、計画の名前を変えても、アメリカはもう油断しない。中国へのハイテク技術や生産の輸出が禁止されている。中国人科学者と技術者を受け入れても、技術が盗まれないように厳しく監視体制が敷かれている。
中国の科学技術の実力の評価は専門家に委ねるが、これからのイノベーションを展望すれば、まさに岐路に立っているといえる。イノベーションの基本はお金ではなくて、人材である。毛沢東時代(1949-76年)、中国は人工衛星と原爆の実験に成功したが、その功労者のほとんどは1949年より前にアメリカの大学で教育を受けた科学者および彼らが帰国したあとの教え子だった。
3年間のコロナ禍のダメージ
コロナ禍はまだ完全に終息していないが、そのダメージは予想以上に大きく、影響も予想以上に長引く可能性が高い。とくにパンデミックによって人の流れが寸断されてしまい、サプライチェーンも中断させられた。コロナ禍前、多国籍企業を中心に中国にR&Dセンターを設立する動きがあったが、今は、中国にあるR&Dセンターを閉鎖し、海外に移転する動きがすでにみられている。主要国の政治家や研究者は、米中デカップリング(分断)はあり得ないと指摘するが、今年に入って、アメリカの輸入に占める中国の割合はすでに首位から陥落し、メキシコに抜かれている。米中デカップリングに関する正しい表現は、あり得る、あるいは、あり得ないのではなくて、デカップリングに伴うハードランディングを回避するためのデリスキング(リスクの軽減)である。こうしたなかで、中国発の技術は生まれにくくなっている。
3年間のコロナ禍において習政権はウィルス感染のパンデミックを恐れて、徹底した隔離措置を中心とするゼロコロナ政策を実施していた。ゼロコロナ政策の意図は間違いなかったが、実施方法に大いに問題があった。当時の隔離措置によって、食料を供給するライフラインも寸断されてしまったため、ウィルスに感染しなかったが、強引な隔離措置によって、自殺者まで出てしまった。
2022年12月、習政権は突如としてゼロコロナ政策を撤廃した。しかし、治療薬がないなかで、ゼロコロナ政策が撤廃されてしまったため、感染者が急増し、高齢者を中心にたくさんの犠牲者が出たといわれている。今は、中国で感染が落ち着いているが、エリート層と富裕層を中心に海外へ移住する人が急増している。エリート層と富裕層の海外移住をきっかけに中国は頭脳と財産を失うことになる。これもイノベーションの支障になる。
日中の科学技術協力の可能性とあり方
短期的には米中の和解は望めない。習政権にとって日本との関係改善はこれからのイノベーションにおいて重要なカギとなる。実は、これまでの白物家電の技術の多くも日本企業からの技術移転を受けたものだった。中国が誇る新幹線の技術の一部も日本から取り入れたものである。したがって、米中対立がエスカレートするなかで、習政権による日本へのアプローチは日増しに強まっていくものと思われる。
いうまでもないことだが、日中の技術協力は日本企業にとってもメリットのあることである。たとえば、日本の自動車メーカーは出遅れている電気自動車(EV)の開発を急いでいるが、日本メーカーにとって重要なのは、電気自動車技術の標準化である。それを標準化するには、ある程度の量を売らないといけない。日本国内市場で一年間、販売される自動車の台数は400万台程度である。それに対して、2022年、中国市場で販売された自動車は2600万台だった。日本企業にとってもっとも有望な市場であるのは明白である。
ただし、技術協力を行う際に、重要なのは互いにルールを順守することである。すなわち、特許などの知的財産権を侵害してはならないことである。要するに、日中の技術協力は重要だが、それに向けたルール作りが不可欠である。ルールを守らない企業があれば、それを厳しく罰する。さもなければ、日中の技術協力は頓挫する可能性が高い。
3年間のコロナ禍によって日中の人の往来がほぼ完全に途絶えてしまった。この状況が長く続けば続くほど、技術協力ができなくなる。なによりも、日本企業もチャイナリスクをこれまで以上に認識している。中国を離れようと考えている日本企業も増えている。今年は日中友好条約成立45周年の記念すべき年である。この節目に際して、日中の技術協力のあり方について再認識する好機と捉えよう。






 新興技術政策の国際動向とアジア・太平洋における国際協力(2025年3月)
新興技術政策の国際動向とアジア・太平洋における国際協力(2025年3月)