北京五輪が終わって 〜「量」と「質」の視点からみる〜
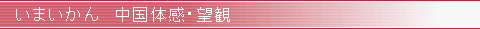
北京五輪が終わって
〜「量」と「質」の視点からみる〜
(中国総合研究センター参事役)
北京五輪が終わった。
今回のオリンピックを通して感じたのは、中国がオリンピックを成功に導くべく、挙国一致して努力したことである。
開会式をはじめとして各種セレモニーや競技は滞りなく終了した。また、中国は優秀な成績をおさめ、開催国としての面目を保った。金メダルについては、アテネオリンピックでは32個で米国に次いで2位だったのが、今回は51個の金メダルを獲得し第1位となった。
今回はオリンピックから受けた筆者の感想を述べてみたい。
中国の選手達からは「とにかく絶対に金メダルをとる!」といった強い執念が感じられた。貧しい環境から脱出して成功者になりたいというハングリー精神が旺 盛な選手も多いのだと思う。国の取り組みとしても、小さい時から将来性のある人材を広く集め、激しく競争させて、優秀な選手を育て上げてきたのだろう。金 メダルを取ることに対する国民の期待も高い。
一方、日本が獲得した金メダルは9個。中国には随分水をあけられている(人口が十分の一であることからすると必ずしも悪くはないのかもしれないが)。ア テネ大会の16個を下回ったこともあり、次回ロンドン大会へ向けて国としても選手個人としても頑張っていくのだろう。ただ、中国の選手育成システム「挙国 一致体制で幼少時から優秀な人材を見つけ出し、エリート教育し激烈に競争させる」を、そのまま日本へ導入しようという声はあまり聞こえてこない。
中国は国土広大。土地柄も多彩であるにも関わらず、挙国一致で優秀な人材を吸い上げることができるのは、「貧困からの脱出」といったハングリー精神に裏打ちされた共通の目的意識をもつ人が多いからではないか。
けれども、現代日本は成熟国家。艱難辛苦に耐えて勝利することを目指す人材を数多く集めるのは、現実問題として難しいと思う。
日本の金メダルの変遷
ではいつから困難になったのか。
ここで筆者の記憶を辿ってみると、物心ついて最初に開かれた東京オリンピック(小旗を振って聖火を見送った記憶がある)以降、高度成長期とその余韻が残る76年のモントリオール大会くらいまでは、オリンピックが開かれる度に
「日本は幾つ金メダルを取れるか!?」
が国民の大きな関心となっていたと思う。勝利に対するこだわりは、今よりずっと強かったように記憶している。例えば、当時バレーボールは日本のお家芸だっ た(76年の女子チームは予選から決勝までの全試合を1セットも失うことなく完全優勝を果たした!)が、この「お家芸」という言葉をあまり耳にしなくなっ てから既に久しい。
その後の記憶はぱっとしない。80年のモスクワ五輪のボイコットぐらいから、日本の社会が落ち着いてきたのか、人々は「オリンピックで国をあげて頑張 る」ことに段々と醒めてきたように感じる。成績は芳しくなかったし、国民の期待感も言ってみれば「ソコソコ」のレベルだったのではないか。
こんな覚醒感が、バブル崩壊後も続いてきた。ところが、近頃オリンピックは盛り上がり、再び関心が高まっているようだ。
個人的な印象だけではどうかと思い、日本オリンピック委員会のWEBで戦後我が国が獲得した金メダル数の推移を見てみた。
1952年のヘルシンキ大会の1個を皮切りに、56年と60年は4個ずつ。64年の東京は地元開催で頑張って16個。それから68年のメキシコシティか ら84年のロサンゼルス大会までは9個から13個の間を行き来している。その後急降下して、88年のソウルから2000年のシドニーまでは3個から5個し かとれなかった。そして、アテネで16個、今回は9個と復活を果たしている。
「盛り上がり=金メダルの数」と考えると、自分の実感とだいたい一致している。
八十年代の初めまでは、まだ高度成長時代の上昇志向的ストリームがあり、
「金メダルをとる!」
という意欲が高かった。その後は、社会の成熟化に合わせて徐々に減退していった・・・というのは理解できる。ただ不思議なのは、21世紀に入ってからオリンピックの成績は復活し、期待感も再度高まってきたことだ。
もちろん日本全体の選手育成システムが充実し、おそらくは予算も増えているのだろう。でも、最後は選手本人の頑張りが決め手になる。
もしかして経済の悪化に伴って、ハングリー精神に満ちた選手達が増えてきたということか。ただ現代日本のスポーツ界においてトップを目指すためには、お金がかかる。どんな優秀な選手でも、最低限初めの頃は個人でその費用を負担しなくてはならないことも事実である。
面白さや感動を求める
改めて昨今の日本国民のオリンピックに関する盛り上がりについて考えてみると、高度成長時代ほど金メダルの数を増やすことには、固執してないように思える。むしろメダルの色や数というより、重きをおいているのは、そのメダルを得るに至った過程の素晴らしさではないか。
例えば、ソフトボールである。確かに女子ソフトボールは、米国を倒して金メダルをとることが長年の悲願となっていた。今回それを達成したことは、喜ばし い限りである。ただ日本の国民に感動を与えたのは、単に悲願を達成したからではない。なんと言っても、準決勝から決勝にわたる上野投手の三連投である。あ の力のこもった熱投があったからこそ、国民の興奮は何倍にもなったのである。
思い起こせば、2006年トリノで開催された冬季五輪において、獲得したメダル数(金メダルの数ではない)は僅かに1個だった。でも、その割には良かっ たというプラスの印象が残ったのは、荒川選手が女子フィギアで金メダルをとったことが大きい。競技で使用したトゥーランドットが開会式でも歌われたり、技 術点にならないイナバウアーに敢えて挑戦したりとエピソードも豊富で、国民の間で大きな話題となったのは記憶に新しい。
つまるところ現代の日本国民にとって大切なのは、メダルの数が多さもさることながら、五輪競技の中で味わうことのできる「面白さ」や「感動」である。北 京でも、例えば北島選手の力強い連覇があった。また金でなくても初めてメダルをとったフェンシングはメジャーではない競技の魅力を十分に伝えたし、水泳や 陸上の男子400メートルリレーなどはインパクトが大きかった。更に例えメダルがとれなくても、世界一の中国ペアを破った女子バドミントンは多くの人に賞 賛された。
日本人にとっての五輪の成績の評価や印象は、メダルの「量」だけでなく、競技のプロセスやその成果が与えた面白さや感動といった成果の「質」にも左右さ れる(この点柔道は金メダルをとって当たり前なのでハードルが高い)。選手の育成に当たっても、ハングリー精神をベースとして挙国一致で強く管理して頑張 るというよりも、厳しい競争下ではあるものの、その競技の面白さを体得させることにも力点をおくことが大切で、結果としてうまくいくように思える(全くの 素人考えで恐縮だが)。おそらくアテネ以降の好成績は、そんなアプローチが功を奏しているのではないかと、勝手に想像している。
中国のシステムの変化
このように考えると、マンスリーレポート8月号の北京五輪に寄せた特集において、国家体育総局の李祥晨氏らが「ポスト五輪時代の中国スポーツ」と題するレポート中、次のように述べているのが興味深い。
我 が国の高度に集中したスポーツ管理体制、政府の競技における金メダル効果重視とスポーツ社会における社会効果軽視、各スポーツ協会が大衆スポーツを顧みな いこと、大衆スポーツ向け公共製品の供給制度の欠陥といったことのために、我が国の競技スポーツの力強い発展を社会スポーツの発展が追随するという関係が 我が国のスポーツ発展における最も不調和な音符となったが、これはスポーツの調和のとれた発展の基礎をも根本から揺るがすであろう。
強力に国が管理して金メダルを獲得していくシステムが曲がり角に来ていることを示唆している。
また、北京体育科学研究所の魏文哲氏は
中国陸上競技の新たな挑戦」の中で、以前は『専門のスポーツチームに入ることは多くの子供たちの、とりわけ農村の貧しい家庭が貧困を脱出するための重要な選択肢となっていた
が、現在は状況が変化していることを指摘している。
ここ数年来、中国の各分野の市場化改革が絶えず経済の発展を促進してきた。目下、専門のスポーツ選手が受けている優遇政策に大きな変化は起きていないが、 就職ルートが絶えず開拓され、生活環境が絶えず改善されるにつれて、スポーツ分野の吸引力も次第に低下し、専門のスポーツ選手はもはや貧困を脱出し豊かに なるための最善の選択ではなくなり、ますます多くの保護者が自分たちの子供が体育学校へ進学することを望まなくなった。<中略> 科学的トレーニングによって、選んだ目標に対する人間性を重視した養成を行ない、限られた人材の最大の潜在能力を掘り起こすことが、中国の陸上競技発展の 新たな課題になった。
中国経済が発展し国民生活が豊かになっている今、社会の中における競技スポーツの位置づけも徐々に変 わってきている。「ハングリー精神で頑張る人材はいくらでもいる」「挙国一致で管理して金メダルを量産する」といったアプローチをとることが、次第に困難 になっていることが分かる。13億人の中から超優秀な人材を大勢選んで競わせ勝ち残った人を代表にすれば良いというのではなく、選手一人一人の人間性や嗜 好といったことを、これまで以上に丁寧に深く把握し尊重しなくてはならなくなっていることが、報告書から伺えるのだ。
科学技術人材の育成でも
「量」と「質」の両方の視点から見ることの重要性は、科学技術人材の育成においても言えるかもしれない。
優秀な科学者となるために、たくさん勉強に没頭することは無論必要である。ただ「質」の面ではどうか。
筆者は科学技術政策研究所にいた頃、「国際級研究人材の養成・確保に関する環境・施策」を明らかにする研究プロジェクトに取り組んだことがある。本プロ ジェクトの「国際級研究人材」とは、平たく言えば「国際的にばりばり活躍している日本人研究者」であり、このうち幾つかの国際的な科学賞を受賞した者、主 要先進国のアカデミー外国人会員、被引用度数が高い論文を書いた日本人研究者等をピックアップした。そして、どのようにして国際級研究人材に育ったのかア ンケートをとり、百名余りから回答を得た。
紙数の関係上アンケートの詳細な集計結果は報告書を読んで欲しいが、例えば子供時代において強調されていることの一つは
周囲の大人から知的な刺激を受けていることを示す記述が目立った反面、あまり勉強を強制されたことはなく、どちらかというとのびのびと好きなことをしながら成長している傾向が見られた
ことだ。猛勉強も大切だが、まずは科学に対する知的な興味や好奇心を伸ばして自由に発想していくことが、研究者として活躍していくための土台となるのである。
ロンドン五輪へ向けて
以上北京オリンピックを見ていて、日中両国における社会的背景や人材育成のアプローチの違いについて連想したことをまとめた。
筆者自身は日本人なので、次回2012年のロンドン五輪においても、我が日本の選手団が大いに活躍して感動を与えてくれることを期待している。
また、中国の競技スポーツへの取り組みが、今後どのように変わっていくのか興味をもって見守っていきたい。
おわりに
筆者が本コラムを書き始めたのは、マンスリーレポート第1号の2006年10月からである。今回のコラムで丸二年を迎えるため、ひとまず本号をもって一つの区切りとしたい。
この間、色んな人から「コラム読んでます」と声をかけられた。自分の雑文を読んでくれる人の存在を知って、嬉しい反面、恐縮したが、とても励みになった。
読者の方、そしてコラムを書くために協力して下さった日中両国の関係者に、この場を借りて感謝の意を表したい。
- 財団法人日本オリンピック委員会WEB(http://www.joc.or.jp/)
- 中国総合研究センターマンスリーレポート第23号(2008年8月20日発行)特集 「スポーツ科学、中国の挑戦〜北京五輪に寄せて〜」
(https://spc.jst.go.jp/report/200808/crc-1.html) - 松室寛治、今井寛,「国際級研究人材の養成・確保のための環境と方策(アンケート調査の結果より)−「個人を活かす」ためのシステムへの移行」,文部科学省科学技術政策研究所調査資料-102,2003
(http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/mat102j/idx102j.html)