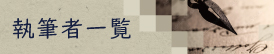中国の科学者、人類初めてヤップ海溝の水深8919メートルの海底に到達
2021年12月08日
上海交通大学深部生命国際研究センター長を務める生命科学技術学部教授の肖湘氏は、「ヤップ海溝の海底では、ナマコ、ヒトデ、イソギンチャク、海綿などのマクロ生物を発見し捕獲した。高密度のマクロ生物は、堆積物と水域に豊富な微生物が含まれることを暗示している。人類未踏だが、人類活動(ゴミ)の影響を観測した」と述べた。新たな科学調査航行段階において、肖氏はヤップ海溝の人類未踏の水深8919メートルの海底に到達した。
肖氏が率いる同大の「深海科学調査4人チーム」が科学調査船「探索1号」に乗り、西太平洋の海域における深淵科学調査任務を終了し、無事に海南省三亜市に帰港した。
上海交通大学深部生命国際研究センターのチームは今回の航行段階において、有人潜水船「奮闘者」号に乗り8回の潜水作業任務を行った。これにはマリアナ海溝の「チャレンジャー海淵」と、人類が初めて到達したヤップ海溝の水深8919メートルの未知のエリアが含まれる。水、堆積物、岩石、マクロ生物を含む200カ所以上の貴重な深淵サンプルを採取・処理し、一連の環境パラメータを測量することで、深淵生態系の研究のために貴重な材料とデータを提供した。
今回の科学調査において、肖氏と2人のダイバーがヤップ海溝の水深8919メートルに位置する人類未踏の未知のエリアに到達した。肖氏は、「マクロ生物の個体の大きさにしろ、マクロ生物の密度にしろ、マリアナ海溝では9000メートル以上のエリアより低い。しかし、全体的にはそこは決して生物が存在できないエリアではなかった。人類活動の海洋最深部への影響も時おり見られた。我々の主な作業は深淵微生物をめぐり展開された。今後は実験室でのシミュレーションや培養などの研究と結びつけ、生物多様性、命の起源と境界、気候変動の影響、汚染物質の分解などの重要な科学的問題の答えを見つける」と述べた。
中国科学技術ニュース 2021年12月
サイエンスポータルチャイナ事務局が、中国の科学技術に関するニュース記事を人民網と共同通信の記事より選んで、日々届くフレッシュなニュースとしてお届けしています。
下記よりご覧ください。
-
-
2021年12月31日
-
-
2021年12月30日
-
-
2021年12月29日
-
-
2021年12月28日
-
-
2021年12月27日
-
-
2021年12月24日
-
-
2021年12月23日
-
-
2021年12月22日
-
-
2021年12月21日
-
-
2021年12月20日
-
-
2021年12月17日
-
-
2021年12月16日
-
-
2021年12月15日
-
-
2021年12月14日
-
-
2021年12月13日
-
-
2021年12月10日
-
-
2021年12月09日
-
-
2021年12月08日
-
-
2021年12月07日
-
-
2021年12月06日
-
-
2021年12月03日
-
-
2021年12月02日
-
-
2021年12月01日
-
-
共同通信提供月別バックナンバーリスト
バックナンバー
-
共同通信提供記事アーカイブ
人気記事
-
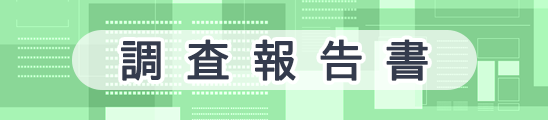
-
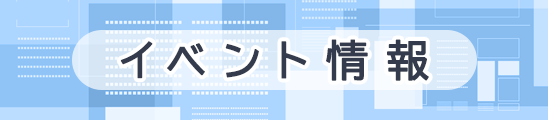
第42回 アジア・太平洋研究会のお知らせ
「「中国製造2025」最終年を迎えた中国~産業高度化政策の現状と今後の展望」4/25(金)15:00~ 詳細・申込みはこちら



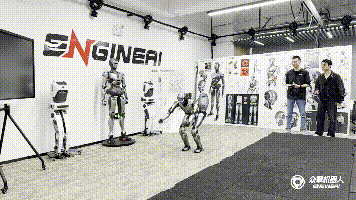

 新興技術政策の国際動向とアジア・太平洋における国際協力(2025年3月)
新興技術政策の国際動向とアジア・太平洋における国際協力(2025年3月)