6.2 社会基盤分野の現状および動向
(1) 交通・運輸
中国は急激な経済成長の裏で輸送インフラ不足に悩まされてきた。中国政府は近年、インフラの大幅な改善をめざしてすべての輸送モードに積極的に投資を行ってきており、その成果は着実に現れてきているが、依然として多くの課題が残されている。
中国交通運輸部計画局の李興華・副局長は2008年11月25日、2009年には交通インフラ整備に約1兆元規模の投資を見込んでいることを明らかにした。主に道路や沿海の港湾、内陸河川の港湾や航路などの施設の建設に充てられる。
同副局長によると、高速道路への投資が最も多く、4000億~5000億元が投入される見通しになっている。また、農村道路の建設には2000億元、沿岸の港湾建設には700億元、河川港湾や航路建設には200億元が投入される予定という。ちなみに、2008年には、道路と水路のインフラ整備に約8000億元が投入された。
なお国家発展改革委員会は、2008年分として新規に追加された政府資金1000億元のうち280億元が交通インフラ建設に充てられたことを明らかにしている。内訳は、鉄道150億元、高速道路50億元、農村道路50億元、中西部の支線空港と西部の幹線空港30億元となっている。
1)鉄道輸送
中国鉄道部によると、2007年末時点で中国の鉄道の営業距離は7万8000kmに達した。内訳は、国営6万3600km、合資9500km、地方4800kmである。また、路線密度81.2km/万km2、複線化率34.7%(営業距離2万7100km)、電化率32.7%(営業距離2万5500km)となっている。
鉄道の高速化も着々と進んでおり、スピード別に見た営業距離は、時速250km以上:1019km、時速200km以上:6227km、時速160km以上:1万6000km、時速120km以上:2万4000kmに達する。
2007年末時点で機関車数は1万8300両に達し、このうちディーゼル機関車と電気機関車が全体の99.4%を占めた。主要幹線ではすべてディーゼル機関車と電気機関車が牽引している。この中には、高出力の電気機関車550両が含まれている。
2007年の年間貨物輸送量は31億4000万トン(預け分を含む)で、トン・キロベースでは2兆3797億トン・km(同)を記録した。旅客輸送量は13億6000万人、人・キロベースでは7216億3100万人・kmに達した。
2007年4月18日に時速200kmを超える「和諧号」が営業運転を開始して以来、同年末までに旅客輸送量は6121万人、人・キロベースでは129億人・kmを記録した。「和諧号」は、CRH(China Railway High-speed)と呼ばれる高速車両を利用する列車の愛称である。
鉄道部によると、中国で鉄道が最も混雑するのは春節前後の約40日間で、2009年は1月11日以降の最初の21日間だけで9361万人が鉄道を利用した。1日あたりでは446万人が鉄道を利用した計算になり、前年同期に比べて15.4%の伸びを示した。
また、鉄道部によると、35日目にあたる2月14日には全国で592万9000人が鉄道を利用した。これは、前年のピーク時より116万5000人多く、春節時期の鉄道利用者数としては過去最高を記録した。
中国政府は、こうした状況を踏まえ、公共交通機関の柱として鉄道輸送力の強化に積極的に取り組んでいる。鉄道部が2008年11月27日に公布した「中長期鉄道網規画」(2008年調整版)では、2020年までの鉄道営業距離達成目標を、2004年に公布した「中長期鉄道網規画」で定められていた10万kmを12万kmに上方修正した。これによって、2020年までに新規に建設される鉄道の営業距離は4万1000kmになった。このほか、電化率は従来計画の50%から60%に、また石炭の輸送能力も23億トンまで引き上げられた。
鉄道部の陸東福・副部長は、「中長期鉄道網規画」の公布以来、鉄道建設に8090億元が投入されたとしたうえで、このうち地方政府と企業の負担額が1400億元であったことを明らかにした。また、同副部長は新しい目標を達成するためには2020年までに総額で5兆元の投資が必要になるとの見通しを示した。
なお、鉄道建設は中国政府の打ち出した内需刺激策の1つとして位置付けられており、2009年の鉄道部門における固定資産総投資額は7007億元に達するとみられている。新規のレール敷設距離は5148km、新規開通路線は5849km、複線レール敷設距離は3462km、複線開通路線は4662km、新規電化開通路線は5606kmに達する見通しとなっている。
中国の鉄道建設計画ではスピードアップも大きなテーマとなっている。中国では現在、日本やフランス、ドイツ、カナダから導入した技術を用いた時速200~300km級の高速列車が運行しているが、さらにスピードアップした時速350km以上で走行可能な高速鉄道技術の構築に着手している。科学技術部と鉄道部が2008年2月26日に合意したもので、これまでの成果を踏まえ、独自の研究開発を強化し、北京と上海を結ぶ路線に導入する計画という。
道路交通の混雑緩和をめざす地下鉄建設も着々と進められている。北京では、4号線、6号線第1期、8号線第2期、9号線、10号線第2期、亦壮線、大興線の7路線の地下鉄建設が行われているほか、2009年には15号線第1期、昌平線、房山線、西郊線、7号線、14号線の建設がスタートすることになっている。こうした地下鉄建設にかかる費用は総額で2000億元と見込まれており、2015年には完成の予定になっている。
2)自動車と道路輸送
交通運輸部が2008年4月18日に公表した「2007年道路・水路交通業界発展統計公告」によると、2007年末時点の中国の道路総延長は358万3700kmに達した。内訳は、国道13万7100km、省道25万5200km、県道51万4400km、郷道99万8400km、専用道路5万7100km、農村道路162万1500kmとなっており、農村道路が全体の45%を占めている。
高速道路の総延長は2007年末時点では5万3900kmであったが、交通運輸部の李盛霖・部長が2009年1月15日に明らかにしたところによると、2008年末時点では6万kmに達し、米国(10万km)に次いで2位となった。
2007年の道路運送量は163億9400万トン、トン・キロベースでは1兆1354億6900万トン・kmに達した。旅客輸送量は延べ205億700万人で、人・キロベースでは1兆1506億7700万人・kmを記録した。2007年末の営業用自動車数は849万2200台で、このうち旅客用自動車が164万7300台、貨物用自動車が684万4900台となっている。なお、中国の自動車保有台数は2007年末時点で4358万台(「2008中国統計年鑑」)に達している。
国務院が2007年10月に公布した「総合交通網中長期発展規画」では、2020年の総合交通網(航空、海上、都市内道路、農村道路を除く)の規模を338万kmとしたうえで、農村道路を除いた道路網規模を300万km以上(2級以上の道路65万km、高速道路10万kmを含む)とする目標を掲げている。
また同規画では、中国の交通運輸体系の効率が低い現状を踏まえ、一体化交通運輸体系を構築する方針が打ち出されている。具体的には、旅客の乗り換えがスムーズに行えるようにするほか、貨物運搬の接続効率の改善などをめざす。
中国では、交通部門でのエネルギー消費が大きく、汚染も深刻になっていることから、既存自動車の省エネや排出抑制技術を導入するとともに、ガスを燃料とした自動車やハイブリッド自動車の研究開発も進められることになっている。
交通事故の減少も大きなテーマの1つとしてあげられており、事故の事前予防や科学的な管理、輸送システムの安全性と信頼性の向上、救急能力の向上に対する中核技術などの研究が行われる。
大都市の交通渋滞の解決も急務になっており、軌道交通を中心とした一体的な都市交通システムと都市部におけるインテリジェント交通システムに関する中核技術の研究を行うほか、交通需要管理を強化し、乗用車の利用を誘導または制限することによって渋滞を緩和することも検討されている。
中国自動車工業協会によると、2008年の中国の自動車製造台数は前年比5.2%増の934万5100台、販売台数は同6.7%増の938万500台となったが、伸び率は前年に比べてそれぞれ16.8ポイント、15.1ポイントという大幅な落ち込みをみせた。
こうしたなかで、温家宝首相が2009年2月14日に招集した国務院常務会議では、自動車産業と鉄鋼産業の調整・振興に関する規画が審議され、原則的に承認された。それによると、自動車消費市場を育成するための措置として、2009年1月20日~12月31日までに限り、排気量1600cc以下の乗用車の自動車購入税が5%に引き下げられることになった。
また、企業による技術革新・技術改良、新エネルギー車と部品開発を支援するための措置として中央政府が今後3年にわたって100億元の特別資金を計上する。さらに、こうした新エネルギー車や省エネ車の大都市での普及をはかるため、政府が補助金を出すことになった。
3)船舶および水路輸送
「2007年道路・水路交通業界発展統計公告」によると、中国の内陸河川航路は2007年末時点で12万3500kmに達した。また、水路によって運送された貨物量は24億8700万トンで、トン・キロベースでは5兆5485億5000万トン・km、旅客輸送量は延べ2億2000万人、人・キロベースでは73億5800万人・kmを記録した。
中国には2007年末時点で、19万1800艘の輸送用船舶があり、内訳は内陸河川用18万200、沿海用9300、遠洋用2300となっている。コンテナ船は2129艘である。
交通運輸部は2009年1月6日、春節期間の水路による旅客輸送量が前年同期を8%上回る延べ3100万に達する見込みであることを明らかにした。水路による旅客輸送用船舶は1万3000艘に達するとみられている。
また、交通運輸部は2009年2月11日、長江本流航路の整備などに20億元を投じる考えを明らかにした。中国政府が進める内需拡大策の一環で、下流の「三沙水路整備プロジェクト」の1期、中流の黒砂洲、武穴、載家洲、張南上浅区、周天、瓦口子、沙子などの水路整備プロジェクト、上流の三峡ダム直下流部にある暗礁爆破工事などが含まれている。
整備の対象にあがっている航路は砂床であることから、運輸面での障害となっていた。このため中国政府は2008年に8億元を投入して長江本流航路の整備プロジェクトに着手した。
(2) 公共安全 (防災)
1)地震防災
2008年5月12日に四川省で発生したマグニチュード8.0(中国地震局発表、米地質調査所はマグニチュード7.9)の地震(「四川省?川大地震」)は、地震防災の重要性を改めて認識させる形になった。
中国科技労働者退職者協会副会長で地震分会会長を務める何永年氏によると、中国では20世紀に入ってからの平均でマグニチュード5以上の地震が年20回、6以上が年4回、7以上が3年に2回の頻度で発生している。また、20世紀に関して言うと、中国で発生した各種自然災害による死者数のうち、地震によるものが50%以上を占め、全死傷被害の第1位になっている(「中国の地震防災の現状と展望」、科学技術振興機構「Science Portal China」、http://spc.jst.go.jp/trend/hottopics/r0901_he.html)。
一方で、同氏によると、全国土の41%、都市部の50%、人口100万人以上の大・中規模都市の70%がレベル7以上の高震度危険エリア内に位置している。多くの都市が高震度危険地帯にあるため、地震防災対策は一層難しくなっている。
こうしたことから中国政府は、一貫して地震防災のための取り組みを重視している。中国地震局は「地震観測予報システム」、「地震災害予防システム」、「緊急援助システム」という枠組みに従い、地震災害の予防と軽減に向けた取り組みを進めている。
このうち地震観測予報システムについては、160ヵ所以上(何永年氏)の基本地震観測所で構成された国家地震観測所ネットワークが構築されており、24時間体制で観測が行われている。得られたデータは、北京の地震観測ネットワークセンターにリアルタイムで送られる。センターでは送られたデータを直ちに処理し、規定に基づいて関係部門に送達するほか、起こり得る地震の前兆現象について調査を行い、地震予知について研究している。表6.19に中国国内の地震観測所を示す。
|
地区 |
国家地震観測所 |
国家地震遠隔観測所 |
市・県の地震台 |
企業 |
||||
|
国家級 |
省級 |
強震 |
地震ネット |
支所 |
市・県級 |
目視 |
||
|
全国 |
139 |
276 |
681 |
82 |
1007 |
792 |
11659 |
107 |
|
北京 |
4 |
18 |
44 |
3 |
92 |
66 |
129 |
2 |
|
天津 |
4 |
4 |
34 |
1 |
28 |
? |
? |
? |
|
河北 |
6 |
17 |
4 |
3 |
56 |
31 |
847 |
11 |
|
山西 |
5 |
20 |
27 |
5 |
58 |
78 |
1036 |
27 |
|
内蒙古 |
6 |
15 |
32 |
1 |
8 |
26 |
525 |
3 |
|
遼寧 |
6 |
11 |
37 |
5 |
71 |
28 |
672 |
3 |
|
吉林 |
5 |
5 |
10 |
1 |
5 |
13 |
500 |
? |
|
黒龍江 |
6 |
5 |
64 |
4 |
20 |
4 |
47 |
1 |
|
上海 |
2 |
? |
13 |
1 |
28 |
7 |
11 |
? |
|
江蘇 |
8 |
7 |
50 |
9 |
59 |
56 |
235 |
4 |
|
浙江 |
3 |
2 |
5 |
4 |
27 |
28 |
4 |
? |
|
安徽 |
3 |
10 |
9 |
1 |
9 |
14 |
357 |
1 |
|
福建 |
4 |
9 |
48 |
1 |
31 |
22 |
170 |
1 |
|
江西 |
2 |
4 |
? |
1 |
8 |
6 |
243 |
? |
|
山東 |
7 |
20 |
47 |
5 |
63 |
4 |
957 |
7 |
|
河南 |
2 |
12 |
? |
1 |
8 |
12 |
676 |
4 |
|
湖北 |
4 |
5 |
4 |
5 |
54 |
28 |
157 |
? |
|
湖南 |
2 |
5 |
1 |
1 |
10 |
17 |
183 |
2 |
|
広東 |
5 |
8 |
67 |
4 |
47 |
13 |
129 |
? |
|
広西 |
3 |
5 |
19 |
5 |
53 |
1 |
513 |
3 |
|
海南 |
2 |
3 |
3 |
1 |
10 |
9 |
238 |
? |
|
重慶 |
1 |
? |
? |
? |
? |
4 |
8 |
? |
|
四川 |
7 |
14 |
69 |
7 |
84 |
89 |
476 |
12 |
|
貴州 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
雲南 |
10 |
20 |
23 |
1 |
32 |
92 |
1036 |
2 |
|
チベット |
3 |
5 |
2 |
1 |
6 |
? |
? |
? |
|
陝西 |
5 |
9 |
? |
2 |
23 |
44 |
704 |
11 |
|
甘粛 |
9 |
20 |
24 |
3 |
27 |
42 |
814 |
7 |
|
青海 |
3 |
9 |
9 |
3 |
49 |
13 |
706 |
4 |
|
寧夏 |
4 |
3 |
6 |
1 |
7 |
14 |
227 |
? |
|
新疆 |
8 |
11 |
30 |
2 |
34 |
31 |
59 |
2 |
中国政府は、9万人近く(何永年氏)の死者を出した四川地震を受け、被害を受けた地域の再建計画と地震対策の強化を矢継ぎ早に打ち出している。
まず再建計画については、国家発展改革委員会が関係部門と共同で2008年11月5日、土地利用や生態系の回復、農村建設、都市システム、公共サービス施設の建設、住宅建設など全部で7件の計画を公表した
計画では、3年間に1兆元を投入し、地震による被害が深刻な四川省をはじめ、甘粛省、陝西省の地域再建を行うとともに、被災地域の基本的な生活や経済・社会の発展を被災前の水準以上にするとの目標が掲げられた。
また、科学技術部、国土資源部、中国地震局は2008年11月6日、「四川省?川大地震」の断層のボーリング調査を開始した。地震の発生メカニズムを明らかにするのがねらいで、2ヵ所の断層に深さ1200mの先導井2本と深さ3000m級の主井2本を掘削し、観測機器を設置して将来の地震観測や予知、早期警戒のための基本的なデータを収集する。
地震対策の最前線に立つ中国地震局の陰朝民・副局長は2008年7月19日、①地震予知理論研究の強化②地震監視網の構築・整備③国際協力の強化――という側面から中国における地震予知を継続的に進める考えを明らかにしている。
省レベルでの地震防災対策もスタートしている。四川省科学技術庁は2008年6月6日、中国初となる耐震工学技術重点実験室と位置付けられる「抗震工程技術四川省重点実験室」を設立した。同省政府は、?川大地震で家屋や橋梁、道路等の基盤施設に甚大な被害が出たのは西部山岳地帯における耐震技術の研究不足が一因と判断している。
同実験室は、西南交通大学に設置され、土木工学や交通運輸工学、地質工学、測量・製図工学等、地震に関係する学科をベースとして、関連分野の研究者が研究活動を行う。耐震建築物の土木構造を重点的に研究し、震災復興と今後の再建への貢献が期待されている。
2)気象観測・災害早期警戒、衛星利用
中国気象局は2008年5月8日、これまで気象部門で公共気象サービスを提供する組織がなかった現状を踏まえ、公共気象サービスセンターを設立した。公共気象サービスは国民の生命・財産の安全や経済社会の持続可能な発展と密接に関係しており、中国がめざす「小康社会」(いくらかゆとりのある社会)の実現に向けて重要な役割を果たすと位置付けられている。
なお中国気象局は2008年1月30日、国が19億6000万元、各気象部が10億元を拠出し気象観測・災害警報体制構築に着手する考えを明らかにしている。具体的には、観測ステーションの増設、ハイテクを用いた予防・警報能力の向上、警報のスピードアップによる公共サービスシステムの強化、ソフト・ハード整備が柱になっている。実施期間は3~5年が予定されている。
中国は、気象観測衛星の拡充も積極的に進めている。中国の気象観測衛星は「風雲」という名称がつけられており、2008年には、全世界と全天候をカバーする多スペクトル・3次元の遠隔探査能力を持つ「風雲3号A」が5月27日に、また気象や海洋、水文等の観測データの収集等に使われる「風雲2号06星」が同12月23日に打ち上げられた。
中国気象局は、2020年までに合計22機の気象観測衛星を打ち上げ、アジア全体をカバーする衛星気象観測網を整備する意向を明らかにしている。投入が予定されている気象衛星は、「風雲2号」タイプの静止軌道衛星が4機、「風雲3号」タイプの太陽同期軌道の中高度・極軌道衛星が12機、「風雲4号」タイプの次世代静止軌道衛星が6機となっている。
中国は、環境や災害の監視・予報用としても積極的に衛星を利用する方針を示している。2008年には、災害や生態系の破壊、環境汚染の進行などを観測し、災害の発生件数の減少や発生後の対応などに利用することを目的とした「環境1号A、B」衛星が9月6日に、また気象観測から自然災害、環境変化などを監視する小型実験衛星「創新1号02星」が11月5日に打ち上げられた。
中国は、交通輸送や気象、石油、海洋、森林防火、災害予報、通信、公安警備などへの利用を目的とした「北斗」衛星ナビゲーション・システムの構築も積極的に進めている。同システムは、米国のGPS、ロシアのGNSS、欧州のガリレオ計画に対抗して進められている中国独自の衛星測位システムである。
システム自体の構築は2000年にスタートし、これまでに5機の「北斗」衛星が打ち上げられている。2009年には12機の「北斗」衛星を打ち上げ、まずシステムを稼働させてから、最終的には30機以上でシステムを完成させる予定になっている。
このほか国家測絵(測量・製図)局も2009年1月13日に発表した今後の戦略方針の中で、中国版「グーグルアース」や「グーグルマップ」の構築に着手する考えを明らかにしている。
(3) 都市化および都市発展
1)資源節約・環境友好型社会
中国では、1978年に改革開放政策を実施して以来、都市化が急速に進んだことから、エネルギーや資源、環境問題が深刻化を増し、経済発展と環境保護との矛盾がますます顕著になってきた。中国政府は、こうした状況を踏まえ、「両型社会」(資源節約・環境友好型社会)の構築に乗り出した。
中国科学技術部と建設部は2007年5月、都市化と都市発展に関するプロジェクトの発足会を開催した。最初に発足したプロジェクトは以下の通りである。
- 省エネ中核技術の研究とモデル
- 都市住民居住環境の改善・保障の中核技術に関する研究
- 環境友好型建築材料の製品の研究開発
- 近代化建築の設計・施工に関する中核技術研究
- 都市部大型建築の災害防止に関する中核技術研究
- 都市部地下空間の建設技術に関する研究とモデル・プロジェクト
- 都市部デジタル化のコア技術に関する研究とモデル
- 建築工事設備技術に関する研究と産業化開発
こうしたなかで国家発展改革委員会などは2007年12月、天津市を国家循環型経済モデル実験都市とすることを決めた。実験都市建設の目標としては、①資源節約型のモデル都市を建設する②工業を中心に、第一次、第二次、第三次産業の相互作用による循環型経済産業発展の枠組みを構築する③泰達と子牙の国家旧モデル実験パークを重点に循環型経済産業体系を構築する④エコ快適居住モデル区を建設する⑤制度と科学技術のイノベーションに重点を置き、循環型経済の支援システムを構築する――ことが掲げられた。
また国家発展改革委員会は2007年12月14日、国務院の同意を得て、湖北省の武漢都市圏と湖南省の長沙・株洲・湘潭都市群を、全国資源節約・環境保護型社会建設に向けた総合一体型改革モデル地域と指定することを承認し、両省政府に対して通知した。
このうち湖南省では、中国都市計画設計院が同省の要請を受けて1年程度をかけてまとめた張家界空間発展戦略・都市全体計画が2008年7月6日、内外の専門家の審査にパスした。同計画では、世界自然遺産と世界地質公園に指定されている武陵源風景名勝区の保護をさらに強化する措置がとられた。
具体的には、これまで武陵源区に設定されていた都市発展・観光サービスの主要区域が風景区から約30km離れた永定区に移されるとともに、観光産業などに関連した新しいタイプの工業拠点も風景区から100km以上離れた慈利県や桑植県に定められた。湖南省北西部の武陵源山脈にある張家界は、自然の織り成す美しい風景で知られる中国有数の名勝である。
2)都市計画
2010年の万博を控えた上海市政府は2008年7月10日、「都市環境建設と管理を強化するための600日間行動計画綱要」を公布し、ベター・シティ(better city)、ベター・ライフ(better life)の実現、美しい居住環境作り、都市文明レベルの向上をめざして、「都市景観の改善」、「市民生活環境改善」、「都市管理強化」の3つのプロジェクトを実施することを明らかにした。
上海市政府は、国際都市という名前とは不釣合いの「不潔、乱雑」な現状に対して、「清潔、整然、美観、安全」を基準として、15項目の措置をとることによって徹底的に改善を行う考えを表明した。
具体的には、違法建築を徹底的に解体するほか、道路設備のクリーン化をはかる、車両・船舶を徹底的に洗浄する、建築物の壁を洗浄する、広告看板や公共施設、駐車場の規制を統一化するなどの対策が含まれている。
また、上海市が公布した綱要では、万博地区の周辺区域や万博の見学・接待所、観光スポット、交通の要衝、黄浦江、高架道路、鉄道、高速道路、軌道交通沿線区域などが重点的に改善する区域として指定された。
上海市は、公共緑地の拡大も進めており、公共緑地500ヘクタールを含めた1000ヘクタールの各種緑地を建設するとの計画を2008年3月に明らかにしている。この計画によると、1人あたりの公共緑地面積を12.5m2に引き上げるとともに、10万m2の屋上を緑化することを目標に、2008年に10ヵ所の古い公園を改造し、260ヵ所の旧住宅地を緑化することになっていた。
こうしたなかで住宅・都市農村建設部は2008年10月、都市緑地システム防災計画の策定を急ぐよう、各地方政府の関係部署に通達した。都市部の緑地化を進め、緑地の持つ防災機能の健全化をはかり、総合防災機能をさらに強化するのがねらいという。
上海市は、地下空間の開発・利用を拡大する一方で、地下空間の管理を強化する動きを強めている。同市の計画・国土資源管理局によると、上海市にはすでに1000万m2に達する地下建築物や構造物が建設されている。上海市は、31ヵ所の重点開発地区を地下空間重点開発区と指定しており、この中には万博地区や徐家漚、江湾五角場、北外灘地区などが含まれている。なお、深圳市政府も2008年7月、「深圳市地下空間開発利用臨時弁法」を公布し、地下空間利用に関する方針を示した。
3)都市部での雇用確保
国家統計局がまとめた2008年の全国人口変動状況によると、2008年末までに中国の都市人口が6億人を超えた。2007年時点と比べると1288万人増加した計算になるが、人口増加のスピードは鈍っている。
一方で、米国発の金融危機を発端とする世界的な経済危機によって、中国が抱える都市問題が浮き彫りになった。
農業部が2009年2月に実施した調査によると、経済危機の影響を受け、農村からの出稼ぎ労働者(農民工)の失業者数は約2000万人に達した。中国社会科学院の人口・労働経済研究所の王徳文氏は、農民工の70%に相当する1400万人が、職を求めて都市に戻ると推測している。
同氏によると、都市部での労働力人口の増加もあり、現在830万人が失業している。さらに、2009年には610万人が専門学校や大学を卒業することに加えて、都市部では前年に職につけなかった150万人の浪人がいる。このため、都市部では、約3000万人分の雇用を確保する必要があるものの、経済成長にともなって創出される新規雇用は毎年900万人程度しかないとみられている。
(4) 国土の管理・保全
1)中国の耕地面積
中国の耕地面積は1996年に1億3000万ヘクタールに達した後、減少を続けた。国土資源部が2008年4月16日に公表した「2007年中国国土資源公報」によると、2007年末時点の耕地面積は1億2173万ヘクタールとなった。
中国政府は、「第11次5ヵ年」期(2006~2010年)において、耕地面積1億2000万ヘクタールの維持を、拘束性を持った目標として掲げている。また、耕地面積維持の一環として、1987年に公布された「中華人民共和国耕地占用税暫定条例」が改正され、2008年1月から施行されている。
新条例では、それまでの条例で規定されていた税額基準をベースに、上限と下限がそれぞれ約4倍引き上げられ、各地方の具体的な適用税額は、省や自治区、直轄市の政府が新条例の規定と各地の状況に基づいて決定することになった。このほか、外資系企業と海外企業を新たに耕地占用税の課税対象とし、国内資本と海外資本の税負担が一本化された。
税額基準の引き上げにあたっては、物価や地価の上昇、国が定めた厳格な耕地保護制度の徹底、「三農」(農民、農村、農業)向けの資金の確保――が考慮された。
中国における耕地面積減少の背景には、以下のような原因があると指摘されている。なお、2007年には開墾等によって19万5800ヘクタールの耕地が増加している。
- 農業以外への転用
- 生態系保持
- 災害による破壊
- 農業構造調整
中国政府は2008年末、国際的な経済危機に対応するための内需拡大・経済安定促進策を打ち出しているが、国土資源部をはじめとした関係部門は共同で、内需拡大にともなう各種の土地使用を厳しくチェックするよう求めた通達を出している。
2007年全国国土利用状況
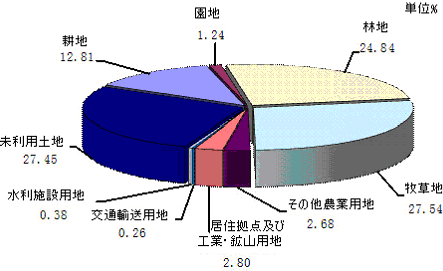
出典:「2007年中国国土資源公報」(国土資源部、2008年4月)
全国耕地面積変化の推移
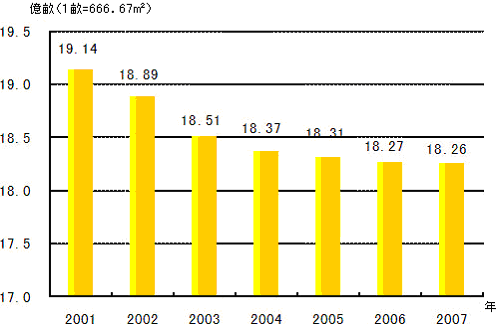
出典:「2007年中国国土資源公報」(国土資源部、2008年4月)
2)砂漠化防止と緑化
中国では、砂漠化の防止が急務となっている。国家林業局によると、1990年代末には1年間に3436km2が砂漠化していたが、2007年には約3分の1程度までに減少してきた。
しかし、中国国務院発展研究センター工業交通貿易司の唐元・司長が2008年11月25日に明らかにしたところによると、砂漠化による直接経済損失は毎年540億元にも達し、約4億人の生活に影響を与えている。
同氏によると、砂漠化は国土の18%にまで達している。また、全国の水土流出面積は356万km2、砂漠化した土地の面積は174万km2に達しているだけでなく、90%以上の草原が退化している。砂漠化によって、大量の粉塵が舞い上がり、砂嵐が頻繁に発生している。北京や天津などでは、住民の健康や生活まで深刻な影響が及んでいる。
こうしたなかで砂嵐の観測や砂漠化を防止するプロジェクトが着々と進められている。国家発展改革委員会は、「青海湖流域の生態環境保護と総合整備計画」を承認し、2008年から10年をかけて、湿地保護や砂漠化した土地の整備、生態人工保護林の整備などを実施することになった。
プロジェクトは、青海湖流域の剛察、海晏、天峻、共和の4県で実施され、面積は2万9661km2に及ぶ。15億6700万元が投じられることになっている。中国最大の塩湖である青海湖は、青海チベット高原の生態系を維持するだけでなく、西部地区の砂漠化が東部地区へ拡大するのを防ぐ天然の障壁になると期待されている。
また中国科学院は2008年1月28日、同研究院傘下の新疆生態地理研究所や新疆農業大学などが共同で乾燥・砂漠化地域の生態系修復再生研究プロジェクトに着手したことを明らかにした。
同プロジェクトでは、砂漠化地域の修復や退化した生態系の回復・再生技術の研究とモデル地区の建設、生態環境保全技術の研究開発とモデル地区の建設、乾燥・砂漠化地域の水・土壌生態環境の安全と生態系の持続的管理に関する研究などが行われる。
外国との緑化プロジェクトも活発に行われている。韓国のヒュンダイ自動車、中国の北京ヒュンダイ自動車、韓国の環境保護組織の「環境運動連合」、内モンゴル自治区のアバグ旗人民政府は2008年5月5日、砂漠化防止・緑化プロジェクトに関する協力協定を締結した。
一方、トヨタ自動車は2008年5月31日、河北省豊寧満族自治県に建設していた「21世紀中国首都圏環境緑化交流センター」の開所式を行った。中国科学院や河北省林業局、特定NPO法人「地球緑化センター」と共同で推進している「21世紀中国首都圏環境緑化モデル拠点」プロジェクトの一環として新設した。
トヨタなど4機関は、2001年から日中共同事業として、中国の首都圏近くまで拡大している砂漠化の防止に向けた緑化活動を展開している。2010年までの計画では、緑化交流センターの建設のほか、500ヘクタールに及ぶ植林を行う。
3)地質災害の予防と対策
「2007年中国国土資源公報」によると、2007年には全国で各種の地質災害が2万5364件発生し、死傷者数が1123人(死者598人、行方不明者81人)に達した。こうした地質災害の直接的経済損失は24億8000万元と推定されているが、前年に比べると、死者・行方不明者数が12.3%、経済損失が42.6%、それぞれ減少した。以下のような、地質災害の予防と対策が強化されたことが寄与したと見られている。
- 地質災害予防の知識普及がはかられた
- 重点地区等の地質災害に関する詳細な調査が行われた
- 増水期の地質災害モニタリング警報システムが整備された
このほか、三峡ダム地区の地質災害の予防と対策で重要な成果が得られた。湖北省と重慶市では2007年末までに応急措置プロジェクト229件、堤防のかさ上げ工事1002件、非応急措置プロジェクトの調査および実施可能性調査231件が終了し、128ヵ所で移転・避難プロジェクトが実施された。
中国では、土地の汚染問題も深刻になっている。環境保護部によると、中国の耕地面積の10%が汚染しており、経済的損失は200億元に達している。そうしたなかで中国科学院は2008年9月2日、傘下の南京土壌研究所が開発した重金属や残留農薬で汚染された土地の修復技術が成果をあげたことを明らかにした。
中国科学院によると、南京土壌研究所は20年間にわたる汚染土壌の修復研究によって、スーパー植物や鉱物、細菌などを利用して土壌中の重金属や残留農薬の吸収・吸着固定化に成功したという。
主要参考文献:
- 「中国科技統計年鑑」(2002~2007年版、国家統計局・科学技術部編、中国統計出版社)
- 「国家中長期科学和技術発展規劃綱要(2006-2020年)」(中華人民共和国国務院、2006年2月)
- 「国家科技支撑計劃"十一五"発展綱要」(科学技術部、2006年9月)
- 「国家高技術研究発展計劃(863計画)"十一五"発展綱要」(科学技術部、2006年9月)
- 「国家"十一五"科学技術発展規劃」(科学技術部、2006年10月)
- 「道路水路交通科学技術発展戦略」(交通運輸部、2005年2月)
- 「公路水路交通中長期科学技術発展規劃綱要(2006-2020年)」(交通運輸部、2005年9月)
- 「公路水路交通"十一五"科学技術発展規劃」(交通運輸部、2006年2月)
- 「"十一五"西部交通科学技術発展規劃」(交通運輸部、2006年4月)
- 「建設科学技術"十一五"規劃」(建設部、2006年9月)
- 「「建設事業"十一五"重点推進技術分野」(建設部、2006年12月)
- 「地震科学技術発展規劃(2006-2020年)」(地震局、2006年3月)
- 「国家地震科学技術発展綱要(2007-2020年)」(地震局、2007年8月)
- 「国土資源部中長期科学技術発展計劃綱要(2006-2020年)」(国土資源部、2006年3月)
- 「中長期鉄路網規劃」(鉄道部、2004年1月)
- 「中長期鉄路網規劃(2008年度調整版)」(鉄道部、2008年11月)
- 「公路水路交通第"十一五"発展規劃」(交通運輸部、2006年9月)
- 「総合交通網中長期発展規劃」(国務院、2007年10月)
- 「2007年国土資源部科技成果統計分析報告」(国土資源部)
- 「2007-2008城市科学学科発展報告」(中国科学技術協会主編、中国城市科学研究会編著、中国科学技術出版社、2008年3月)
- 「2007年中国国土資源公報」(国土資源部、2008年4月)
- 「中国科学技術発展報告2006」(科学技術部、科学技術文献出版社、2008年1月)
主要関連ウェブサイト:
- 国家発展改革委員会(http://www.ndrc.gov.cn)
- 科学技術部(http://www.ndrc.gov.cn)
- 住宅都市建設部(http://www.cin.gov.cn)
- 交通運輸部(http://www.moc.gov.cn)
- 鉄道部(http://www.china-mor.gov.cn)
- 中国地震局(http://www.cea.gov.cn)
- 国土資源部(http://www.mlr.gov.cn)
- 中央人民政府網(http://www.gov.cn)
- 国家科技支撑計画網(http://kjzc.jhgl.org)
- 国家重点基礎研究発展計画網(http://www.973.gov.cn)
- 中国科学技術協会(http://www.cast.org.cn)
- 中国科技統計網(http://www.sts.org.cn)