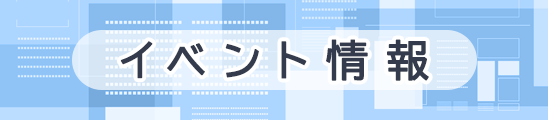次世代脳研究を考える
2010年 8月 3日

藤井 直敬(ふじい なおたか):
(独)理化学研究所 脳科学総合研究センター 適応知性研究チーム チームリーダー
一九六五年、広島生まれ。東北大学医学部卒業。同大学院、マサチューセッツ工科大学、理化学研究所脳科学総合研究センター象徴概念発達研究チームを経て、現在は同センターにて適応知性研究チームを率いる。著書に『つながる脳』(毎日出版文化賞受賞)『予想脳』『ソーシャルブレインズ入門』など。東京テクノフォーラム21・第16回ゴールドメダル賞受賞。
はじめに
脳科学は生物学の一部でありながら、生物学に収まらず、自然科学の幅広い領域と繋がりをもつ、ヒトを理解するための広範な学問領域である。言い換えるなら、脳科学は、ヒトを知りたい、自分を知りたいという私たちの根源的な欲求に応えるための学問と言える。
脳に対する科学的アプローチが本格的に始まったのは1950年代以降であり、これまで様々な手法を用いて様々な脳機能が明らかにされてきた。しかし、半世紀以上経った現在においても、その知見に関して科学的に曖昧なものが少なくない。それはなぜだろうか。それは、私たちが最も知りたいと考える、知性を支える高次認知機能に対してどのようなアプローチをとるべきなのか、どのように記述し理解すればいいのか、その方法がまだよく分かっていないからである。
社会的適応と知性
普段の私たちの脳は、環境の変化に適切に対応し、その変化に応じた行動の最適化を行っている。このような脳機能を適応的脳機能という。しかし、現在の脳科学は,適応機能について非常に限られた知識しか持ち合わせていない。この場合の適応機能とは、それぞれのヒトの周辺に埋め込まれている多様な社会環境文脈を適切に読み取り、その文脈を参照しながら、自分自身と他者との関係性にもとづいて最適な行動を選択するために必要な知的機能となる。
ここで重要なのは、社会環境文脈が常に変化しているということである。文脈を構成しているのは自然現象だけでなく、自分自身の行動であったり、他者の行動であったりする。特に他者の行動は予測困難なことが多く、適切な行動を選択するためには、常に文脈の変化に敏感でなければならない。
なぜ、私たちは環境文脈に敏感でなければならないのか。それは、その場の文脈に合った適応的な行動をとらないと、多くの場合で自己の社会的存在が脅かされるからである。
たとえば、満員の通勤電車の中で、隣に立っている同僚が突然大きな声で歌を歌い始めたとしたらどうだろう。おそらく周りの誰もがびっくりし、困惑するだろう。そして、知り合いであるあなたは他人の振りをするのではないか。しかし、カラオケボックスで同じように大声で歌を歌っても何の問題も起きない。同じ行動を行ったとしても、その意味は、そのヒトを取り巻く状況によって全く異なるのはなぜか。そんなことは当たり前だと思うかもしれないが、われわれがそのような文脈依存的な社会のしくみに気がつくのは、非適応的な行動に直面したときだけである。それほど、普段の私たちは文脈から外れた行動を嫌う、実に適応的な生き物なのである。それは、すなわち、脳が非適応的な行動を嫌っている事を意味する。
行動の意味を決定するのは、個人ではなく、社会環境に埋め込まれた時々刻々変化する文脈である。もし通勤電車で、大声で歌を歌うような衝動的な行動を毎日続けるなら、そのヒトは徐々にコミュニティから排除される。その瞬間のその空間での文脈が規定するルールに従わない事、すなわち空気を読めない行動は、ヒトの社会的存在を危機的状況に陥れてしまうのである。
サルを使った実験でも同様の現象が報告されている。UC DavisのAmaralらによると、サルの扁桃体を破壊したところ、サルの社会的行動に変化が見られたという。そのサルは、社会性を失い、他のサルの存在のいかんにとらわれる事無く自由に振る舞うようになったのである。サルはヒトと同じように高い社会性をもっていることが知られている。ここで言う社会性とは、上位のサルとの間に起きうる競合関係を積極的に避けようとする下位のサルの適応的行動を指している。正常なサルは、各個体のヒエラルキーに応じて、自己の欲望を抑制する。つまり自分より上位のサルに対して、積極的に抑制を選択することで、個体間に発生する競合が解決されている。
そのような抑制を主体とした社会的問題解決方法が一般的なサル社会において、扁桃体を破壊されたサルは、上位サルに対する抑制を見せなかった。どのサルに対しても自己抑制をしないという事は、行動だけを見るならば、他者に対する抑制を必要としないボスザルと何も変わらない事になる。それでは、そのように振る舞うサルの社会的地位はどうなるかと言えば、群れの中では最下位に置かれるという。つまり、社会のルールに従えないサルは、グループの中で社会的な存在を認めてもらえないのである。この事を逆に言うならば、サル社会は上位のサルの統率よりも、下位のサルが適応的に抑制を選択することで成り立っていると言える。同じ事はヒト社会でも言えるかもしれない。
一方で、「サルの社会性を説明するには抑制だけで良いかもしれない、しかしヒトの社会性でより重要な要素は協調である」という意見も多い。確かにヒトとヒトの間の協調行動は、私たちの社会行動に影響を与える重要な要素である。しかし、協調行動は私たちの社会行動の中で必須の条件ではないことを強調したい。たとえば、電車の中でヒトに席を譲らないヒトがいたとしても、そのヒトが多少非難されることはあったとしても、社会的存在を否定され、排除されることは少ない。しかし、衝動的な行動-電車の中で歌を大声で歌うような事-を抑制出来ないヒトは社会から排除される。つまり、社会がより重視するのは適応的な抑制であり、協調ではないと考えられる。
また、ヒト以外の動物が協調行動を殆ど見せない事も社会性の基盤に協調が無い事を示している。なぜなら、進化的にみて私たちヒトは、サルのもつ社会性を基盤として現在の社会性を獲得したと考える事が自然だからである。むしろ、協調という社会行動は、ヒトが生まれた時から持つ機能なのではなく、生後の発達期に獲得する文化的形質であり、その生物学的な基盤は弱いのではないだろうか。とするなら、社会的脳機能のしくみを理解しようとする時に、社会的抑制の神経メカニズムを研究対象とすることは理にかなっている。
そのような社会的適応機能こそヒト知性の根源であるという社会脳仮説がある。これは、1975年ハンフリーが“Social Function of Intellect”の中で議論した仮説であり、以後様々な場面で他の要素と比較しながら議論が続けられてきた。当然ながら、何が原因で私たちヒトが他の動物種から隔絶した高い知性を獲得できたのかをひとつに決定することは困難だが、少なくとも進化的圧力の1要素として、社会的要素の影響は強かったと言って良いに違い無い。
つまり、ヒト知性の要である適応機能を理解するには、本来の脳が最も注意を払っている社会的文脈と適応行動、そしてその時の脳活動を関連付けなければならない。しかしながら、従来の脳科学では、そのような研究を行う事が出来なかった。なぜなら、社会的文脈や他者の行動を、実験環境で実験者が自由に制御することが難しく、かつそれらを記録し、科学的に記述する方法も存在しなかったからである。
そのため、従来の実験では、極めて自由度の低い、予測可能な学習済み課題環境で、しかも脳内の限られた領域からの神経活動記録を行っていた。過去半世紀に渡る脳科学の知見の多くはそのような手法で獲得されたものである。もちろん、それによって蓄積された膨大な知見により、半世紀前と比べて脳機能については大分見晴らしがよくなってきた。特に視覚や記憶、意思決定などの個別の機能については、随分沢山のことが明らかにされてきた。
しかし、そのような自由度の低い、低次元実験環境で得られた実験結果をいくら積み重ねても、脳機能の全体像を理解する事は無理なのではないかという議論が2000年前後から研究者たちの間に広がってきた。一つ一つの脳機能のしくみが分かっても、それらが複数同時に動いている時の機能が単純な足し合わせで説明できないことが分かって来たからである。断片的な知識は、それが沢山集まっても全体像をつくる手助けはしてくれない。なぜなら、実験のデザインの都合で削られた次元に関連する情報を、後から取り戻す事は決してできないからだ。そして、失われた次元の中にこそ、異なる機能をつなぐカギが秘められている。
多次元生体情報記録手法
その問題を解決するため、われわれは、サルを対象とした多次元生体情報記録手法という新しい実験手法を開発した。この実験手法では、サルの行動の自由度を可能な限り抑制しない。しかし、自由度を上げると言う事は、行動記録が格段に難しくなるということである。
そこで、モーションキャプチャを導入して、サルの自由行動の全てを完全に記録することとした。さらに、それ以外の身体・生理情報、たとえば眼球位置、視野映像、血圧、呼吸等も可能な限り同時に記録する。一方、脳内の神経活動は、慢性留置型ECoG電極を独自に開発することで脳内の広範囲から同時に記録することが出来ようになった。この慢性留置型ECoG電極を用いた記録手法の信号安定度は極めて高く、これまでの神経生理学的手法を大きく書き換える可能性を秘めている。また、実験には複数の個体を参加させ、相互作用中の2頭以上の動物から同時に行動と神経活動を記録する技術を実現した。このような高い自由度を保ったまま、脳活動と行動、そしてそれ以外の様々な生体情報を同時に、しかも安定して記録し続ける事が可能な研究施設は世界でも他に例をみない。
このような実験環境を整備し、実際のサルを用いて実験を開始した。この実験では、サルの行動抑制を基本とした適応的行動と、その時の脳活動の相関を明らかにすることを目的としている。そのためには、サルが自発的に行動し、文脈に応じてその行動を抑制するような環境条件を作り出さなければならない。しかし、これまでの実験課題では、そのような自発的適応行動を発現させる行動課題は全く開発されていなかった。
そこで、われわれは2頭のサルを向かい合わせに座らせて、その真ん中にエサを置くという条件でサルの行動を観察してみた。2頭のサルの距離は十分離れており、エサが置かれる周辺で両者の手が触れ合う事はあっても、それ以外の身体や顔などにお互いが触れる事はない。つまり、両者の間につかみ合いの喧嘩が起きる事はなかった。また、2頭のサルは個別のケージで暮らしている為、実験室で発生する社会的競合を実験後に引きずる事はない。
そのような環境下では、お互いが初めて会ったサル同士の場合、はじめのうちは、どちらのサルも躊躇することなくエサに手を伸ばす。その時、エサをつかむのは単純に早くエサに手を伸ばした方のサルである。この状況では、どちらのサルもエサ取り行動を抑制することはない。
しかし、この課題をしばらく続けると、突然一頭のサルがエサを取らなくなる。このサルが見せる抑制的行動が、どのような仕組みで発現するのかは不明である。しかし、われわれが観察した10ペア以上の個体間で、常に片方のサルが、エサを取るのを止めた。この行動抑制は、長期間に渡って持続する。
つまり、2頭の間に社会的な上下関係が構築されれば、競合環境を操作することで、社会的行動抑制を安定的に実験環境で取り扱えるが分かった。そこでわれわれは、このような関係性を持った個体間におきる適応行動とそのときの脳活動を記録する事で適応的脳機能の解明を進めている。
ブレインマシンインターフェイス(BMI)
一方、われわれが開発した多次元生体情報記録手法は、社会神経科学に用いるだけでなく、ブレインマシンインターフェイス(BMI)という技術の開発にも有用だということが明らかになった。
BMIは、脳と外部の人工的デバイスの間をつなぐための技術であり、外傷、神経疾患、脳梗塞などが原因として失われた身体機能を補償するための技術として開発が進められている。その手法は、侵襲型と非侵襲型の2種類に大別出来るが、われわれの多次元生体情報記録手法は侵襲型に属する。
われわれの記録技術がなぜBMIに転用可能かと言えば、われわれの慢性留置型ECoG電極がもたらす極めて高い信号の質と安定度による。
これまでの神経活動記録は、ある瞬間に偶然記録できる神経活動を記録するものであり、時間が経過すると記録できる神経細胞が変わることが多かった。たとえば、ある日に記録した神経細胞活動を、続けて何ヶ月も記録することは現実的に無理だった。実際のところ、一日、もしくは数日すら難しい。
BMIは、記録される神経活動のもつ情報を解析し、脳の意思を抽出する予測モデルによって機能する。この予測モデルは、記録される神経活動に最適化され、予測性能はそれに依存する。そのため、神経活動記録の安定度が低いと、予測モデルを頻繁に更新しなければならない。この安定度の低さが、これまでのBMIの最大の難点であった。
しかし、われわれの慢性留置型ECoG電極は、この最大の難点を克服した。われわれの電極から記録出来る神経活動は日を跨いでも殆ど変化することなく、それゆえ予測モデルの予測性能も数ヶ月に渡って殆ど変化しなかった。このような高い安定度を持つ記録手法と解析手法を実現した研究室は世界中でも他に無く、今後のBMI技術の本格的な臨床応用へ向けて、最大の難関を超える事ができたと考えられている。
一方、BMI技術は失われた機能の再建に限らず、様々な高次認知機能の解明にも役に立つことが明らかになってきた。たとえば、BMIの予測モデルを応用する事で、脳内のどの部位が、どの瞬間で、どの変数に関係する情報をどれくらい持っているかを定量的に示す事が可能になる。勿論、類似の解析は、これまでも可能であった。しかし、われわれの手法が最も異なるのは、全ての脳領野を記録対象とし、網羅的に解析を行う事にある。それによって、ネットワーク全体で情報がどのように処理されているかという、これまでにない新しい視点を得る事ができると期待されている。
ローカル機能の解明からネットワーク機能の解明へ
われわれは、現在これまでの手法をさらに拡張し、脳内のあらゆる部位から神経活動を記録するPan-Brain Recording(PBR)の手法を開発している。この大規模記録により、脳内の各部位から個別の情報を抽出するだけでなく、領域間の情報の流れや関係性を因果的に記述する事が可能となる。
しかし、そのような巨大ネットワークの構造や、そのしくみを理解する為の解析方法はまだ十分確立されていない。その一番の理由は解析技術を開発するための基盤データが存在しなかったからである。われわれが開発を行っている、PBRやBMI等の技術は、その基盤となる大規模データを提供するためのプラットフォームとなる。そして、それによって初めて脳のネットワーク機能の解明に正面から挑む事が可能になる。われわれは、そのためのデータ共有サービスProject TYCHOを準備中であり、これによってあらゆる領域の研究者が、大規模神経活動データに自由にアクセス出来る環境を提供することを目指している。
われわれは、これまで複雑なネットワークシステムである脳機能を明らかにするために、様々な新しい試みを行ってきた。それぞれの試みはお互い何の関連が無いように見えるが、それらを統合する事で、これまでの神経科学が手にすることのなかった強力なツールとなる。
これからの脳科学は、これらの新しい技術を導入し、周辺研究領域と旺盛に連絡を取りあう事で、多次元空間を自在に操る複合研究領域として大きく発展していくだろう。






 インドのスタートアップ・エコシステムとディープテック・スタートアップ振興策(2025年3月)
インドのスタートアップ・エコシステムとディープテック・スタートアップ振興策(2025年3月)